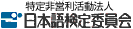日本語検定 受検規約

第1章 総則
(総則)
- 第1条
- 日本語検定(以下、「当検定」といいます)は、特定非営利活動法人日本語検定委員会(以下、「当委員会」といいます)が実施する日本語の知識と運用能力(敬語・文法「言葉のきまり」・語彙「いろいろな言葉」・言葉の意味・表記・漢字・総合問題)を測る検定です。
- 以下に規定する申込・受検規約(以下、「本規約」といいます)は、当検定の受検申込者、受検者(以下、単に「申込者」、「受検者」といいます)が確認すべき事項および遵守すべき事項を定めたものであり、申込者および受検者は、当検定の申し込み及び受検にあたり、本規約を必ずお読みいただき、その内容を理解していただいた上で、同意していただく必要がございます。
- なお、当検定の申し込み方法や受検に関する最新の情報については、随時、公式サイトで公開いたしますので、必ずご確認ください。
第2章 用語の定義
(用語の定義)
- 第2条
- 本規約における用語の定義は、以下のとおりとします。
- 「一般会場受検」=当委員会が設置する検定会場で実施する受検方法。
- 「準会場受検」=学校・学習塾・企業・団体等が自らの施設を会場として実施する受検方法。
- 「受検申込者」=検定の申し込み手続きを行うまたは行った個人(本人が未成年者の場合はその保護者等)。
- 「受検者」=検定日当日に受検される、または受検された個人。
- 「団体受検実施担当者」=団体受検を実施される機関の、当検定の申し込み・実施責任者。
- 「個人申込」=申込者個人(本人が未成年者の場合はその保護者等)が「一般会場受検」を申し込む方法。
- 「団体申込」=学校・学習塾・企業・団体等の団体受検実施担当者が申込者数を原則合計5人以上集め、団体として申し込む方法。
- 「申込方法」=「個人申込」「団体申込」のいずれかの方法。
- 「公式サイト」=当委員会が公式に公開するホームページ(https://www.nihongokentei.jp/)。
- 「個人受検」=個人で申し込みをし、受検をする方法。
- 「団体受検」=団体登録のうえ、一括して原則合計5人以上の申し込みをし、受検をする方法。
- 「機密情報」=受検に関して知りえた情報全般。
- 「サービスの利用期間」=申し込み時から個別カルテ発送時までとする。
第3章 申し込み等
(受検資格・条件)
- 第3条
- 当検定の受検資格・条件は以下のとおりです。
- 原則として、国籍・年齢・職業・学歴等を問いません。
- 過去に受検した級に関係なく、どの級でも受検することができます。
- 未成年者が受検する場合は、保護者が本規約および公式サイトで受検上の案内や注意事項を確認の上、受検が可能かどうかを判断して申し込みを行ってください。
- 申込者または団体受検の場合の団体受検実施担当者が次に掲げる事由に該当する場合、当委員会は、当検定の申し込みをお断りする場合があります。
- ①申込内容に虚偽の記載が認められたとき
- ②受検料の支払いを怠り、または怠るおそれがあると当委員会が判断したとき
- ③当検定を利用して第三者の権利を侵害し、または違法行為をなすおそれがあると当委員会が判断したとき
- ④申し込みが日本語の知識及び運用能力を測るという検定目的から逸脱していると当委員会が判断したとき
- ⑤指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員または関係者、その他の反社会的勢力に属していると認められるとき
- ⑥当検定の申し込みに関し、当委員会の職員その他の関係者に対して、暴力的行為を行い、合理的範囲を超える負担を要求し、または脅迫的言辞を用いたとき
- ⑦風説を流布し、または偽計もしくは威力を用いて当委員会の信用を棄損または業務を妨害したとき
- ⑧本規約に違反する行為があったとき
- ⑨その他、当委員会が不適当と認めたとき
(併願受検)
- 第4条
- 併願受検(同一の申込者が同一の検定日に複数級を受検することをいいます)は、以下のとおりとします。
- 「一般会場受検」では、同一時間に実施する受検級は併願受検できません。
- 「準会場受検」では、同一の申込者が、同一の検定日に同一の検定会場に限り、併願受検ができます。
- 同一の受検申込者が、同一の検定日に「一般会場受検」「準会場受検」を組み合わせて受検することはできません。
- 二つの級まで受検することができます。
- 同一回に同じ級を重複して申し込みおよび受検することはできません。
(検定概要の確認)
- 申込者は、受検する級、受検料、検定開始時刻、検定時間、検定の概要および受検上の注意事項等を確認の上、申込方法の手順に従い申し込みを行ってください。
(個人情報の取り扱い)
- 第6条
- 申込者は、当委員会の公式サイトに公開する「個人情報保護方針」および「個人情報の取り扱いについて」(https://www.nihongokentei.jp/guide/persdata/)に必ずご同意の上、お申し込みください。必要な情報が提供されない場合、検定の受検、採点、結果の発行等ができない場合があります。
- 2 EU加盟国及び欧州経済領域(EEA)の一部であるアイルランド、ノルウェー、リヒテンシユタインの申込者または受検者から取得する個人情報は、日本語検定の円滑な実施、業務運用、結果の発行等のサービスに関わる用途に使用します。個人情報の取り扱いは申込者または受検者との間の契約の履行のために処理が必要な場合、または契約の締結前にその求めに応じて手続きをとるために取り扱いが必要な場合に行われるほか、申込者または受検者の同意に基づいて行われることがあります。当委員会は申込者または受検者の個人情報の処理の全部または一部を、採点業者等の第三者に委託することがあります。個人情報は日本に転送され、当委員会の日本国内のサーバーに保存されますので、転送・保存の過程において、不正アクセスその他要因による個人情報の流出または喪失のおそれがあります。当委員会は申込者または受検者の個人情報を日本に転送するときには、EU一般データ保護規則内の標準契約条項に基づいた適切な保護措置を講じ、適切に管理します。申込者または受検者は日本に個人情報が転送される場合の保護措置の内容の詳細を個人情報の取り扱いに関する連絡先である当委員会(東京都北区堀船2-17-1 特定非営利活動法人日本語検定委員会)に連絡することにより知ることができます。取得した個人情報は、法律でそれ以上の期間の保存が求められていない限り、申込者または受検者からの削除要請があった場合または当委員会が定める保存期間の経過後まで保存されます。申込者または受検者は、法律の認める範囲内で自らの個人情報へのアクセス、訂正、消去または自らに関する処理の制限、もしくは処理に対する異議申し立て、および、提供した個人情報について、構造化され、一般的に利用され機械可読性のある形式で受け取ることおよび提供した個人情報を他の管理者に移行することを当委員会に要求できます。なお、当委員会の個人情報の取り扱いに不満がある場合には、EU加盟国及び欧州経済領域(EEA)の一部であるアイルランド、ノルウェー、リヒテンシユタインの監督機関に苦情申し立てをすることができます。個人情報が同意に基づいて取り扱われている場合、この同意はいつでも撤回する権利があり、この同意の撤回は、撤回前のデータ処理の適法性に影響をあたえるものではありません。申込者または受検者の情報は契約の履行のために必要であり、これらの情報が提供されない場合には受検、合否の判定またはその通知ができません。
(申し込みのキャンセルや変更の禁止)
- 第7条
- 理由の如何によらず、原則としてお支払い後の受検料の返還、次回への繰り越し、受検者の変更、級の変更、受検希望都市の変更、他の受検方法への変更はできません。また、申込締切日後の申し込みは承れません。
(配慮が必要な受検者の対応)
- 第8条
- 「一般会場受検」をされる方で、配慮が必要な受検者は、申し込み前に当委員会の公式サイトの「個人受検についてのお問い合わせフォーム」または電話で事前に当委員会に相談してください。「準会場受検」で申し込みされる場合は、団体受検実施担当者に相談してください。
- 2 当委員会は、前項前段の相談を受けた場合、当該社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をするよう努めますが、物理的、技術的、人的および経済的な制約等により、受検をするために十分な程度に社会的障壁を除去できない場合は、会場の変更、または申し込みをお断りせざるを得ない場合があります。
(団体申込)
- 第9条
- 団体申込は、団体受検実施担当者を通じて行いますので、申し込みに必要な書類・受検料は団体受検実施担当者に提出してください。
- 2 「団体申込」に関するお問い合わせは、団体受検実施担当者までお願いいたします。当委員会ではご対応いたしかねます。なお、検定終了後の合否結果・個別カルテについても、団体受検実施担当者を通じて受検者に通知・配付します。
(検定日時・検定会場)
- 第10条
- 「一般会場受検」の場合は、受検票を発行します。受検票に記載された検定日時・会場で受検してください。
- 2 「準会場受検」の場合は、当該団体受検の団体受検実施担当者が指定する検定日時・会場で受検してください。なお、この場合は、原則として受検票の発行はありません。
(受検票について)
- 第11条
- 「個人申込」の場合は、検定日の7日前までを目安に受検者あてに送付いたします。検定日の5日前になっても受検票が届かない場合は、当委員会までご連絡をお願いいたします。
- 「団体申込」で「一般会場受検」の場合は、検定日7日前までを目安に団体受検実施担当者あてに送付いたします。団体受検実施担当者から受検票を受取ってください。
- 2 検定日までに受検票に記載の申込者情報、注意事項を必ず確認してください。
- 3 受検票で指定された検定日時・会場・受検級の変更等の希望には応じられません。
- 4 1級、2級、3級の受検者は、受検票に顔写真(たて4㎝×よこ3㎝。直近3か月以内に撮影された正面写真(脱帽))を必ず貼り付けて会場にお持ちください。顔写真は、印画紙や写真用紙に印刷されたものに限ります(コピー用紙、普通紙は不可)。顔写真の裏面には氏名、受検番号を記入し、指定の欄にしっかりと糊付けしてください。顔写真の貼り付けがない場合は、WEB合否確認を不可とし、検定結果の発送を行わず、検定結果が無効になる場合があります。
第4章 受検について
(注意事項の遵守)
- 第12条
- 検定の当日は、本規約、受検票(「一般会場受検」の場合のみ)、公式サイト、問題用紙の表紙および検定会場に掲示された注意事項・禁止事項を確認し、遵守してください。また、検定監督者の指示に従ってください。
(第三者による受検の禁止)
- 第13条
- 検定当日に受検することができるのは受検者本人のみです。第三者による代理受検および受検する権利の譲渡は一切禁じます。
- 2 検定の当日に本人確認ができないとき、または申し込みの事実が確認できないときは、当検定の受検をお断りする場合があります。
(所持品の自己管理)
- 第14条
- 会場内での貴重品、現金、手荷物、携帯品の管理は受検者自らが行ってください。盗難、紛失等が生じた場合、当委員会は一切の責任を負いかねます。
(必須の持ち物)
- 第15条
- 受検時に必須の持ち物は以下のとおりです。
- 「一般会場受検」の場合
- ①1~3級=受検票(顔写真を貼り付けたもの)、筆記用具
- ②4~7級=受検票(顔写真の貼り付けは不要)、筆記用具
- 「準会場受検」の場合
- ①筆記用具
- ※筆記用具とは、黒のHB、B、2Bの鉛筆またはシャープペンシル、および消しゴムを指します。
- ※受検票に「上履き持参」と記載されている会場は、受検者自身で上履き・靴袋等を用意してください。
- ※必須の持ち物・上履きを忘れた場合、当委員会は貸与いたしません。
(使用許可が必要となる物)
- 第16条
- 受検時、当委員会または検定監督者の許可がある場合にのみ使用できるものは以下のとおりです。
- 腕時計(音が出ないもの)
※携帯電話・スマートフォンを時計として使用することは認められません。 - 座布団、クッション
- ルーペ
(使用禁止となる物)
- 第17条
- 受検時に使用禁止となる物は以下のとおりです。
- 携帯電話・スマートフォンなどモバイル端末
- ウェアラブル端末
- 撮影・録画・録音のできる電子機器
- 音の出る一切の機器
- 参考書、辞書、教科書、問題集などの書籍類
- 飲食物
※ただし、飲み物については、熱中症対策や体調不良、健康被害が見込まれる場合に、水筒またはラベルを剥がしたペットボトルのみ持ち込みを許可します。 - 上記の他、当委員会が受検上不要と判断した一切の物
- 2 前項に掲げる物を教室内に持ち込む場合、音の出る物については電源を必ず切った上で、かばんの中に収めてください。電源を切れない場合は付添者に預け、付添者がいない場合は検定監督者に申し出た上で、その指示に従ってください。
- 3 第1項に掲げるものにつき、健康上の理由等やむを得ない理由により使用を希望する場合には、事前に当委員会へ申し出て、使用許可を得た上で使用してください。
(遅刻時の対応)
- 第18条
- 遅刻の場合は、検定を開始してから20分以内であれば入室・受検が可能です。ただし、検定時間の延長等の措置はありません。
(教室内環境の留意点)
- 第19条
- 教室内の室温については、すべての受検者の要望に沿うことができませんので、体温調節のできる服装でお越しください。
(控え室)
- 第20条
- 受検者または付添者の方の控え室については、原則設置しておりません。
(試験環境)
- 第21条
- 受検時間が異なる他級の受検者が同時受検をしているため、入退室音等があり無音にはなりません。
- 2 一般会場受検の場合、座席は指定いたします。準会場受検につきましては、団体受検実施担当者にお尋ねください。
(交通手段)
- 第22条
- 必ず公共交通機関をご利用ください。会場周辺の道路混雑や近隣住宅への配慮から車での送迎・自転車・バイクでの来場についてもご遠慮ください。
(検定監督者への質問)
- 第23条
- 検定監督者に対する検定問題の内容についての質問には一切お答えできません。
(途中退室および再入室について)
- 第24条
- 「一般会場受検」「準会場受検」ともに、検定開始30分後から検定終了10分前までであれば、受検途中でも退室できます。なお、途中退室された場合、再入室はできません。
- 2 お手洗いや体調不良により一時退室する必要がある場合は挙手し、検定監督者へ申告してください。一時退出した際の時間延長の措置はありません。
(検定問題の複製・漏えいの禁止)
- 第25条
- 検定問題の著作権は当委員会に帰属します。当委員会の許可なく検定問題の一部または全部を複製し、または他に伝え、漏えい(インターネット、SNS等への掲載を含む)することは、法令により許される場合を除き一切禁じます。
(検定情報の漏えいの禁止)
- 第26条
- 検定会場内での録音・撮影(動画・静止画)行為や、検定または検定の運営に関して知り得た情報について他者に開示し公開することは、一切禁じます。
(問題用紙・答案用紙の持ち出しについて)
- 第27条
- 問題用紙は、「一般会場受検」の場合は受検後持ち帰ることができます。「準会場受検」の場合は団体受検実施担当者の指示に従ってください。
- 2 答案用紙は、いかなる理由においても教室から持ち出すことを禁じます。
(検定試験中の記録について)
- 第28条
- 厳正公平な検定実施、検定の質的向上および調査研究のため、検定時の状況を記録(録画・録音)することがあります。なお、記録された情報は、法令に定められた特別な場合を除き第三者に開示することはありません。
- 2 前項の他、広報の一環として受検時の状況を撮影(静止画)する場合があります。撮影した画像を使用する場合は、個人が特定できないよう慎重かつ適切に画像処理をいたします。
(迷惑行為・違反行為・不正行為)
- 第29条
- 本規約に違反する行為の他、以下に示す行為が認められる場合は、口頭または文書によって注意喚起することがあります。
- 受検者および付添者が、検定監督者の指示に従わないとき
- 受検者および付添者が、本規約の他、公式サイト、検定会場等で示される禁止事項に従わないとき
- 他の受検者に迷惑をかける行為・他の受検者へ援助行為・検定を妨害したとき(年少者につき、集中力低下による他の受検者への迷惑行為を含みます)
- 不正行為(カンニング行為等)をしたとき
- 2 前項の規定に基づき注意を促されたにも関わらず改善が見られなかった場合、その時点で退場・失格(または検定結果を無効)とし、受検料の返還もいたしません。また、当該受検者の将来における当検定の受検を禁止することがあります。
- 3 受検後に禁止事項を行ったことが判明した場合、当委員会による検定結果送付の中止、もしくは検定結果の取り消しを行うことがあります。
(インフルエンザ等その他感染症について)
- 第30条
- インフルエンザ等その他感染症(学校保健安全法施行規則(昭和三十三年文部省令第十八号)第3章第18条に定める各種感染症)に罹患している、あるいは罹患の疑いがある場合は、受検を控えてください。インフルエンザ等その他感染症に罹患している、あるいは罹患の疑いがある受検者が検定会場に来られた場合、受検をお断りいたします。
第5章 受検後について
(解答の開示)
- 第31条
- 解答の開示は、原則、検定日から4日前後で公式サイトに公開します。
(合否確認について)
- 第32条
- 「個人受検」の合否確認については、検定日から約25日後に公式サイトで公開します。この場合、受検票に記載されている受検番号とパスワードが必要になります。
- 2 「団体受検」の合否確認については、検定日から約25日後に公式サイトで公開し、団体受検実施担当者のみがこれを確認することができます。この場合、団体の団体コードとパスワードが必要になります。
- 3 前二項に掲げるパスワードまたは団体コードを紛失した場合、再発行はできません。
(検定結果の送付について)
- 第33条
- 検定日から約35日後に、「個人受検」の場合は受検者本人が申し込みの際に登録した住所に、「団体受検」の場合は団体受検実施担当者あてにそれぞれ検定結果を送付いたします。
- 2 「個人受検」で郵便が不着の場合は、当委員会までご連絡をお願いいたします。保管期間は3か月です。
- 3 前項の送付物の内容に汚損、破損等が生じた場合、または個人情報の誤りや変更がある場合には、送付物の到着後3週間以内に、「個人受検」の場合は当委員会に、「団体受検」の場合は団体受検実施担当者に申告してください。
(検定結果の送付内容について)
- 第34条
- 検定結果の内容は以下のとおりとします。
- 「個人受検」の場合 認定証・認定証明書(認定の場合)、個人カルテ、アンケート
- 「団体受検」の場合 上記(1)の他に、団体成績一覧表(希望する団体のみ)
(問題内容・採点結果についての異議申し立ての禁止)
- 第35条
- 検定問題の内容や採点結果・合否結果についての異議の申し立ては一切受け付けません。
第6章 その他の条項
(再委託)
- 第36条
- 当委員会は、当検定の申し込みから結果の通知等に至るまで円滑かつ滞りなく履行するために必要な業務の全部または一部を、当委員会の指定する第三者(以下、「委託先」といいます)に委託できるものとします。
- 2 前項の規定に基づき委託を行う場合、当委員会は、委託先に対して、当委員会が申込者および受検者に対して負う機密保持義務と同等の義務を負わせ、適切に監督を行うものとします。
(機密保持)
- 第37条
- 申込者および受検者は、当検定の申し込みおよび受検にあたり、当委員会から開示され、または知り得た一切の機密情報を、第三者に開示・漏えいしてはならないものとします。
- 2 前項の規定は、日本語検定に関するサービスの利用期間が終了した後も有効とします。
(免責事項)
- 第38条
- 当委員会は、台風や大雪、大地震等の災害や、公衆衛生に関わる緊急事態、伝染病の流行等により、当検定の一部または全部を中止することができるものとします。その場合は、公式サイトへの掲載等を通じて受検者および団体受検実施担当者へ通知いたします。
- 2 前項において受検者に損害が発生した場合でも、当委員会は検定料の返還を含めいかなる責任も負わないものとします。
- 3 第1項の他、次の各号に掲げる場合についても、当委員会は一切責任を負わないものとします。
- 申込者または受検者(付添者を含む)間でトラブルが起こった場合
- 検定会場内および検定会場への往復経路における事故等、受検者の体調急変またはそのおそれが生じた場合
- 団体受検実施担当者による不正等が発覚し、当委員会の判断により当該団体受検における検定が無効とされた場合(この場合、受検者に対するすべての責任は当該団体受検の団体受検実施担当者が負うものとします。)
(当委員会の損害賠償責任)
- 第39条
- 当検定への申し込み及び受検に起因して、受検者に損害が発生した場合、受検者に発生した損害が当委員会の債務不履行又は不法行為に基づくときは、当委員会は、申込者および受検者が実際に支払った検定料相当額を上限として損害賠償を負うものとします。ただし、当委員会の故意または過失に基づくときは、当該上限は適用せず、適用される法令の範囲で損害賠償責任を負うものとします。
(申込者および受検者の損害賠償責任)
- 第40条
- 申込者および受検者は、日本語検定の受検に際し、当委員会または第三者に損害を与えたときは、その損害について法令に基づく損害賠償責任を負うものとします。
(本規約の変更)
- 第41条
- 当委員会は、次の各号に該当する場合には、本規約の変更の効力発生時期を定め、本規約を変更する旨、変更後の本規約の内容およびその効力発生時期について、公式サイトへの掲載をもって、本規約を変更することがあります。また本規約を申込者および受検者に事前に通知することなく変更することがあります。
- 本規約の変更が、申込者または受検者の一般の利益に適合するとき
- 本規約の変更が、本規約に係る契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき
- 2 前項第2号に掲げる場合、当委員会は、変更後の本規約の内容を効力発生時期が到来するまでに公式サイトへの掲載を行うものとします。
(知的財産権)
- 第42条
- 当検定の検定問題や当委員会が提供する当検定に関する資料の著作権等の一切の知的財産権は当委員会に帰属し、日本の著作権法およびその他関連する法令によって保護されています。したがって、受検者および団体受検実施担当者は、当委員会の承諾を得ることなく、これらを無断で複製、改変、その他の利用をすることはできません。
(準拠法)
- 第43条
- 本規約の成立、効力、履行および解釈については、日本法が適用されるものとします。
(管轄)
- 第44条
- 当検定の申し込みおよび受検に関連して訴訟が生じた場合には、訴額に応じ、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
令和3年4月27日
特定非営利活動法人日本語検定委員会