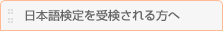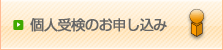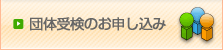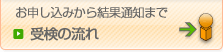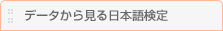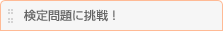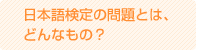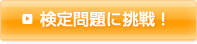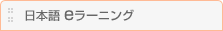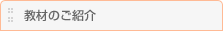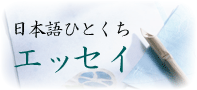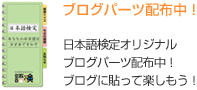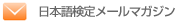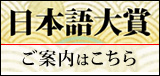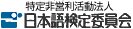検定まつり-「日本語検定」問題の解答および解説
2012.10.28
検定まつり-「日本語検定」にチャレンジありがとうございました!!
平成24年10月28日(日)、第22回神保町ブックフェスティバル会場内、「検定まつり~検定あれこれ大集合!」において配付されました「日本語検定」問題の解答および解説を掲載しています。
九仞の功を一( )に虧くような、致命的失敗だ。
[ ① 勢 ② 迅 ③ 簣 ]
| 答 | 解説 |
|---|---|
| ③ | ③「簣」が適切です。「簣」は、土砂などを運ぶ「もっこ」のこと。「簣」を入れた「一簣(いっき)」は、もっこで運ぶ一杯分の土。「九仞(きゅうじん)の功を一簣に虧(か)く」は、ほとんど成功しかけていたのに、ちょっとした手抜きが原因で失敗し、それまでの努力を無駄にすることをいいます。「九仞の功」が「大変な努力」を、「一簣に虧く」が「ちょっとした失敗でだめになること」を表しています。 |
【会議に際して、部長が部下に】
① 田中さんがお見えになったので、会議室にご案内してください。
② 田中さんが見えられたので、会議室に案内してください。
③ 田中さんがお見えになられたので、会議室にご案内してください。
| 答 | 解説 |
|---|---|
| ① | 前半部分について、①の「お見えになった」は、「来る」の尊敬語「見える」を「お~になる」という尊敬表現の形にしたもので、二重敬語ですが、慣用として認められている言い方で、適切です。②の「見えられた」は、「見える」に尊敬の助動詞「られる」を付けた過剰敬語で、不適切です。③の「お見えになられた」は、尊敬表現の「お見えになる」に尊敬の助動詞「れる」を付けた過剰敬語で、不適切です。後半部分については、謙譲表現「ご~する」を用いた①と③が適切。②は謙譲表現がありません。全体としては、①が適切ということになります。 |
その後の彼の消息は( )として知れない。
[ ① 寂 ② 漠 ③ 杳 ]
| 答 | 解説 |
|---|---|
| ③ | ③「杳」が適切です。「杳(よう)として」は、問題とする人の消息などがはっきりとしない、分からない様子を表します。①を用いた「寂(せき)として」は、しんと静まり返って、物音一つしない様子、②を用いた「漠(ばく)として」は、話の内容などが曖昧(あいまい)だったり広すぎたりして、はっきりしない様子を表します。 |
来月の研修会は、企画部の希望どおり、営業部と合同で( ① 行わせ ② 行わさせ ③ 行わせさせ )てもらうことになりました。
| 答 | 解説 |
|---|---|
| ① | 「行う」は五段活用動詞なので、使役表現は未然形「行わ」に使役の助動詞「せる」を付けます。したがって、①「行わせ(て)」が適切です。②「行わさせ(て)」は、「せる」の代わりに別の使役の助動詞「させる」を付けた、いわゆる「さ入れ言葉」です。③は、「行わせる」に、さらに「させる」を付けた不適切な形です。 |
【こけら落とし】
① 新しくできた劇場で、演劇界の名手を集めてこけら落としが行われた。
② ビルの起工にあたって、建設予定地でこけら落としが行われた。
③ 日本初出店となるファーストフード店で、開業を前に盛大なこけら落としが行われた。
| 答 | 解説 |
|---|---|
| ① | 「こけら落とし」は、新築または改築された劇場で行われる初めての興行のことなので、①が適切です。②は、「起工式」などの表現が用いられます。③は、一般に「開店祝い」などと言います。 |
【遺失】
[ ① 過失 ② 紛失 ③ 損失 ]
| 答 | 解説 |
|---|---|
| ② | 「遺失」は、金品を落としたり置き忘れたりしてなくすことで、似た意味を表すのは、物をどこかでなくすことをいう、②「紛失」です。①「過失」は、失敗や間違いのことです。③「損失」は、得られるはずの利益を失うことで、実際に物をなくすときに使う言葉ではありません。 |
コーチは、学年に関係なく実力本位で選手を起用すると協調した。
[ ① 本位 ② 起用 ③ 協調 ]
| 答 | 解説 |
|---|---|
| ③ | ③「協調」が誤りです。物事の一部分を目立たせたり、ある事柄を強く主張したりすることをいう、「強調」が正しい書き表し方で、「協調」は、立場の異なる者が、互いに譲り合って協力することです。 |
けがをして一人で歩けなかったとき、家族の介( )がとてもうれしかった。
[ ① 包 ② 抱 ③ 泡 ]
| 答 | 解説 |
|---|---|
| ② | 音が「ホウ」である漢字の使い分けです。②「抱」を入れて、病人やけが人の世話をすることをいう「介抱」になります。①「包」は、つつむという意味をもつ漢字で、「包装」「包囲」などの熟語があります。③「泡」は、あわという意味をもつ漢字で、「水泡」「発泡」などの熟語があります。 |
【地方】
[ ① 中心 ② 中間 ③ 中央 ]
| 答 | 解説 |
|---|---|
| ③ | 「地方」は、首都や各地の大都市以外の地域のことです。首都や、国の政治や経済の中心となっているところを表す、③「中央」が反対の意味の言葉です。①「中心」は、広い意味で「真ん中」を指しますが、それだけでは首都や、政治の中心の意味にはなりません。②「中間」は、距離・時間・程度などについて、二つのものの間という意味です。 |
【まな板――包丁】
[ ① みかん――果物 ② にんじん――かぼちゃ ③ ねぎ――畑 ]
| 答 | 解説 |
|---|---|
| ② | 「まな板」と「包丁」は、どちらも調理器具の一種ですから、ものの名前と、それと同じグループにふくまれるものを表す言葉という関係です。同じ関係になるのは、どちらも野菜の一種である、②「にんじん―かぼちゃ」です。①は、「みかん」が「果物」の一種であるという関係、③は、「ねぎ」が「畑」で作られるという関係です。 |
1③、2①、3③、4①、5①、6②、7③、8②、9③、10②