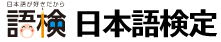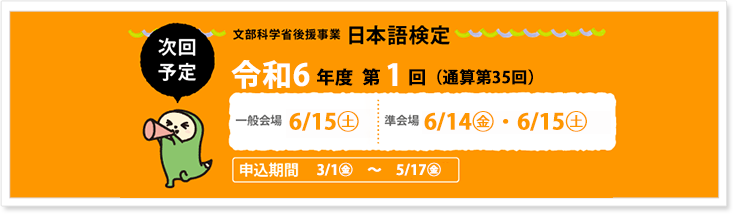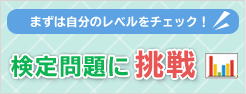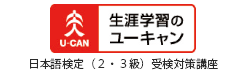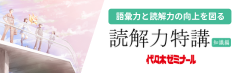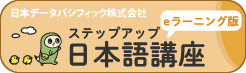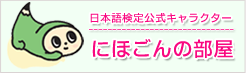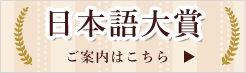このたびは、このような素晴らしい賞をいただき、感激しています。ありがとうございます。
改めて自分の文章を読み返してみました。そして、しばらく涙にくれました。 幼かった私、何といじらしく健気で意固地だったことでしょう。何でも自分でしなくちゃと思って、やっているつもりになっていましたが、実際はいつも祖父に守られていたのです。
今思い出します。
遠足や運動会の時には祖父が大きな固いおにぎりを作ってくれたこと。春、祖父が裏山に入り筍や竹帚の材料を採るそばで、キイチゴを食べたこと。夏、祖父に見守られながら家の前の祖父谷川で遊んだこと、井戸で冷やしたスイカを一緒に食べたこと。秋、祖父がきのこを採るそばで、山ブドウやあけびを食べたこと。冬、祖父が作ってくれた竹スキーで坂道をすべったこと。そして毎朝、月山を眺めたこと、月山の頂上から昇る満月の大き <美しかったこと。広瀬での2年半、つらいこともあったけど、楽しいこともたくさんあったのです。
成長する私に戸惑いながらも、貧しいながらも私を一生懸命愛し育ててくれた祖父に、中学生になって東京に出た私は一度も手紙を書くことも電話をすることもありませんでした。
大人になって会った時も、何となくわだかまりがあって、感謝の言葉も優しい言葉も掛けることができませんでした。そして、祖父は亡くなった。
祖父亡き後、母から聞きました。私の娘を広瀬に連れて行った時、母が「この子、なんて可愛いいんでしょ」と言ったら、祖父が「惠子の方がずっと可愛かったわ」と言ったそう。
今、祖父に言いたいです。
「おじいちゃん、私を育ててくれてありがとう。直接言えなくてごめんね。でもおじい ちゃんだって、惠子は可愛いって直接言ってくれてたら嬉しかったよ」
二人とも無口で不器用だったね。
私は最近、若い頃よく読んでいた太宰治を再読しています。そして、「津軽」の中に、故郷に贈る言葉を求められた太宰が「汝を愛し、汝を憎む」と記しているのを見つけました。おこがましいのですが、故郷に対する思いは私と太宰は同じだな、と思いました。
いろいろありましたが、今は故郷、広瀬が大好きです。安来駅からバスに乗ってしばらくして月山が見えてくると、涙が出てきそうになります。愛おしくて。だから「汝を増み ・汝を愛す」です。
最後に、このエッセイは広瀬で一人暮らしをしている母には見せられないな、と思います。泣いてしまいそうだから。
母とはこれから、たくさん話し、たくさん同じ時を過ごしていこうと思います。祖父と父にできなかった分まで。
受賞作品を読む(PDF)