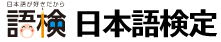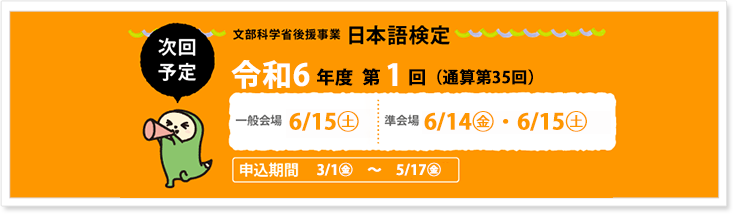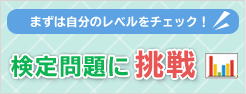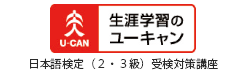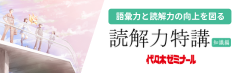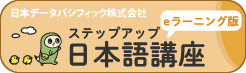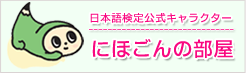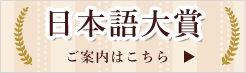令和7年(2025年)春号 ごけんメッセージ
今、なぜ日本語検定か?
前編
―語彙力を身につけるために―
佐々木 文彦
今年度(2025年度)、日本語検定委員会は、日本語検定の各級で扱う言葉のリストを公開いたします。(公開時期未定)
今号では、日本語検定委員会審議委員長である佐々木文彦先生に、公開の経緯とねらいについてご寄稿いただきました。日本語検定がどのように変わり、何が期待できるのか、ぜひお確かめください。

語彙学習の重要性
日本語検定では「敬語」「文法」「語彙」「言葉の意味」「表記」「漢字」の六つの領域で日本語運用能力を測定しますが、今回は語彙学習について考えましょう。
日本語検定の「語彙」「言葉の意味」という二つの領域で問われるのは「慣用句を含めて言葉の意味・用法を正しく理解し、適切に使うことができる力」で、次のような問題が出題されます。下線をひいたものが正解です。
〇波線部の言葉について、( )に入る対照的な意味を表す語を選びなさい(HP掲載2級)
職場ではいつも寡黙な彼が、飲み会となると途端に( )になるから不思議だ。
①喧伝 ②世辞 ③饒舌 ④雄弁
◯【はびこる】の適切な用法を次の中から選びなさい(HP掲載3級)
- ①
- 昨日見た映画は、犯罪がはびこる禁酒法時代のシカゴが舞台になっていた。
- ②
- どこにでもあるパン屋だったが、テレビで取り上げられてから、この一か月大変はびこっているようだ。
- ③
- 若い女性の間では、手作りのお菓子を交換することがはびこっているらしい。
「寡黙」「饒舌」や「はびこる」の意味・用法を正しく理解しているかどうかが問われる問題です。「饒舌」は「おしゃべり」とほぼ同じ意味ですが「寡黙な彼が饒舌になった」とすることで表現を引き締めることが出来ます。「はびこる」の選択肢②は「繁盛する」、③は「はやる」などと置き換えるのが適切です。いずれも「数多く行われる、広まる」という意味なのですが、①の文では「はびこる」を用いることで「悪いものがやたらに増えている」という印象を明確に伝えることが出来ます。
このように日本語には類義語がたくさんあるため、わたしたちは自分の言いたいことを伝えようとする際に常に語彙の選択に迫られることになります。豊富な語彙の中から適切に言葉を選ぶことによって伝えたいことを的確に表現できればよいのですが、一歩間違えると誤解を招いて相手に不快な思いを与える可能性もあります。仕事上のトラブルに発展したり、プライベートな場面で人間関係をこじらせたりしかねません。語彙選択はわたしたちの人生を左右する問題だと言っても過言ではありません。
語彙学習の難しさ
それではわたしたちはいったい何語の語彙を身につけたらよいのでしょうか。これはなかなか難しい問題です。
日本語検定委員会では2008年に『日本語検定必勝単語帳』(入門編・発展編、東京書籍刊)を出して語彙学習のための教材を提供していますが、日本語検定の各級の出題とは必ずしも結びついておらず、「単語帳で勉強したけど検定には出なかった」などという声も聞かれ、検定対策に直結する語彙リストの作成を待ち望む声が日本語検定の指導者の先生方からも聞かれるようになりました。
そもそも「語彙力」は問題集で学ぶものではなく、たくさんの言語体験の中で培われるものであり、「語彙力を身につけるためには本をたくさん読む」というのが語彙学習の王道です。問題集で知識を身につけたとしても、読んだことも使ったこともないのでは本当にその言葉を習得したとは言えないからです。しかしながら「たくさん本を読みなさい」という指導にも限界があります。
読書量の減少「国語に関する世論調査」
次のグラフは2024年9月に公表された「令和5年度 国語に関する世論調査」の結果の一部です。今回の調査から対面調査ではなく書類による調査に変更になったため過去の調査結果との「比較には注意が必要」とのただし書きはあるのですが、本を「読まない」と答えた人が大きく増えて6割を超えているという事実は重く受け止めるべきです。言語体験は読書だけではありませんが、公の場面で用いられる語彙や日本語の遺産でもある文学作品で用いられる語彙に触れる機会は今後ますます減っていくでしょう。

語彙リストの公開と語彙学習テキストの刊行
そこで日本語検定委員会は、適切な語彙リストを作成してそれを習得するためのテキストを提供すれば、語彙学習の目標が立てやすくなり、読書量の減少による語彙力低下を食い止めることができるのではないかと考えました。
日本語検定には18年間でのべ120万人を超える受検者の成績が蓄積されており、その膨大なデータを活用することによって1級から7級までレベルに応じてどの語彙を出題するのが適切か、目安を定めることができました。このたび「語彙・言葉の意味・漢字」の三つの領域の学習目標として『日本語検定必修単語集』(級別)を刊行いたします。また、2025年度中に「日本語検定語彙リスト(仮称)」をホームページ上で公開し、原則としてこのリストから出題することにいたしました。これによって、受検者の皆さんが学習に取り組み、先生方が語彙学習指導を進める上での到達目標を明確にすることができると考えます。
決して読書体験等を通じて語彙力を身につけることをあきらめるのではありません。日本語検定に取り組んで語彙力を身につけることによって、読書がもっと楽しくなり、読書量が増えることも期待できると考えております。
おわりに-今、なぜ日本語検定か?
日本語はどんどん変化し「教科書で習った日本語」と「みんなが使っている日本語」はますますかけ離れていきます。そんな中で「公的な場できちんとした日本語を使える」力を身につける学習はどうしても必要です。世の中の変化につれて「正しい日本語」の姿も変化しますので、日本語検定は「現時点での正しい日本語」についての情報を「解答解説」やホームページを通じて発信する努力を続けてまいります。
そしてこの度公開する「日本語検定語彙リスト」は、日本語話者が身につけるべき語彙力のスタンダードを提案するものとして画期的なものであると自負いたします。
日本語検定の2級では、社会生活におけるさまざまな場面で求められる日本語力が問われます。7級から2級まで年齢や段階に応じて日本語力を向上させ、社会人として必要な日本語運用能力をしっかりと身につけるための目安として日本語検定をぜひご活用ください。そして、さらに1級にチャレンジして「日本語の達人」を目指してください。
『日本語検定必修単語集2級』
『日本語検定必修単語集3級』
本体価格1400円
東京書籍 / 2025年3月19日発行

佐々木 文彦(ささき ふみひこ)
明海大学外国語学部日本語学科教授。1958年秋田県秋田市生まれ。秋田県立秋田高等学校卒業、東京大学文学部卒業。同大学院博士課程満期退学。専門分野は日本語学。語彙論、語の意味・用法の変化を中心に研究。2018年3月より、日本語検定委員会審議委員。2020年10月より、日本語検定委員会審議委員長。著書に『暮らしの言葉擬音・擬態語辞典』、『暮らしの言葉新語源辞典』(以上、講談社)、『日本語再入門知識編』(日栄社)など。『広辞苑第七版』(岩波書店)の項目選定と執筆(国語項目)に携わる。