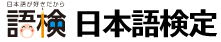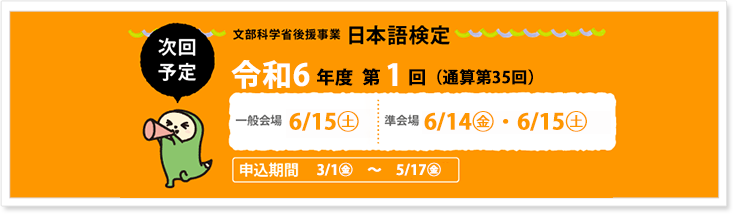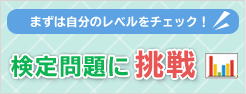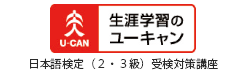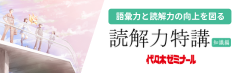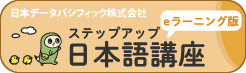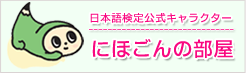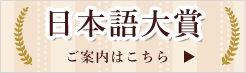連体詞は、「ある日」の「ある」のように、名詞を修飾することのみを役割とする品詞です。「ある」がもともとは、動詞「あり」の連体形に由来するように、ほかの品詞から派生して成立したものが多いというのが特徴です。ここでは、連体詞の表記についての特徴を探ります。
「送り仮名の付け方」(1973)
送りがなの決まりを示した「送り仮名の付け方」には、本則(基本的な法則)として「副詞・連体詞・接続詞は、最後の音節を送る」とあり、「来る」(きたる)と「去る」が語例としてあがります。この本則が連体詞を漢字で書く場合の一般的な基準です。本則に従えば、「あくる朝」の「あくる」は、「明る」となるはずですが、「明」には、動詞として「明ける」と書く事例があり、「く」「け」の部分を漢字の外に出さないと、読み分けがしにくくなるという理由から「例外」として「明くる」(動詞は「明ける」)と書く決まりになっています。
公用文
2021年3月12日文化審議会国語分科会報告の「新しい「公用文作成の要領」に向けて」(以下「公用文」)では、連体詞は「仮名書きを基本とするが一部のものは漢字で書く」グループに含まれ、かな書きの語としては、「あらゆる」「ある」「いかなる」「いわゆる」「この」「その」「どの」があがり、漢字表記の語としては「来る」「去る」「当の」「我が」があがります。「我が」の後ろに「等」とあるため、ほかにも漢字表記する連体詞が存在することがうかがえます。
新聞
共同通信の『記者ハンドブック 第14版』(2022)の「用字について」には、連体詞の「ある」「あらゆる」「いわゆる」「この」「その」「そんな」「ほんの」「わが」がひらがなで書くものとして掲げられています。「公用文」で漢字表記の例として示すもののうち、「来たる」が「用字用語集」のページに載ります(「来る」ではなく「来たる」であることについては後述)。「去る」は、項目がありません。こちらは、「去る4日」のように表現するのではなく、「(何年)5月4日」のように日付を明示する書き方をするのが新聞の基本であり、連体詞の「去る」は、使う必要性が高くないと判断されている可能性があります。
『読売新聞用字用語の手引 第7版』(2024)は、「文字遣いの基準」のページで、「平仮名で書く例」と「漢字で書いてもよい例」を区別して示します。前者には「あの」「あらゆる」「ある」「いわゆる」「かの」「この」「こんな」「さる」「その」「どの」があがり、後者には「明くる」「大きな」「単なる」「主な」「来たる」「大の」「小さな」「当の」「我が」があがります。「彼の」は表外音訓を用いた書き方であるため、「あの」となり、「所謂」は、表外字と表外音訓を用いた書き方であるため、「いわゆる」となります。
放送
放送については、NHKの『NHK漢字表記辞典』(2011、以下『NHK漢字』)を参考にします。連体詞について表記の原則を記すページがないため、上述の語について、五十音順に列挙することにします。
明くる、あの、あらゆる、ある、いかなる、いわゆる、大きな、主な、かの、①きたる②来る、この、こんな、去る、その、単なる、小さな、当の(「当」の項目の用例に「当の本人」が示される)、どの、①わが②我が
「大の」「ほんの」は、項目がありません。『NHK日本語発音アクセント新辞典』(以下『NHKアクセント』)には「大の」「ほんの」であがっています。NHKの表記に言及する際は、『NHK漢字』を優先し、そこにない語の場合は『NHKアクセント』の扱いを記します。
教科書
教科書については、東京書籍の『教科書 表記の基準2021年版』を参照します。放送のところに示した語のうち、東京書籍の辞書の「用例集」に項目があるもののみについて列挙します。
明くる、ある、いわゆる、大きな、主な、かの、来る、この、去る、小さな、当の、我が
どうして、「常用漢字表」の範囲で漢字表記が可能であっても、「さる」と「去る」、「わが」と「我が」というように、業界ごとに標準表記が異なるということが生じるのでしょうか。また、単に語を列挙するのではなく、原則として指摘できるようなことはないのでしょうか。次にこれらのことを検討します。
検討する連体詞の範囲
以下では『NHKアクセント』から抜き出した63の連体詞を用いて、表記の原則と例外(ゆれの生じる部分)について考えます。上述の連体詞は、63語中にすべて含まれます。
原則1:表外字・表外音訓を使う語は、かな書きにする
この原則により、「あの」「あらゆる」「ある」「いかな」「いかなる」「いわゆる」「かかる」「この」「その」「たえなる」「ちょっとした」「どの」「にっくき」「ろくな」がかな書きする語として取り出せます。
原則2:一般的・慣用的な漢字表記がない語は、かな書きにする
たとえば「どういう人ですか」の「どういう」は、副詞の「どう」に動詞の「言う」がついたものだと考えれば、「どう言う」という表記も考えられますが、これを表記欄に掲げる辞書は一般的ではありません。「どう言う」では2文節に感じられます。1文節の連体詞として処理するには「どういう」のほうが視覚的にも好ましいということでしょう。同様の処理が可能なのは、「とんだ」「どんな」「ふとした」「むくつけき」です。過去に当て字としてこれらに漢字表記が行われたことがあったかもしれませんが、それは現代語の標準表記を考えるにあたっては、不要な情報です。
原則3:表内字・表内音訓で書ける漢語(の部分)は漢字表記にする
漢語(主に、中国語に由来する音読みのことば)は、漢字表記が原則です。ただし、漢語は、名詞として処理されるのが一般的であり、そのほかには、「健康な体」のように形容動詞として機能する場合と「勉強する」のように漢語サ変動詞の語幹として機能する場合があります。連体詞として分類される可能性があるのは、「翌15日」などという場合の「翌」です。「明くる」と同じ意味であり、口にするとき「翌」と「15日」のあいだにポーズ(発音の際の休止)が入りうることなどから連体詞として処理されます。他方、辞書によっては、「不健全」「初出勤」の「不」や「初」と同じく接頭辞として処理する立場もあります。ここではひとまず、連体詞として扱われる可能性がある漢語の例として取り上げ、「よく」ではなく「翌」と書くということが確認できれば十分です。
残りの語は、「当の」のように、前に漢語、後ろに和語が来て、全体としては混種語(和語と漢語、漢語と外来語など、複数の種類のものがくっついてできた単語)になるものばかりです。これに当てはまるのは、「異な」「確たる」「冠たる」「最たる」「主たる」「聖なる」「大した」「大それた」「大の」「単なる」「無理からぬ」「例の」です。
原則4:用言に由来する連体詞は、用言の表記に合わせる
「飽くなき」は、動詞「飽く」「飽きる」と関係があり、それらが漢字表記であることから、連体詞としても漢字表記が選びやすいタイプです。前述の「明くる」もこの原則で扱えます。
「大きな」「小さな」は、「大きい」「小さい」が漢字表記であるなら、同じく漢字表記という判断が行われます。「長の」「永の」(『NHKアクセント』では別立項されているため、ここでは別語として扱っておきます)は、形容詞「なが(い)」に助詞の「の」がついたものです。形容詞を「長い」「永い」と書くことの延長に「長の」「永の」も位置づけられます。
「憂きこと」「亡き人」の「憂き」「亡き」は、文語形容詞「憂し」「亡し」の連体形から来ています。現代語の形容詞「憂い」「亡い」をもとにして、これらも漢字表記と判断することが可能です。また、「常用漢字表」の「亡」「憂」の欄に「憂き目」「亡き人」という語例があることをもとにして漢字を選ぶこともできます。
形容動詞「大いなり」の連体形に由来する「大いなる」は、形態的には「大きい」「大きな」との関係が見いだしにくい語ですが、意味には関連があると考えて漢字表記という答えを導き出すことができそうです。「常用漢字表」の「大」の欄に「おおいに」という訓が載り、「大いに」という語例(表記例)があるのを参考にすることもできます。「主な」も、「常用漢字表」の「主」に訓の「おも」と「主な人々」という語例があるのを表記の判断基準にすることが可能です。
原則5:名詞を主成分とする連体詞は、名詞の表記に合わせる
たとえば「先の大会」などという場合の「先の」を名詞「先」に助詞の「の」がついた連体詞として認めるならば、名詞を「先」と書くのに合わせて連体詞も漢字表記と判断することができます。「あじな」は、文語の形容動詞「あじなり」の連体形「あじなる」に由来するとされますが、現代語に関連する形容動詞ないし形容詞がないこと、「常用漢字表」に「あじな」という語例が載っていないことなどから考えると、現代語の表記を考えるうえでは、名詞の「あじ」を「味」と書くのが標準表記であるのと同じく、連体詞の「味な」もそれに合わせて漢字表記というふうに捉えるほうが理解がしやすいと見ておきます。
複合語について
『NHKアクセント』には、複数の名詞や動詞が組み合わさってできた連体詞がいくつか載っています。それらの語の表記がどういう理由で選ばれているのかを考えます。
「見知らぬ」「見果てぬ」は、「見る」「知る」「果てる」が漢字を標準とするのに合わせた処理結果です。「人知れぬ」も同様です。
「ならない」と同じ意味の「ならぬ」が含まれた「道ならぬ」は、何かに「成る」わけではないと見て、かな書きです。「道行く」は、「道」と「行(く)」の漢字の意味が生きていると考えて漢字表記です。
「一とおりの」は、「ひととおり」がstreetの意味ではないので、「一通り」ではなく「一とおり」と書くことになっているのに合わせた処理です。「心ある」は、動詞の「ある」の優先的な表記がかな書きであるのに合わせています。
「なだたる」は、「名立たる」という表記も慣用としてありますが、共同通信も東京書籍も「名だたる」を標準表記に採用しています。「なたちあり→なだたり→なだたる」という変遷を経ているため、「たつ=立つ」という感覚が生じにくいのでしょう。
他方、「おもだった」については、『NHK漢字』は「おもだった」を採用し(「おもだつ」の用例に示されています)、共同通信は「主立った」を採用します。共同は、「主+立つ」と考えて漢字表記にしていますが、NHKは、「主」と「重」のうち、どちらが標準的な字であるとも判断しにくいため、全体をかな書きにしています。
まとめ
連体詞の表記について、原則的なことを述べました。表記のゆれが問題となるような事例については、次回に考えます。
![]()
中川秀太
文学博士、日本ウェルネススポーツ大学スポーツプロモーション学部 准教授、日本語検定 問題作成委員
専攻は日本語学。文学博士(早稲田大学)。2017年から日本語検定の問題作成委員を務める。
- 最近の研究
- 「現代語における動詞の移り変わりについて」(『青山語文』51、2021年)
- 「国語辞典の語の表記」(『辞書の成り立ち』2021年、朝倉書店)
- 「現代の類義語の中にある歴史」(『早稲田大学日本語学会設立60周年記念論文集 第1冊』2021年、ひつじ書房)
- 「現代日本語のジェネレーションギャップ」(2024年、武蔵野書院)など。
コラム一覧
- 2025.4 (39)「連体詞の表記①」
- 2025.3 (38)「語頭のラ行音」
- 2025.2 (37)「接続詞の表記」
- 2025.1 (36)「一語文の用法を持つヒト名詞」
- 2024.12 (35)「朝昼晩のあいさつのことば」
- 2024.11 (34)「接頭辞の『ま』『ど』『せい』」
- 2024.10 (33)「相撲の世界における動詞の特別な使い方」
- 2024.9 (32)「数字の語形と表記」
- 2024.8 (31)「ぼかす副助詞」
- 2024.7 (30)「『甲の乙』という形の単語について」
- 2024.6 (29)「母音が連続するときの発音」
- 2024.5 (28)「『現代仮名遣い』と表音一致」
- 2024.4 (27)「動詞のウ音便について」
- 2024.3 (26)「『かな(仮名)』の語形とアクセントと表記」
- 2024.2 (25)「『わかる』のコミュニケーション文法」
- 2024.1 (24)「『よりか』とは何か」
- 2023.12 (23)「『お』と体の部分」
- 2023.11 (22)「質問という行為について」
- 2023.10 (21)「しこ名の『~川』」
- 2023.9 (20)「『~ていただきたいです』という表現について」
- 2023.8 (19)「今に生きる旧国名の別称」
- 2023.7 (18)「『可決・成立する』は是か非か」
- 2023.6 (17)「語頭に[p]の音を持つ単語のこと」
- 2023.5 (16)「『いる』と『おる』の活用形」
- 2023.4 (15)「『ローマ字のつづり方』は実用的か否か」
- 2023.3 (14)「御しがたいひと言『なるほど』のこと」
- 2023.2 (13)「『~犬』はイヌかケンか」
- 2023.1 (12)「『ありか』『かくれが』『すみか』の表記」
- 2022.12 (11)「みずうみ・ぬま・いけ」
- 2022.11 (10)「『お間違いありませんか(お間違いないですか)』に問題はありませんか」
- 2022.10 (09)「現代の1拍語」
- 2022.9 (08)「動植物名を表す漢字について」
- 2022.8 (07)「現代語における女の人の一人称」
- 2022.7 (06)「『水鳥』の語形とアクセント」
- 2022.6 (05)「動物と敬称②」
- 2022.5 (04)「動物と敬称①」
- 2022.4 (03)「『東方・西方』の語形」
- 2022.3 (02)「『母方・父方』の語形」
- 2022.2 (01)「『失礼します』か『失礼しました』か」