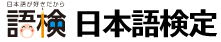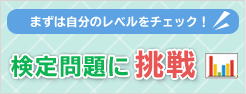「うるかす」は「潤かす」と書くという。
初めてこの言葉を聞いたのは大学三年の頃、昭和五十年代も半ばのこと。中学・高校と東京都心の学校に通った私は、通学電車の混雑に嫌気がさし、大学は東京を離れると心に決めた。その年の同学の卒業生の中で、東京を離れたのは、私一人。
目指したのは関東平野の北、筑波山の麓。新設の大学で、大学の建物以外に周囲に見えるのは赤松林だけ、四月でも冬枯れの野が広がる、荒涼とした景色に惹かれた。
大学の一年生と二年生は、必ず学生宿舎に入居を許可されるという環境も、世間知らずで不動産屋めぐりなど、とても怖くて覚束ない新入生にとっては、有難かった。
ところで、当然のことながら、三年生になれば、大方の学生が学生宿舎を出され、近隣のアパートで自炊生活を始めることとなる。そうした生活が始まると、すでに世慣れた学生たちは、宿舎生活以上に互いの部屋を訪ねあい、ときには食事をふるまって、語り合い、そのまま友人のこたつに泊り込んだ。
そのような日々に、私がよく訪れ、一宿一飯の世話になったのが、岩手は盛岡近郊出身の友人が借りた部屋だった。
彼女は大学のあった開発地区の幹線道路から一筋離れた、旧村部と呼ばれる地区の農道脇に立つ、とある長屋の一室を借りていた。首都圏から引っ越してきた老夫婦が自宅の庭に経営する、「八千草荘」という風雅な名前の、風呂トイレ共用、女子学生四部屋だけの長屋だった。夜ともなれば周囲はしじまに包まれる、さらに田舎びたその風情に惹かれて、私は足繁く、そこに通った。
その友人が、帰ってくれと言わんばかりの無愛想な様子で飯を炊いてくれるとき、よく「米をうるかす」という耳慣れない言葉を口にした。語感と、彼女の動作から、「米を水に浸す」ことだとわかったが、これにぴんとくる東京言葉がない。「浸す」では、いかにも汎用性がありすぎる。
私はその後、自分の語彙に、この「潤かす」を加えた。この言葉、北海道・東北では、米だけでなく豆やら乾物やら洗う前の食器にも使うという。ときに、「その言葉はどちらで」と反応する人に出会うこともある。
後年生まれた息子の名前が、「潤」となったのは、夫がこの漢字を使いたいと言ったからだが、私も、男の子の名前に水の意が入ることを良しとして、賛成した。
片意地で頑固な人の心を「潤かし」て、さらさらと溶かす人になってほしいとこじつけたのは、さらに後年のことだが。
阿部 由美子(あべ ゆみこ)
東海大学湘南校舎国際教育センター非常勤講師(日本語教育)
記事一覧
- 2017.11 (31) 「羊羹」
- 2015.10 (30) 「世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない」
- 2015.01 (29) 「猫」
- 2014.07 (28) 「おでん」
- 2014.04 (27) 「すし」
- 2014.01 (26) 「のんのんのんのん」
- 2013.10 (25) 「じぇじぇじぇ」
- 2013.08 (24) 「一日作さざれば一日食らわず」
- 2013.07 (23) 「宮城県の方言」
- 2013.06 (22) 「天ぷら」
- 2013.06 (21) 「何か食ひたい」
- 2013.04 (20) 「乾燥しなさい?!」
- 2013.04 (19) 「花冷え」
- 2013.03 (18) 「浦じまい」
- 2013.03 (17) 「葡萄の種をのどに詰まらせて」
- 2013.02 (16) )「てふてふが一匹韃靼海峡を渡って行った」
- 2013.02 (15) 「戦時中」
- 2013.01 (14) 「21世紀を生きるのだから」
- 2012.12 (13) 「うらやんではいけない」
- 2012.12 (12) 「国語は英語でJapanese」
- 2012.11 (11) 「顔が重い」
- 2012.11 (10) 「お雪さま」
- 2012.10 (09) 「ヨダレザクラ」
- 2012.10 (08) 「岸離れ」
- 2012.09 (07) 「米穀通帳をなくしたように寂しい」
- 2012.09 (06) 「衝き居(つきう)」
- 2012.08 (05) 「お暑うございます」
- 2012.08 (04) 「お嫁に行っても困らない」
- 2012.07 (03) 「かしらん」
- 2012.07 (02) 「うるかす」
- 2012.06 (01) 「ずくなし」