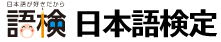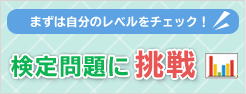このごろは旬の果物を買っても、種なし品種が増えてしまい、包丁で切ったときに種に邪魔される感触がなくて、なんとはなしに物足りなさを感じることがある。
葡萄もそのひとつで、そのまま呑み込める種なし葡萄がふえた。しかし、種があったところで、葡萄の種がいかばかり大きいというのか。いくら赤ん坊のか細いのどでも、のどを詰まらせるほど、葡萄の種がかつて大きかったというのか。
最初の子どもが生まれて、夫の母はいろいろと助言してくれた。子どもを寝かしつけるときの子守唄も義母の口移しだし、「抱っこされながら肩に眼をこすりつけているときは眠いのよ」と教えてくれたのも義母。「赤ん坊ってなぜか夕方になると泣くけど、寂しいのかね」と、泣かせたって、母親のせいじゃないよと慰めてもくれた。
しかし、女に教育は要らないという父親に、小学校四年までしか通学を許されず、高等小学校へ進みたいと願うその目の前で願書を破り捨てられたと語る義母は、そのせいか、人一倍賢い人なのに、どうにも迷信、占い、祈祷の類に弱く、儀式として以上にそれらを鵜呑みにするところがあった。
若かった夫は口を酸っぱくして、その愚をたしなめたが、義母も頑として譲らない。子どもが何でも口にするようになったころ、義母は真顔で「葡萄の種をのどに詰まらせて死んだ子どももいるのだから」と、私に注意せよと説いた。理性で考えて、いくらなんでも「葡萄の種」ぐらいで、と思ったが、何度も同じ話を繰り返されると、ただただ疎ましい。その疎ましさも、今振り返れば、「葡萄」に引っかかって、言葉を文字通りにしか受け取れない、若気の至りと思い至るが。
大地震が発生して、福島の原子力発電所の事故が勃発して間もない頃、ある若い母親の嘆きを耳にした。北の地方に住むその人の夫の母が、「事故後、近海で取れた魚を口にしていた母親が、油にまみれた子どもを産んだ」から、決してその辺りで獲れた魚を口にするなと言ってよこしたのだという。若い母親にとっては、聞くに堪えない非科学的な話に違いない。
しかし、年が寄ると、同じ話も違って聞こえる。「葡萄の種をのどに詰まらせて」も、今なら素直に、子どもの口に入りそうなどんな小さなものにも目を光らせよ、と翻案して聞こえるし、「油まみれ」の話も、事故のあった地元の人には心寒い話だろうが、自然を畏れて怯える人間の声と聞くこともできる。
遠い先祖の昔から、こうして誇張と寓意に満ちた言葉が紡がれ、言い伝えとして語られたのだろう。かつては蒙昧と思えた義母の言葉から、その疎ましさはきれいに消えて、今では言葉の寓意だけが耳に残っている。
いつか次の世代が生まれたら、「昔、お義母さんはこんなことを言って」と、私は同じ言葉を繰り返して疎まれるだろう。だが、葡萄の種がいかに小さかろうと、なくなろうと、その寓意のおもしろさは、どこかにそっと残しておきたい。
阿部 由美子(あべ ゆみこ)
東海大学湘南校舎国際教育センター非常勤講師(日本語教育)
記事一覧
- 2017.11 (31) 「羊羹」
- 2015.10 (30) 「世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない」
- 2015.01 (29) 「猫」
- 2014.07 (28) 「おでん」
- 2014.04 (27) 「すし」
- 2014.01 (26) 「のんのんのんのん」
- 2013.10 (25) 「じぇじぇじぇ」
- 2013.08 (24) 「一日作さざれば一日食らわず」
- 2013.07 (23) 「宮城県の方言」
- 2013.06 (22) 「天ぷら」
- 2013.06 (21) 「何か食ひたい」
- 2013.04 (20) 「乾燥しなさい?!」
- 2013.04 (19) 「花冷え」
- 2013.03 (18) 「浦じまい」
- 2013.03 (17) 「葡萄の種をのどに詰まらせて」
- 2013.02 (16) )「てふてふが一匹韃靼海峡を渡って行った」
- 2013.02 (15) 「戦時中」
- 2013.01 (14) 「21世紀を生きるのだから」
- 2012.12 (13) 「うらやんではいけない」
- 2012.12 (12) 「国語は英語でJapanese」
- 2012.11 (11) 「顔が重い」
- 2012.11 (10) 「お雪さま」
- 2012.10 (09) 「ヨダレザクラ」
- 2012.10 (08) 「岸離れ」
- 2012.09 (07) 「米穀通帳をなくしたように寂しい」
- 2012.09 (06) 「衝き居(つきう)」
- 2012.08 (05) 「お暑うございます」
- 2012.08 (04) 「お嫁に行っても困らない」
- 2012.07 (03) 「かしらん」
- 2012.07 (02) 「うるかす」
- 2012.06 (01) 「ずくなし」