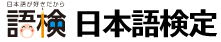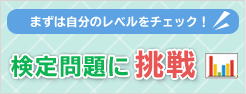赤塚不二夫の漫画には、強烈な個性の持ち主が登場する。印象的なのは、主人公よりむしろ脇役達である。
たとえば、『もーれつア太郎』のしゃべる猫ニャロメ。『天才バカボン』に現れる元祖スーパーハイブリッドのウナギイヌ。これは名前のとおり、鰻と犬のミックス動物である。
おそ松を筆頭に一松、カラ松、チョロ松、トド松、十四松の六つ子の兄弟が騒動をひきおこす『おそ松くん』(昭和37年~44年連載)も懐かしい作品である。テレビでも放映されるようになり、六つ子の父親の旧友井矢見(後、イヤミ)の驚くさま「シェー」が流行った。
とくに気になった脇キャラはチビ太である。チビ太は六つ子をいじめる近所の子供だ。がんもどき、ちくわぶ、こんにゃくなのだろうか、しょっちゅう○、□、△型の串にさしたおでんを持っていて、筆者には、それが不思議な食べものに見えた。仙台市では、おでんを串に刺して売る屋台を見かけなかったからである。漫画では、町のやくざ「ひょっとこ組」のガンモも串に刺したおでんを持っていたので、チビ太はガンモの屋台から買っていたのかもしれない。
ところで「おでん」には、風雅な語源がある。料理名になったのは、室町時代以降のことで、味噌を塗って炙った豆腐田楽が最初のものらしい。
安楽庵策伝『醒睡笑』(1628年)では、「田楽」について、白袴をはき、色つきのうちかけを着けた田楽法師が鷺足(「高足」とも言う長い一本の棒)に乗って踊る様子に似ていることからその料理名になったのだろうかと推察している。「田楽」とは、平安時代から、田植えの時に田んぼの神様を祀り、畦道で太鼓の伴奏とともに歌ったり踊ったりする「田舞」から発展して曲芸のようになったものを指す。
「おでん」という名称は、その「田楽」の「楽」がとれて「お」がついたものという。もともとは、宮中や幕府に仕える女房達の間で使われていた言葉――女房詞だった。
江戸時代では、田楽とおでんの双方の名称が使われていたようである。『豆腐百珍』(1782年)では、木の芽や海胆等を使ったさまざまな田楽のレシピが掲載されている。「煮込みのおでん」は、近世後期には既に誕生していたようである。近代以降、二葉亭四迷の書いた『浮雲』(明治20年)では、「煮込みのおでん」が庶民の食べものという意味で母娘の会話の中で引用されている。
語源を顧みれば、チビ太のもっていた串に刺したおでんの方が、皿に盛ったおでんより正統おでんだったということになるだろうか。
戦前の織田作之助作『夫婦善哉』(昭和15年)では、鍋で煮込んだおでん「関東煮(かんとだき)」がとりあげられている。元芸者の蝶子は働き者だが、柳吉は仕事の続かないぐーたら男である。
二人で法善寺境内の「正弁丹吾亭」や道頓堀の「たこ梅」をはじめ、関東煮屋の暖簾をくぐって、味加減などを調べあげ、「蝶柳」という関東煮の店を開いた。店は繁盛する。ところがそれもつかの間、柳吉は店の金を持ち出して遊んでしまう。二人は喧嘩をしながらも、結局別れることなく、寄り添い続けていく。
作品では、二人ですする「夫婦善哉」に夫婦の機微が表象されているのだが、「関東煮」も効果的にとりあげられているように思われる。鯨のさえずりやコロ、牛すじ、蛸の入った関東煮は、関東のおでんに比べると、薄口醤油で味をつけたやや甘口のものだ。田楽に比べれば一つの鍋で煮込む簡単な料理だが、たくさんの具の入った関東煮の鍋は、ちょっとしたカオスの世界でもある。夫婦という一つの鍋に、それぞれの悲喜交々の十年間程の日々が煮込まれているかのようである。
「おでん」をとおして、言葉の背景にある歴史とともに様々な物語が見えてくる。
大本 泉
仙台市出身。仙台白百合女子大学教授。日本ペンクラブ女性作家委員。専門は日本の近現代文学。
著書に『名作の食卓』(角川書店)、共編著に『日本語表現 演習と発展』『同【改訂版】』(明治書院)、共著に『永井荷風 仮面と実像』(ぎょうせい)等がある。
記事一覧
- 2017.11 (31) 「羊羹」
- 2015.10 (30) 「世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない」
- 2015.01 (29) 「猫」
- 2014.07 (28) 「おでん」
- 2014.04 (27) 「すし」
- 2014.01 (26) 「のんのんのんのん」
- 2013.10 (25) 「じぇじぇじぇ」
- 2013.08 (24) 「一日作さざれば一日食らわず」
- 2013.07 (23) 「宮城県の方言」
- 2013.06 (22) 「天ぷら」
- 2013.06 (21) 「何か食ひたい」
- 2013.04 (20) 「乾燥しなさい?!」
- 2013.04 (19) 「花冷え」
- 2013.03 (18) 「浦じまい」
- 2013.03 (17) 「葡萄の種をのどに詰まらせて」
- 2013.02 (16) )「てふてふが一匹韃靼海峡を渡って行った」
- 2013.02 (15) 「戦時中」
- 2013.01 (14) 「21世紀を生きるのだから」
- 2012.12 (13) 「うらやんではいけない」
- 2012.12 (12) 「国語は英語でJapanese」
- 2012.11 (11) 「顔が重い」
- 2012.11 (10) 「お雪さま」
- 2012.10 (09) 「ヨダレザクラ」
- 2012.10 (08) 「岸離れ」
- 2012.09 (07) 「米穀通帳をなくしたように寂しい」
- 2012.09 (06) 「衝き居(つきう)」
- 2012.08 (05) 「お暑うございます」
- 2012.08 (04) 「お嫁に行っても困らない」
- 2012.07 (03) 「かしらん」
- 2012.07 (02) 「うるかす」
- 2012.06 (01) 「ずくなし」