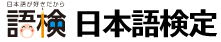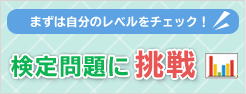子どもの頃は身体が弱かったために、外でほとんど遊んだことがなかった。遊び相手は、もっぱら家の中での飼い猫である。そのためだろうか、今でも外で猫を見かけると、思わず声をかけてしまう。研究室では猫の置物が並び、猫の写真が壁一面に貼られている。部屋を訪れる猫嫌いの人にとっては、一種のハラスメントになるだろう。
猫の原種は、リビアヤマネコといわれている。博物館で剥製を見たことがあるが、中型犬位の大きさである。それが家畜化され、現在の猫になった。
日本では、奈良時代に中国から渡来したというのが定説のようである。留学僧が船で帰朝したおり、仏教の経典を鼠から守るために、猫を連れてきたという。古代エジプトでは猫をミイラにしたし、イスラム教では猫を大切にしているため、たとえばイスタンブールのモスク近辺では、たくさんの猫が幸せそうに暮らしている。猫は、宗教と密接な生きものなのだ。
『枕草子』(10世紀末)では「うへにさぶらふ御ねこ」といったセレブ猫が登場するが、庶民の生活に欠かせないのも猫である。『宇治拾遺物語』(13世紀)では、「子子子子子子子子子子子子」という文字遊びが見受けられる。かつて「ネ」を「子」と表記したので、「猫の子の子猫獅子の子の子獅子(ねこのこのこねこししのこのこじし)」と戯れて読む。たしかに、三味線の胴張にされたり、昔、医学の実験台になったり、人間の犠牲になることもあった。が、「猫に小判」「猫に鰹節」等といった猫にまつわる慣用句が多いのも、日本人が猫と共生してきた証拠である。
「ねこ」という名称についてだが、猫のある情報誌を読んでいたところ、鼠をとるのを「ネコ」、鳥をとるのを「トコ」、蛇をとるの「へコ」と呼ぶと書いてあった。だが、はたしてそうなのだろうか。外猫のパイド嬢は、捕まえた「蜥蜴」や「鯉」を時々玄関先まで届けにくるが、そのたびに「トコ」「ココ」と異なった生きものになるのはおかしいからである。やはり有力な説は、猫の鳴き声「ネー」に、親愛の情をこめて「コ」をつけて「ネコ」になったというものだろう。「猫」の音読み「ビョウ」も、中国語の発音「マオ」も猫の鳴き声から生まれたと思われる。
昨年、米国の有線テレビ局CNNが、「世界六大猫スポット」を発表した。米国フロリダにあるヘミングウェイ博物館、イタリアにある古代遺跡のラルゴ・アルジェンティーナ広場、トルコの地中海沿岸の街カルカン、アジアでは、台湾新北市にある侯硐(ホウトン)、そして日本の福岡県藍島、宮城県石巻市田代島である。
田代島は近いので、年に一度は訪れる。島に住む人より猫の数の方が多い。ひょっこりひょうたん島のモデルになった島だ。侯硐は、台北から電車で4,50分の距離にある。炭鉱が閉山した後、一種の村おこしで猫を保護し、観光地として成功した。町の随所にカーテンつきの猫個室がある。首輪をつけた、こぎれいな猫が多い。
はじめて行ったときに、雨音にも怖がる「びびり猫」(臆病な猫)ミャー嬢にぴったりなステッカーを旅のみやげとして買ってきた。玄関に貼ったステッカーを見るたびに、楽しい気分になる。
「小心猫出没」
小心者の猫(小心猫)が出没するという意味と解釈して買ってきた。しかし、台湾の意味では、「注意! 猫が出たり入ったりします」である。
意味の多少のずれはあっても、愛猫家は、世界でつながっているのである。
大本 泉
仙台市出身。仙台白百合女子大学教授。日本ペンクラブ女性作家委員。専門は日本の近現代文学。
著書に『名作の食卓』(角川書店)、共編著に『日本語表現 演習と発展』『同【改訂版】』(明治書院)、共著に『永井荷風 仮面と実像』(ぎょうせい)等がある。
記事一覧
- 2017.11 (31) 「羊羹」
- 2015.10 (30) 「世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない」
- 2015.01 (29) 「猫」
- 2014.07 (28) 「おでん」
- 2014.04 (27) 「すし」
- 2014.01 (26) 「のんのんのんのん」
- 2013.10 (25) 「じぇじぇじぇ」
- 2013.08 (24) 「一日作さざれば一日食らわず」
- 2013.07 (23) 「宮城県の方言」
- 2013.06 (22) 「天ぷら」
- 2013.06 (21) 「何か食ひたい」
- 2013.04 (20) 「乾燥しなさい?!」
- 2013.04 (19) 「花冷え」
- 2013.03 (18) 「浦じまい」
- 2013.03 (17) 「葡萄の種をのどに詰まらせて」
- 2013.02 (16) )「てふてふが一匹韃靼海峡を渡って行った」
- 2013.02 (15) 「戦時中」
- 2013.01 (14) 「21世紀を生きるのだから」
- 2012.12 (13) 「うらやんではいけない」
- 2012.12 (12) 「国語は英語でJapanese」
- 2012.11 (11) 「顔が重い」
- 2012.11 (10) 「お雪さま」
- 2012.10 (09) 「ヨダレザクラ」
- 2012.10 (08) 「岸離れ」
- 2012.09 (07) 「米穀通帳をなくしたように寂しい」
- 2012.09 (06) 「衝き居(つきう)」
- 2012.08 (05) 「お暑うございます」
- 2012.08 (04) 「お嫁に行っても困らない」
- 2012.07 (03) 「かしらん」
- 2012.07 (02) 「うるかす」
- 2012.06 (01) 「ずくなし」