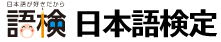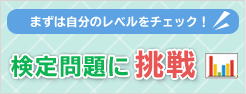夏目漱石は、1867(慶応3)年2月9日、現在の新宿区喜久井町に生まれた。1868(明治元)年時は1歳なので、年齢が明治の元号と符合していてわかりやすい。まさしく明治に生きた作家である。
第二次刊行岩波書店版の漱石全集は、29巻ある。多筆である。処女作『吾輩は猫である』を書いたのは38歳の時。戦前まで、日本人男性の平均寿命は50歳に満たないので、遅いデビューである。そして亡くなったのは、1916(大正5)年49歳の時のことだ。作家活動期間は、わずか10年間程度だった。
ところで「文豪」漱石にも、人間的で意外な一面があった。
漱石が胃潰瘍でなくなったのは周知の事実である。だが、漱石は喰いしん坊だった。好物は、「洋食」で「こってりした脂っこい肉類のようなもの」である。淡泊な豆腐よりは「がんもどきの煮物」に箸をつける。お猪口一杯で赤くなることもある下戸だったが、とくに甘いものには目がなかった。砂糖をまぶした豆菓子、西洋菓子(たとえば到来もののシュークリームを、子どもにわけずに自分だけで食べることもあった)、アイスクリーム(明治期には珍しい製造機が家にあった)、藤むらの羊羹、空也最中、蜜柑、山形の桜桃等々。
胃の調子が悪いと、食事は厳禁である。具合がよくなると、食べられなかった分を取り戻すべく食べたくなる。食べる。タカジアスターゼのような薬を飲む。その繰り返しである。
1916年11月23日、前日に出席した辰野隆の結婚式で出た南京豆がきっかけとなったのか、執筆途中の『明暗』の原稿用紙に漱石が突っ伏しているのがみつかった。
宵には元気を取り戻し、「腹がすいたから、何か食わせろ」と鏡子夫人にせがみ、一片のパンと牛乳を口にするが嘔吐する。
28日頃には気分もよくなり、微量の牛乳、果汁、アイスクリーム、薬を摂るが、内出血をおこして昏倒する。12月2日は薄い葛湯をおいしそうに啜るが、2度目の内出血をして人事不肖に陥る。摂取できる滋養物は、「食塩注射」と「一匙の葡萄酒」だけである。
9日昼過ぎ、4番目の娘愛子がたまらなくなって泣き出し、夫人がなだめると、漱石は眼をつぶりながら「いいよいいよ、泣いてもいいよ」と言った。長男純一が枕元に座ると、目を開いて微笑する。
次男の夏目伸六は、漱石の臨終間際の様子を次のように書いている。
「ふと眼をあけた父の最後の言葉は、『何か食ひたい』と云う、この期に及んで未だに満し得ぬ食欲への切実な願望だったのである。
で、早速、医者の計らいで、一匙の葡萄酒が与えられる事になつたが、
『うまい』
父は、最後の望みをこの一匙の葡萄酒の中に味わって、又静かに眼を閉じたのである。」(『父・漱石とその周辺』1967年、芳賀書店)
「何か食ひたい」「うまい」ということばを引き出した漱石の「脳」と「胃袋」は、今も東大で保存されている。
大本 泉
仙台市出身。仙台白百合女子大学教授。日本ペンクラブ女性作家委員。専門は日本の近現代文学。
著書に『名作の食卓』(角川書店)、共編著に『日本語表現 演習と発展』『同【改訂版】』(明治書院)、共著に『永井荷風 仮面と実像』(ぎょうせい)等がある。
記事一覧
- 2017.11 (31) 「羊羹」
- 2015.10 (30) 「世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない」
- 2015.01 (29) 「猫」
- 2014.07 (28) 「おでん」
- 2014.04 (27) 「すし」
- 2014.01 (26) 「のんのんのんのん」
- 2013.10 (25) 「じぇじぇじぇ」
- 2013.08 (24) 「一日作さざれば一日食らわず」
- 2013.07 (23) 「宮城県の方言」
- 2013.06 (22) 「天ぷら」
- 2013.06 (21) 「何か食ひたい」
- 2013.04 (20) 「乾燥しなさい?!」
- 2013.04 (19) 「花冷え」
- 2013.03 (18) 「浦じまい」
- 2013.03 (17) 「葡萄の種をのどに詰まらせて」
- 2013.02 (16) )「てふてふが一匹韃靼海峡を渡って行った」
- 2013.02 (15) 「戦時中」
- 2013.01 (14) 「21世紀を生きるのだから」
- 2012.12 (13) 「うらやんではいけない」
- 2012.12 (12) 「国語は英語でJapanese」
- 2012.11 (11) 「顔が重い」
- 2012.11 (10) 「お雪さま」
- 2012.10 (09) 「ヨダレザクラ」
- 2012.10 (08) 「岸離れ」
- 2012.09 (07) 「米穀通帳をなくしたように寂しい」
- 2012.09 (06) 「衝き居(つきう)」
- 2012.08 (05) 「お暑うございます」
- 2012.08 (04) 「お嫁に行っても困らない」
- 2012.07 (03) 「かしらん」
- 2012.07 (02) 「うるかす」
- 2012.06 (01) 「ずくなし」