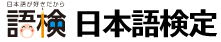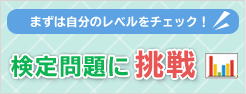過去の記憶にその後の人生を支配されることはあまり望まないし、生活の中では、できるだけ、昔語りをしないことにしている。
子どもに昔の記憶を聞かれても、大抵「忘れた」で押し通すし、過去の堆積は、今を生きる上での拠りどころとはしたくない。しかし、何十年も前のある記憶に、今の私を照射する特別な意味を見出したとき、その記憶を持ち続けた自分に感謝したいときもある。
そのひとつが、小学一年生のときの授業参観日の記憶。あの頃「父兄」と呼ばれた、そのほとんどが母親の保護者たちが、私たち一年生の英語の授業を参観していた。
東京郊外の小さなキリスト教系の学校で、当時設立されて十年ほど、教員は修道会の修道女たちと、そして熟練の教員が集められたのか、もう定年間近といった老練の教員が多かった。一年生の眼から見たら、どの先生もずいぶんな年寄りに見えたものだ。
キリスト教系の学校の多くがそうであるように、そこも小学生から英語の授業があった。一年生に英語を教えてくれたのは、その小学校で唯一若いといえた日本人の女性教師、併設の中学・高校の足の不自由な日本人の男の先生、そして日系ハワイ人の修道女の校長。校長の授業の日は、クラスの男女ふたりが、高校の校舎一階の校長室まで、うやうやしく彼女をお迎えに行くという儀式もあった。小中高の校長兼務の忙しい人が、授業時間を失念しないように、という配慮だったのだろうか。
その校長の授業が参観の対象で、教室は木製の長いベンチに腰掛ける、正装した母親たちでいっぱいだった。教室の清浄な空気は、頭の痛くなるような化粧品のにおいで充満し、それが私にとっては参観日の象徴だった。
その日、校長は生徒ひとりひとりに、「どの科目がすき」と英語で尋ねた。私は、「国語」と答えたかったが、「ええと、国語って、英語でなんというのだろう」と頭の中でいそがしく考えても答えはない。順番が来たとき、困って、日本語を解する校長に「国語」と言うと、黒縁眼鏡に顎の少しとがった顔立ちの校長は、穏やかに”Japanese”と教えてくれた。
「Japanese、え、国語はJapaneseなの、知っている言葉じゃない」とうろたえた記憶、「英語はEnglishなんだから、そうか、国語、という言葉があるわけじゃないんだ、Japaneseでいいんだ」とすぐ得心がいった記憶、そして、そのときの奇妙な感覚の記憶。
何が奇妙だったかといえば、それまで「国語」という言葉が私の中で主張していた他言語との境界線が一瞬にして解かれ、「国語」が一挙にJapaneseとしてEnglishと同列の一言語になってしまった感覚の奇妙さである。その瞬間、「国語」は私の中で「日本語」となり、言語のひとつに相対化されたと思う。
成り行きで日本語教師の職に就いた私だが、あるとき、ふと、あの日の授業参観の記憶に今の私の原点があるのではないかと思ったとき、やはり感慨というほかはない感情に襲われたことは忘れがたい。
阿部 由美子(あべ ゆみこ)
東海大学湘南校舎国際教育センター非常勤講師(日本語教育)
記事一覧
- 2017.11 (31) 「羊羹」
- 2015.10 (30) 「世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない」
- 2015.01 (29) 「猫」
- 2014.07 (28) 「おでん」
- 2014.04 (27) 「すし」
- 2014.01 (26) 「のんのんのんのん」
- 2013.10 (25) 「じぇじぇじぇ」
- 2013.08 (24) 「一日作さざれば一日食らわず」
- 2013.07 (23) 「宮城県の方言」
- 2013.06 (22) 「天ぷら」
- 2013.06 (21) 「何か食ひたい」
- 2013.04 (20) 「乾燥しなさい?!」
- 2013.04 (19) 「花冷え」
- 2013.03 (18) 「浦じまい」
- 2013.03 (17) 「葡萄の種をのどに詰まらせて」
- 2013.02 (16) )「てふてふが一匹韃靼海峡を渡って行った」
- 2013.02 (15) 「戦時中」
- 2013.01 (14) 「21世紀を生きるのだから」
- 2012.12 (13) 「うらやんではいけない」
- 2012.12 (12) 「国語は英語でJapanese」
- 2012.11 (11) 「顔が重い」
- 2012.11 (10) 「お雪さま」
- 2012.10 (09) 「ヨダレザクラ」
- 2012.10 (08) 「岸離れ」
- 2012.09 (07) 「米穀通帳をなくしたように寂しい」
- 2012.09 (06) 「衝き居(つきう)」
- 2012.08 (05) 「お暑うございます」
- 2012.08 (04) 「お嫁に行っても困らない」
- 2012.07 (03) 「かしらん」
- 2012.07 (02) 「うるかす」
- 2012.06 (01) 「ずくなし」