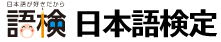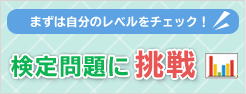先日、小学校時代の同級生が、卒業時に書いた寄せ書きを持ってきた。当時の筆者が友人に贈ったことばは、「すきなたべもの。とらやのようかん」。惜別の辞でもなんでもない。何故、そのようなことを書いたのか思い出せない。食い意地が張っていたのは今も同じである。
東日本大震災の時、贅沢なことに、惣菜より嗜好品のないのがつらかった。冷蔵庫に以前間違って入れていた羊羹を発見した時は嬉しかった。一か月程停電状態だったので、一種の保存食を戸棚に入れていたのと同じである。
ところで羊羹は、もともと中国で作られていた羊の羹(あつもの)だった。羊肉を煮たお吸い物のようなものである。鎌倉時代、禅僧が日本に伝えたが、殺生の戒めから、羊を小豆に替えて精進料理として作った。そして、茶の湯が盛んになると、蒸し物から菓子に変わっていった。『庭訓往来』(1536年)に、点心としての「ようかん」の名があることから、その起源を16世紀に遡ることができる。
古来中国では、羊の肝に似せて小豆と砂糖で煮る「羊肝糕」「羊肝餅」があり、これがルーツだとする説もある(『嬉遊笑覧』1830年)。羊羹の文字が使われるようになったのは、中国音のキャング(羹)、あるいはカウ(羹)とカン(肝)という音が似ていたためという(『大言海』1932-37年)。
ちなみに練羊羹は、1589年、和歌山の駿河屋5代目岡本善右衛門により作られたというのが定説である。溶かした寒天を槽に流し込んで固めて棹物に切るものだったので、羊羹を1棹、2棹と数えるのは、この頃から生れたのかもしれない。そして、1626年、金沢の茶人だった浅香忠左衛門が赤小豆で作ったのが、本郷の藤村羊羹のはじまりだという。現在、藤村は、残念ながら看板をおろしている。
甘党の夏目漱石も羊羹が好物だった。処女作『吾輩は猫である』(1905-06年)の中で、苦沙弥と迷亭が話しながら羊羹をつまむ箇所がある。よくとりあげられるが、『草枕』(1906年)における「余」の羊羹を芸術品として絶賛する語りの部分が印象深い。
「余は凡ての菓子のうちで尤も羊羹が好だ。別段食ひたくはないが、あの肌合が滑らかに、緻密に、しかも半透明に光線を受ける具合は、どう見ても一個の美術品だ。ことに青味を帯びた練上げ方は、玉と蝋石の雑種の様で、甚だ見て心持ちがいゝ。のみならず青磁の皿に盛られた青い練羊羹は、青磁のなかゝら今生れた様につやつやして、思はず手を出して撫でゝ見たくなる。西洋の菓子で、これ程快感を与へるものは一つもない。クリームの色は一寸柔かだが、少し重苦しい。ジエリは、一目宝石の様に見えるが、ぶるぶる顫へて、羊羹程の重味がない。白砂糖と牛乳で五重の塔を作るに至つては、言語道断の沙汰である。」
近代文学において、西洋菓子のクリーム、ジェリー、デコレーションケーキと相対化し、比喩表現を駆使して、羊羹がはじめて客体としてデッサンされたのが、漱石の『草枕』なのではないかというのが、筆者の仮説である。
時代が降りて、昭和期に発表された向田邦子の水羊羹をとりあげた随筆も名文である。
「水羊羹の命は切口と角であります。宮本武蔵か眠狂四郎が、スパッと水を切ったらこうもなろうかというような鋭い切口と、それこそ手の切れそうなとがった角がなくては、水羊羹といえないのです。(中略)水羊羹は江戸っ子のお金と同じです。宵越しをさせてはいけません。傷みはしませんが、『しわ』が寄るのです。表面に水気が滲み出てしまって、水っぽくなります。水っぽい水羊羹はクリープを入れないコーヒーよりも始末に悪いのです。固い水羊羹。これも下品でいけません。色も黒すぎては困ります。」(『眠る盃』1979年)
このように、作家の食べものへの執着が、名作を生んだ。作家としての矜持が、卓越した描写を生んだ。
大本 泉
仙台市出身。仙台白百合女子大学教授。日本ペンクラブ女性作家委員。専門は日本の近現代文学。
著書に『名作の食卓』(角川書店)、共編著に『日本語表現 演習と発展』『同【改訂版】』(明治書院)、共著に『永井荷風 仮面と実像』(ぎょうせい)等がある。
記事一覧
- 2017.11 (31) 「羊羹」
- 2015.10 (30) 「世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない」
- 2015.01 (29) 「猫」
- 2014.07 (28) 「おでん」
- 2014.04 (27) 「すし」
- 2014.01 (26) 「のんのんのんのん」
- 2013.10 (25) 「じぇじぇじぇ」
- 2013.08 (24) 「一日作さざれば一日食らわず」
- 2013.07 (23) 「宮城県の方言」
- 2013.06 (22) 「天ぷら」
- 2013.06 (21) 「何か食ひたい」
- 2013.04 (20) 「乾燥しなさい?!」
- 2013.04 (19) 「花冷え」
- 2013.03 (18) 「浦じまい」
- 2013.03 (17) 「葡萄の種をのどに詰まらせて」
- 2013.02 (16) )「てふてふが一匹韃靼海峡を渡って行った」
- 2013.02 (15) 「戦時中」
- 2013.01 (14) 「21世紀を生きるのだから」
- 2012.12 (13) 「うらやんではいけない」
- 2012.12 (12) 「国語は英語でJapanese」
- 2012.11 (11) 「顔が重い」
- 2012.11 (10) 「お雪さま」
- 2012.10 (09) 「ヨダレザクラ」
- 2012.10 (08) 「岸離れ」
- 2012.09 (07) 「米穀通帳をなくしたように寂しい」
- 2012.09 (06) 「衝き居(つきう)」
- 2012.08 (05) 「お暑うございます」
- 2012.08 (04) 「お嫁に行っても困らない」
- 2012.07 (03) 「かしらん」
- 2012.07 (02) 「うるかす」
- 2012.06 (01) 「ずくなし」