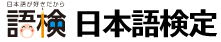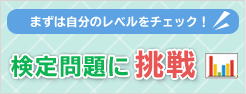2013年12月、和食:日本人の伝統的な食文化がユネスコの無形文化遺産に登録された。日本食は世界で大ブームである。最近は、ヨーロッパでも、箸の使い方の上手な人が増えた。
日本食の中でもすしは人気がある。回転寿司のある国では、地元の人達の利用でにぎわっている。
「すし」ということばは、「酸し」、つまり酸っぱいという意味から生まれた。
「すし」」には、「鮨」と「鮓」の漢字が用いられるが、「鮨」は魚の塩辛(『爾雅』紀元前5~3世紀)、「鮓」は塩と米によって魚を醸した漬物(『釈名』後漢:3世紀)、すなわちなれずしにつながるものといった意味の違いがあったようである。
「寿し」「寿司」はおめでたい当て字だとしても、「鮓」という漢字を使う方が正しいのだろう。漢字が混用されるようになったのは、『広雅』(3世紀)が「鮨」と「鮓」を同義として挙げていることが原因らしい。
「鮨」と「鮓」の文字が、日本の最古の文字記録資料に挙げられている例として、正倉院文書『尾張国正税帳』(天正6<734>年)に「白貝内鮨」とある。『養老令』(養老2<<18>年)の基となった『大宝令』(大宝元<701>年)にも、「鰒鮓二斗、胎貝鮓三斗、雑鮓五斗」と「鮓」の文字があったと指摘されている。
石毛直道はすしの発祥地候補を東北タイやミャンマーあたりの平野部と挙げたが、東南アジアから中国大陸を経て、日本には奈良時代にはすでに「すし」があったと考えられる。すしが米を使う食べものであることを考えれば、日本への伝来は、縄文晩期(紀元前2~300年前)まで遡るかもしれない。すしの形は、なれずしから発酵期間を短くした早ずしへ、そして押しずしから現在の新鮮な魚を食べる握りずしへ変遷していった。この過程を経て、日本独自の食べものが誕生した。
近代文学では、樋口一葉作『たけくらべ』に「朝飯がすすまずは後刻に鮨(やすけ)でも誂(あつら)へようか」とあるように、「弥助」という隠語で登場する。吉野のつるべずし弥助から転用されたのである。
すしが重要な素材として扱われている作品の一つに、志賀直哉作『小僧の神様』がある。秤屋の小僧仙吉は、握りずしを食べたことがない。往復の電車賃をもらうと帰りは歩いて小銭を4銭貯め、ある日、番頭が話していたつうの行くすし屋に入ってみた。
「小僧は少し思い切った調子で、こんな事は初めてじゃないと云うように、勢よく手を延ばし、三つ程並んでいる鮪の鮨の一つを摘んだ。ところが、何故か小僧は勢よく延ばした割に其手をひく時、妙に躊躇した。/『一つ六銭だよ』と主が云った。/小僧は落すように黙って其鮨を又台の上に置いた。/『一度持ったのを置いちゃあ、仕様がねえな』そう云って主は握った鮨を置くと引きかえに、それを自分の手元へかえした。/小僧は何も云わなかった。小僧はいやな顔をしながら、其場が一寸動けなくなった。然し直ぐ或勇気を振るい起して暖簾の外へ出て行った。」
当時、握りずし一人前が15銭位だったので、そう安い店ではなさそうである。落胆する小僧の一部始終を見ていた貴族院議員Aは、後日、素性を隠して仙吉にすしをごちそうする。しかしAは、自分が高所に立ってすしをおごったことに気づき、「変に淋しい、嫌な気持」になる。
そのやるせない思いも、すしの酸っぱさをとおして伝わってくるような作品である。
大本 泉
仙台市出身。仙台白百合女子大学教授。日本ペンクラブ女性作家委員。専門は日本の近現代文学。
著書に『名作の食卓』(角川書店)、共編著に『日本語表現 演習と発展』『同【改訂版】』(明治書院)、共著に『永井荷風 仮面と実像』(ぎょうせい)等がある。
記事一覧
- 2017.11 (31) 「羊羹」
- 2015.10 (30) 「世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない」
- 2015.01 (29) 「猫」
- 2014.07 (28) 「おでん」
- 2014.04 (27) 「すし」
- 2014.01 (26) 「のんのんのんのん」
- 2013.10 (25) 「じぇじぇじぇ」
- 2013.08 (24) 「一日作さざれば一日食らわず」
- 2013.07 (23) 「宮城県の方言」
- 2013.06 (22) 「天ぷら」
- 2013.06 (21) 「何か食ひたい」
- 2013.04 (20) 「乾燥しなさい?!」
- 2013.04 (19) 「花冷え」
- 2013.03 (18) 「浦じまい」
- 2013.03 (17) 「葡萄の種をのどに詰まらせて」
- 2013.02 (16) )「てふてふが一匹韃靼海峡を渡って行った」
- 2013.02 (15) 「戦時中」
- 2013.01 (14) 「21世紀を生きるのだから」
- 2012.12 (13) 「うらやんではいけない」
- 2012.12 (12) 「国語は英語でJapanese」
- 2012.11 (11) 「顔が重い」
- 2012.11 (10) 「お雪さま」
- 2012.10 (09) 「ヨダレザクラ」
- 2012.10 (08) 「岸離れ」
- 2012.09 (07) 「米穀通帳をなくしたように寂しい」
- 2012.09 (06) 「衝き居(つきう)」
- 2012.08 (05) 「お暑うございます」
- 2012.08 (04) 「お嫁に行っても困らない」
- 2012.07 (03) 「かしらん」
- 2012.07 (02) 「うるかす」
- 2012.06 (01) 「ずくなし」