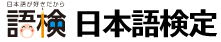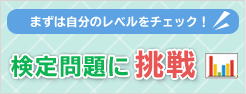「水鳥」は、「みずとり」か「みずどり」かという問題です。それぞれの語形におけるアクセントも検討を要します。「水鳥」は「鴨かも・鶴つる・白鳥など、水上や水辺にすむ鳥の総称」(『新選国語辞典 第10版』)です。本題に入る前に簡単にアクセントの説明をします。日本語の標準語のアクセントは、単語ごとに決まっている音の高低のことです。たとえば「
ここから「水鳥」について考えます。清濁のゆれは、以前から問題になることがあり、菊谷(1984)には、NHKにおける扱いが述べられています。
この記述のあと、アンケートの結果をもとにして、有識者に「みずとり」が多く、学生に「みずどり」が多いことが述べられます。このようなゆれは現在でも続いています。たとえば先日、ある時代劇ドラマを見ていたところ、登場人物の俳優とナレーターが「み
上記のことをもとにして、次のことを以下で考察します。
- ①
- 人はふだん「み
ずとり 」という語に接する機会があるのかどうか。 - ②
- なぜ「み
ずどり ・みず どり」が広がったのか。
まず①について。学校で『平家物語』を学ぶときなどに富士川の戦い(1180年、平氏と源氏の戦い)の場面に出てくる「水鳥」の語を目にして「み
以上のことからわかるのは、日本史や日本文学を学ぶ際には「み
次に②について考えます。語形に関しては「う
以上のように、「水鳥」の語形・アクセントが変わる、それなりの理由があることがわかりました。ただし筆者としては、「水鳥」が「海鳥」「山鳥」と足並みをそろえなくてもよい理由も、あわせて考えてみたくなります。よく知られていることとして、鼻音(鼻から息が出る音)の「ん」に続く場合に連濁が起こりやすいという現象があります。動詞で説明すると、助詞の「て」をつけた際、「書いて」「受けて」のように「ん」がなければ「て」は清音のままですが、「読んで」「飛んで」などは濁音の「で」となります。「海鳥」「山鳥」の場合、[mi][ma]というように間に母音が入りますから単独の「ん」とは異なりますが、[m]という鼻音がすぐ前にあることは確かです。「水鳥」の「ず」には鼻音はありません。それゆえ、鼻音のある「海鳥」「山鳥」は「どり」と連濁するが、「水鳥」は鼻音がないから清音のままでもおかしくない、と考えることとします。歴史的事実として、そのような要因により「水鳥」が清音であり続けたとは主張しません注1。そうではなく、現代人が「み
先に述べたように、一般に文章の中で「水鳥」は難読ではない語と捉えられて、語形が示されることがありませんが、清濁がゆれていること、また音読みの「す
例外的に語形がしっかり示されている作品があります。それは『万葉集』です。各社から刊行されている『万葉集』巻19-4261の歌(天武天皇をたたえる歌)には、読みがなが添えられているので、現代人が歌を味わう際に助かります。アクセントはわからないにしても、清濁の部分は、読みがなを頼りにして迷わず清音で読むことが可能です。最後に歌の本文を記して今回のコラムを終わります。
大君は神にしませば
注1 母音を挟んで「と」の前に鼻音が存在しない語であっても、「都鳥」「千鳥」「夏鳥」などは連濁しています。
注2 京阪地方では「
参考文献 NHK放送研究部(2001)「放送用語委員会(東京)用語の決定」『放送研究と調査』51-4
菊谷彰(1984)「「発音のゆれアンケート」から」『放送研究と調査』34-6
![]()
中川秀太
文学博士、日本語検定 問題作成委員
専攻は日本語学。文学博士(早稲田大学)。2017年から日本語検定の問題作成委員を務める。
- 最近の研究
- 「現代語における動詞の移り変わりについて」(『青山語文』51、2021年)
- 「国語辞典の語の表記」(『辞書の成り立ち』2021年、朝倉書店)
- 「現代の類義語の中にある歴史」(『早稲田大学日本語学会設立60周年記念論文集 第1冊』2021年、ひつじ書房)など。
コラム一覧
- 2026.2 (49)「『地酒』の語釈」
- 2026.1 (48)「『ほぼほぼ』『やっぱり』『わざわざ』 その副詞は何のために?」
- 2025.12 (47)「『ドッジボール』か? それとも『ドッチボール』か?」
- 2025.11 (46)「デアル体とダ体の詳細」
- 2025.10 (45)「『孔子』や『孫子』のアクセント」
- 2025.9 (44)「比喩的な『続投』が捨てられない理由」
- 2025.8 (43)「1日のうちに行う動作を表す連用形名詞+晩酌」
- 2025.7 (42)「『かき氷』関連のボキャブラリー」
- 2025.6 (41)「代名詞の表記」
- 2025.5 (40)「連体詞の表記②」
- 2025.4 (39)「連体詞の表記①」
- 2025.3 (38)「語頭のラ行音」
- 2025.2 (37)「接続詞の表記」
- 2025.1 (36)「一語文の用法を持つヒト名詞」
- 2024.12 (35)「朝昼晩のあいさつのことば」
- 2024.11 (34)「接頭辞の『ま』『ど』『せい』」
- 2024.10 (33)「相撲の世界における動詞の特別な使い方」
- 2024.9 (32)「数字の語形と表記」
- 2024.8 (31)「ぼかす副助詞」
- 2024.7 (30)「『甲の乙』という形の単語について」
- 2024.6 (29)「母音が連続するときの発音」
- 2024.5 (28)「『現代仮名遣い』と表音一致」
- 2024.4 (27)「動詞のウ音便について」
- 2024.3 (26)「『かな(仮名)』の語形とアクセントと表記」
- 2024.2 (25)「『わかる』のコミュニケーション文法」
- 2024.1 (24)「『よりか』とは何か」
- 2023.12 (23)「『お』と体の部分」
- 2023.11 (22)「質問という行為について」
- 2023.10 (21)「しこ名の『~川』」
- 2023.9 (20)「『~ていただきたいです』という表現について」
- 2023.8 (19)「今に生きる旧国名の別称」
- 2023.7 (18)「『可決・成立する』は是か非か」
- 2023.6 (17)「語頭に[p]の音を持つ単語のこと」
- 2023.5 (16)「『いる』と『おる』の活用形」
- 2023.4 (15)「『ローマ字のつづり方』は実用的か否か」
- 2023.3 (14)「御しがたいひと言『なるほど』のこと」
- 2023.2 (13)「『~犬』はイヌかケンか」
- 2023.1 (12)「『ありか』『かくれが』『すみか』の表記」
- 2022.12 (11)「みずうみ・ぬま・いけ」
- 2022.11 (10)「『お間違いありませんか(お間違いないですか)』に問題はありませんか」
- 2022.10 (09)「現代の1拍語」
- 2022.9 (08)「動植物名を表す漢字について」
- 2022.8 (07)「現代語における女の人の一人称」
- 2022.7 (06)「『水鳥』の語形とアクセント」
- 2022.6 (05)「動物と敬称②」
- 2022.5 (04)「動物と敬称①」
- 2022.4 (03)「『東方・西方』の語形」
- 2022.3 (02)「『母方・父方』の語形」
- 2022.2 (01)「『失礼します』か『失礼しました』か」