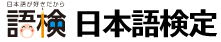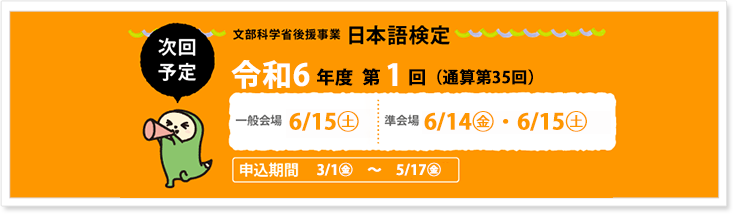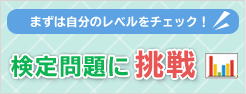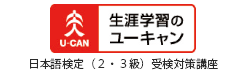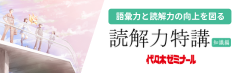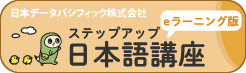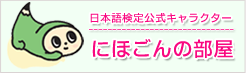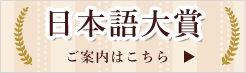前回に引き続き、連体詞の表記を扱います。今回は、表記のゆれが生じやすい事例と、その理由について考えます。
表記のゆれ1:いろんな、そしらぬ、ほんの
『NHKアクセント』では「いろんな」は、かな書きとされています。これは、表記辞典のほうに「いろいろ」がかな書きであるのに合わせた結果です。colorの意味が生きていないと考えての処理です。共同通信も東京書籍も「いろいろ」は、かな書きを標準としています。これらの業界においては統一がとれそうですが、国語辞典の中には「色色」「色んな」を標準表記とするものもあるので、世間一般の実態としては、表記にゆれが見られます。
「そしらぬ」は、漢字で書くなら「素知らぬ」となります。「そ」の語源は確定していないようです。そうすると、「素」には当て字の疑いが出てきます。当て字をあまり使わないようにしている立場では、「そ知らぬ」か「そしらぬ」かとなるところですが、前者だと一語として捉えにくいと見るならば、「そしらぬ」が選ばれることとなります。『NHK漢字』、東京書籍は「そしらぬ」、共同通信は「素知らぬ」を採用しています。
「ほんの少し」の「ほんの」をNHKはかな書きにしています。ほかの表記辞典には項目がありません。多くの国語辞典では「本の」を標準表記としますが、「本の」から「本当の」という意味を引き出せるユーザーがどれだけいるでしょうか。また、「本の」とあれば、bookのほうがまず思い浮かびます。もちろん、「本の少し」とあれば、「少し」まで見て、ホ\ンノではなくホンノ ̄であると気づきはしますが、漢字で書くほどのことばかという疑念は残ります。
表記のゆれ2:さらなる
副詞と関係がある連体詞が「さらなる」です。「さらに」が副詞です。それゆえ、副詞がかな書きなのか漢字表記なのかによって、連体詞の表記も決まります。『NHK漢字』は、「①さらに②更に」を採用します。アクセント辞典には、「さらに」と「さらなる」両方が載り、どちらも優先がかな書き、許容の表記が漢字表記です。東京書籍の辞書には「さらに」が、共同通信の辞書には「さらに」「さらなる」がかな書きの語として載っています。
共同通信が漢字表記にする「全て」「互いに」の場合、「全部」「交互」といった漢語の熟語と照らし合わせて、「すべて」「たがいに」の意味を理解することが可能であり、漢字を使う意義があると言えますが、「更に」「更なる」の場合、「更」の字には、「そのうえ」「ますますの」の意味に相当する熟語がすぐには見当たりません。そこで、無理に漢字を使うこともないという判断がとられることとなります。
この語も国語辞典では「更なる」が載っていますから、一般的にはゆれがそれなりに起こっているものと考えられます。
表記のゆれ3:わが
『NHK漢字』は「①わが②我が」とし、共同通信は「わが」のみであるため、マスコミ業界では統一がとれます。どちらも「われ」についてもかな書きを標準としています。東京書籍は「我が」を標準とします。「我が家」「我が国」とした場合、「われが」とする誤読がありそうです。他方、「我我」「我ら」を「わわ」「わら」と誤読する恐れは低そうです。漢字をさけたくなる要因は、「わ(が)」と読むべき語のほうにあると解釈します。
表記のゆれ4:きたる、さる
この二つは、「公用文」と同じように「来る」「去る」とする東京書籍、「来たる」「さる」とする読売新聞(共同通信も「来たる」とするが、「さる」の見出しがない)、それから「①きたる②来る」「去る」とする『NHK漢字』とのあいだでゆれがあります。学習効率から言えば、「来る」「去る」か「きたる」「さる」とするのがよさそうです。
「来たる」について、共同通信の『記者ハンドブック 第14版』には、「本来は「来る」だが、動詞「来=く=る」と紛らわしいので「来たる」と表記する」という注が載ります。読売新聞でも(動詞の「きたる」は)「送り仮名は活用語尾から送るという原則からすれば「来る」となるが、「来(く)る」と誤読されるおそれがあるため、「た」から送る。また、内閣告示「送り仮名の付け方」には連体詞の「来る」が示されているが、これも同様に「来たる」とする」としています。動詞の「きたる」を「球春来たる」「待ち人来たらず」「若者来たれ」のように使う場合を想定しての処理です。
ポイントは、動詞と連体詞との区別が紛らわしいのか、「くる」と「きたる」の区別がつきにくいのか、二つの動機が入り交じっているということです。動詞・連体詞の場合、「来る」のみを見ただけでは確かに紛らわしさがありますが、連体詞のほうは「来る15日」のように数詞の前に固定的に用いるため、これを動詞であると誤解する恐れは実際には低いでしょう。動詞・連体詞のみを考えるなら、「来る・去る」でも問題はありません。もっとも「きたる」という語を知らない人が「来る」を「くる」と読む恐れは残ります。そこまで考慮するなら「きたる・さる」の組み合わせがベターとなります。
次に「くる」と「きたる」の区別については、どうでしょうか。「球春来る」「待ち人来らず」「若者来れ」のうち、後ろの二つについては、「くる」の活用では解釈できないため、「きたらず」「きたれ」と判断することが可能です。紛らわしいのは、終止形の場合です。読売新聞のように送りがなで処理する方法もありますが、終止形のみは「来(きた)る」というように読みがなをつけて処理することもできます。または、動詞も連体詞も「きたる」を標準とすれば、「くる」との区別は容易につきます。
表記のゆれ5:かの
共同通信は、「彼女」には漢字を使いますが、「かの地」「かの人」は、かな書きとします。『NHK漢字』には「かの〔彼〕~人」とあり、「彼」は使わない漢字としてあります。表外音訓の記号はついていません。他方、東京書籍は「かの」を用い、「彼の」は表外音訓を用いた表記であると示しています。
国語辞典では、『学研現代新国語辞典 改訂第6版』『大辞林 第4版』が「彼の」を表内音訓として扱い、『岩波国語辞典 第8版』『旺文社国語辞典 第12版』『旺文社標準国語辞典 第8版』『現代国語例解辞典 第5版』『三省堂現代新国語辞典 第7版』『三省堂国語辞典 第8版』『新選国語辞典 第10版』『新明解国語辞典 第8版』『明鏡国語辞典 第3版』は表外音訓として扱います。
このようなゆれが起こるのは、「常用漢字表」の扱いに原因があります。漢字表の「彼」には、音読みの「ひ」、訓読みの「かれ」「かの」が示されています(1948年の「当用漢字音訓表」のときから)。このうち、「かの」は、「特別なものか、又は、用法のごく狭いもの」として掲げられ、語例として「彼女」が載っています。この「かの」について、ほかの語にも適用できる読みであると判断すれば、「彼地」または「彼の地」と書けることとなり、「彼女」のみに使える読みであると判断すれば、「彼地」「彼の地」は表外音訓による表記となります。国語辞典では、後者の判断をしているものが多いということです。武部(1979、p.82)には「「彼・かの」の場合に例欄に「彼女」一語だけが掲げられているのは、それ以外の用例(この場合は「かの地」「かの男」など)に用いないという趣旨である」と説明されています。
新聞や放送の現場では、「彼女」以外に使うことを国は想定していないのであろう、また、「この」「その」「あの」「どの」に対して、「かの」のみ「彼(の)」と書くことになると、同種の語とのバランスが損なわれてしまう、といったことも考慮に入れて、「かの」を選ぶという判断をしています。しかし本来であれば、「常用漢字表」そのものに、「かの」は「彼女」のみに使うとする注記を掲げるのが望ましいでしょう。あるいは、ほかの語にも適用してよいとするなら、はっきりそう書く必要があります。
まとめ
連体詞は、新たに作られることがあまりありません。ここまでに見たポイントを押さえたうえで、自身の表記方針を固めれば、文章を書く際に表記のゆれが生じるのを防ぐことが十分に可能な品詞と言えます。
参考文献
武部良明(1979)『日本語の表記』角川書店
![]()
中川秀太
文学博士、日本ウェルネススポーツ大学スポーツプロモーション学部 准教授、日本語検定 問題作成委員
専攻は日本語学。文学博士(早稲田大学)。2017年から日本語検定の問題作成委員を務める。
- 最近の研究
- 「現代語における動詞の移り変わりについて」(『青山語文』51、2021年)
- 「国語辞典の語の表記」(『辞書の成り立ち』2021年、朝倉書店)
- 「現代の類義語の中にある歴史」(『早稲田大学日本語学会設立60周年記念論文集 第1冊』2021年、ひつじ書房)
- 「現代日本語のジェネレーションギャップ」(2024年、武蔵野書院)など。
コラム一覧
- 2026.1 (48)「『ほぼほぼ』『やっぱり』『わざわざ』 その副詞は何のために?」
- 2025.12 (47)「『ドッジボール』か? それとも『ドッチボール』か?」
- 2025.11 (46)「デアル体とダ体の詳細」
- 2025.10 (45)「『孔子』や『孫子』のアクセント」
- 2025.9 (44)「比喩的な『続投』が捨てられない理由」
- 2025.8 (43)「1日のうちに行う動作を表す連用形名詞+晩酌」
- 2025.7 (42)「『かき氷』関連のボキャブラリー」
- 2025.6 (41)「代名詞の表記」
- 2025.5 (40)「連体詞の表記②」
- 2025.4 (39)「連体詞の表記①」
- 2025.3 (38)「語頭のラ行音」
- 2025.2 (37)「接続詞の表記」
- 2025.1 (36)「一語文の用法を持つヒト名詞」
- 2024.12 (35)「朝昼晩のあいさつのことば」
- 2024.11 (34)「接頭辞の『ま』『ど』『せい』」
- 2024.10 (33)「相撲の世界における動詞の特別な使い方」
- 2024.9 (32)「数字の語形と表記」
- 2024.8 (31)「ぼかす副助詞」
- 2024.7 (30)「『甲の乙』という形の単語について」
- 2024.6 (29)「母音が連続するときの発音」
- 2024.5 (28)「『現代仮名遣い』と表音一致」
- 2024.4 (27)「動詞のウ音便について」
- 2024.3 (26)「『かな(仮名)』の語形とアクセントと表記」
- 2024.2 (25)「『わかる』のコミュニケーション文法」
- 2024.1 (24)「『よりか』とは何か」
- 2023.12 (23)「『お』と体の部分」
- 2023.11 (22)「質問という行為について」
- 2023.10 (21)「しこ名の『~川』」
- 2023.9 (20)「『~ていただきたいです』という表現について」
- 2023.8 (19)「今に生きる旧国名の別称」
- 2023.7 (18)「『可決・成立する』は是か非か」
- 2023.6 (17)「語頭に[p]の音を持つ単語のこと」
- 2023.5 (16)「『いる』と『おる』の活用形」
- 2023.4 (15)「『ローマ字のつづり方』は実用的か否か」
- 2023.3 (14)「御しがたいひと言『なるほど』のこと」
- 2023.2 (13)「『~犬』はイヌかケンか」
- 2023.1 (12)「『ありか』『かくれが』『すみか』の表記」
- 2022.12 (11)「みずうみ・ぬま・いけ」
- 2022.11 (10)「『お間違いありませんか(お間違いないですか)』に問題はありませんか」
- 2022.10 (09)「現代の1拍語」
- 2022.9 (08)「動植物名を表す漢字について」
- 2022.8 (07)「現代語における女の人の一人称」
- 2022.7 (06)「『水鳥』の語形とアクセント」
- 2022.6 (05)「動物と敬称②」
- 2022.5 (04)「動物と敬称①」
- 2022.4 (03)「『東方・西方』の語形」
- 2022.3 (02)「『母方・父方』の語形」
- 2022.2 (01)「『失礼します』か『失礼しました』か」