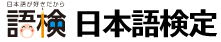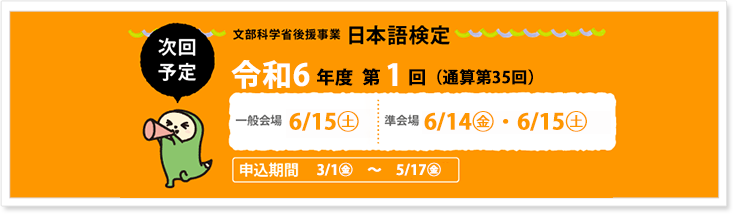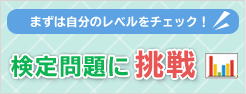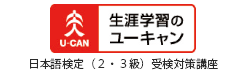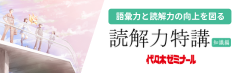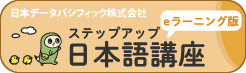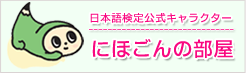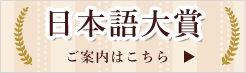「そして」や「しかし」などの接続詞は、現在はかな書きが一般的ですが、かつては「然して・而して」「然し・併し」などと書かれることもありました。どういう理由により、漢字表記が行われなくなったのか、また、接続詞は、一般的にかな書きをするものと考えてよいのかどうか、こういったことを検討します。
国語施策(しさく)と接続詞の表記
「当用漢字表」(1946)の「使用上の注意事項ロ」に「代名詞・副詞・接続詞・感動詞・助動詞・助詞は、なるべく仮名書きにする」という内容が示されています。これが「当用漢字表」および「当用漢字音訓表」(1948)の行われた時代における接続詞の表記の基準です。「然して」「併し」といった書き方は、「然」「併」に「そして」「しかし」といった訓が認められなかったため(現在の「常用漢字表」(2010)でも同じ)、漢字表に従って書くなら当然「そして」「しかし」となります。
その後、「常用漢字表」(1981)の時代となり、三省堂編修所編(2022)によれば、漢字表には「代名詞・副詞・接続詞で広く使用されるものは語例として漢字で掲げてある」「感動詞・助動詞・助詞は語例欄にも掲げられていない」とのことです。
以上から、接続詞は、かな書きが一般的であるものの、中には漢字表記が普通の語もあるという見込みが成り立ちます。このことを前提として、以下では、教科書、新聞、放送の表記について、『教科書 表記の基準2021年版』(東京書籍、以下『教科書』と略記)、『新聞用語集 2022年版』(新聞協会、以下『新聞』)、『記者ハンドブック 第14版』(共同通信、以下『共同』)、『読売新聞用字用語の手引 第7版』(『読売』)、『NHK漢字表記辞典』(『NHK』)を用いて、どこに表記のゆれ、つまり表記の安定性を妨げるネック(障害)があるかを考えます。公用文については、2021年の「新しい「公用文作成の要領」に向けて」(報告)を参照します。
対象とする接続詞は、『NHK日本語発音アクセント新辞典』(2016)から抜き出した76語です。
かな書きが原則となる接続詞
「表外字」は、「常用漢字表」にない漢字のこと、「表外音訓」は同漢字表にない音訓のことです。それらの漢字・音訓を含む場合、その語ないしその部分はかな書きにするのが原則です。この条件で、かな書きが導き出せるのは、次の41の接続詞です。
あるいは かくして かくて さすれば さて さては さりとて さりながら
されば しかし しかして しかしながら しかも しからずんば しからば しかる
に しかれども しこうして すなわち そうして そこで そして それから
それだから それで それでは それでも それどころか それとも それなのに
それなら それに それにしても ために ちなみに ないし もっとも かたがた
ここに さらば ただ
たとえば、表外字を含む「或いは」「其れで」は「あるいは」「それで」となり、表外訓を含む「則ち・即ち・乃ち」は「すなわち」となります。
これらに加えて、漢字表記を持たない接続詞もあり、その場合は、当然かな書きです。以下に該当する6語を示します。
すると だから だけど だって では でも
「すると」は「為ると」と書く慣用がないため、ここに入れてあります。「だけど」は「だ+けど」、「では」は「で+は」というように、いわゆる付属語どうしのくっついたものであるため、極めて漢字表記が行われにくいタイプです。
残る29語に、かな書きと漢字表記で迷う可能性があります。
公用文で漢字表記を採用する語
「新しい「公用文作成の要領」に向けて」には、「仮名書きを基本とするが一部のものは漢字で書く」という項目があり、接続詞については、以下のように記されています。
例 さらに(副詞の「更に」「更なる」は漢字で書く。) しかし しかしながら したがって(動詞の「従う」は漢字で書く。) そして そうして そこで それゆえ ただし ところが ところで また(副詞の「又」は漢字で書く。) 〔漢字を使って書く接続詞〕 及び 又は 並びに 若しくは
※「さらなる」は連体詞(中川注)
接続詞か副詞かにより、「さらに」と「更に」、「また」と「又」というように書き分けるのは、なかなか複雑な決まりです。
上記のうち、漢字で書くことにしている接続詞は、法令などに頻繁に用いる接続詞であり、文字数を節約したり、漢字かな連続を成り立たせたりするために必要とされるようですが、教科書やマスメディアでは、接続詞はかな書きという原則を優先しています。一部、会社ごとの差もあるため、表1にまとめて示します。
| 教科書 | 新聞 | 共同 | 読売 | NHK | |
|---|---|---|---|---|---|
| および | および | 項目なし | および | 及び(接続詞の場合は仮名書きでも) | および |
| また(は) | また(は) | また(は) | また(は) | また(は) | また(は) |
| ならびに | ならびに | 並びに | ならびに | 「漢字で書いてもよい例」に「並びに」があがる | ならびに |
| もしくは | もしくは | 若しくは〔注〕表内訓だが、仮名書きが一般的 | もしくは | もしくは | もしくは |
いずれの立場でも、副詞の「また」をかな書きとするため、副詞も接続詞も「また(は)」と書くことで公用文以外の分野では安定が保てます。「もしくは」の場合、「若しくは」でも文字数が減らないため、かな書きが進みやすいのに対し(新聞やテレビの字幕は、文字数制限がシビアです)、「および」「ならびに」は、「及び」「並びに」とすることにより、1字分の節約になるため、そのメリットが捨てがたいという気持ちが品詞上の原則にまさると『読売』のような掲げ方が生じることとなります。
マスメディアでかな書きに決めている接続詞
「且」「但」「又」は「常用漢字表」にある漢字ですが、新聞・放送では、原則として使わないことに決めています。それゆえ、これらの語を使う場合は「かつ」「ただし」「また」と書くことになります。「また」については、前述したとおりです。
『教科書』でも「かつ」「ただし」と書くことにしていますから、教科書、新聞、放送の3分野では足並みがそろいます。「かつまた」「なおまた」「はたまた」も、「且つ又」「尚又」「将又」ではなく、かな書きが選ばれています。
用言の活用形を含む接続詞
「したがって」は、動詞「従う」から派生した接続詞です。このように、動詞の活用形が助詞を伴うなどして接続詞になったものが「したがって」を入れて計八つあります。形容詞「同じ」に由来する「おなじく」もここで扱います。これらについて、各社の掲載状況を表2に示します。
| 教科書 | 新聞 | 共同 | 読売 | NHK | |
|---|---|---|---|---|---|
| したがって | したがって | 項目なし | 従って | 「漢字で書いてもよい例」に「従って」があがる | ①したがって②従って |
| してみると | 項目なし | 項目なし | 項目なし | 項目なし | 項目なし |
| してみれば | 項目なし | 項目なし | 項目なし | 項目なし | 項目なし |
| ついで | 次いで | 項目なし | 項目なし | 項目なし | 次いで |
| ついては | ついては | ついては | ついては | ついては | 項目なし |
| とはいえ | とはいえ | 項目なし | とはいえ | 項目なし | 項目なし |
| なんとなれば | 項目なし | 項目なし | 項目なし | 項目なし | 項目なし |
| よって | よって | 項目なし | 項目なし | 項目なし | よって |
| おなじく | 項目なし | 項目なし | 項目なし | 項目なし | 同じく |
『新聞』の動詞「よる」の項目には、「因る」は「表内訓だが、仮名書きにする」という注があるので、接続詞の「よって」も、自動的にかな書きになることがわかります。『共同』『読売』も同様です。
『NHK』にない項目を『NHK日本語発音アクセント新辞典』で確認すると、「してみると」「してみれば」「ついては」「とはいえ」「何となれば」となっています。動詞と助詞の組み合わせからできている「してみると」「とはいえ」などは、漢字表記の必要性が薄れるものの、「なに・なん」という名詞を要素として含む「何となれば」の場合、「何か」「何とも」などを漢字表記するのと同じく、「何となれば」が選ばれたということです。
「ついで」に「次いで」の表記が選ばれやすいのは、動詞の「次ぐ」において、どの辞書でも漢字表記が標準とされ、その動詞の意味からの隔たりが小さいためです。
これに対して、「したがって」の場合は、「XがYに従う」という動詞の意味からの隔たりが大きくなるため(「○○に従って」という動詞用法とのつながりを断ち切るためにあえて「したがって」と書くという捉え方もできます)、かな書きを選ぶ立場が生じます。しかし、「従って」により、2文字分の節約が可能であることは、新聞など文字数に神経をとがらす分野においては魅力的にうつります。そのことが統一的な標準表記を決めるうえでのネックとなります。
「おなじく」は、形容詞「同じ」の連用形から来ています。意味の変化がほとんど見られないため、「おなじ」(形容動詞)を「同じ」と、漢字で書くなら、それに合わせて「おなじく」も漢字表記という判断になります。
名詞を含む接続詞
次に名詞を含む八つの接続詞を扱います。表3に一覧として示します。
| 教科書 | 新聞 | 共同 | 読売 | NHK | |
|---|---|---|---|---|---|
| そのうえ | そのうえ | 項目なし | その上 | 項目なし | その上 |
| そのくせ | そのくせ | 項目なし | そのくせ | 項目なし | そのくせ |
| それゆえ | それゆえ | 項目なし | それ故 | 項目なし | それゆえ |
| つぎに | 次に | 項目なし | 項目なし | 項目なし | 次に |
| ときに | ときに | 項目なし | 項目なし | 項目なし | 時に |
| ところが | ところが | ところが | 項目なし | 項目なし | ところが |
| ところで | ところで | ところで(原則ページに載る) | ところで | 項目なし | ところで |
| ゆえに | ゆえに | 項目なし | 故に | 故に | 故に |
名詞を中に含む接続詞は、全体をかな書きするか、名詞部分を漢字表記するか、ゆれの生じやすいグループです。全品詞の中で名詞がもっとも漢字で書かれやすいことに由来する現象です。
『教科書』が漢字表記とする「次に」は、動詞「つぐ」から派生した名詞(日本語学では「動詞連用形名詞」「居体言(きょたいげん)」などと呼ばれます)の「つぎ」に助詞の「に」がついたものです。名詞を「次」と書く慣用が確立しているため、接続詞の「次に」においても、その慣用が保たれます。「次いで」以外は、『教科書』のように、すべてかな書きとするのも一法ですが、「その上」「時に」「故に」に漢字の意味が生きていると見るためか、また、「時に」「故に」に漢字かな交じり文を整える力があると見るためか、マスメディアでは漢字表記が選ばれています。たとえば、「ところが」「ところで」には場所の意味は感じられないため、「所が」「所で」とはしないのに対し、「ときに」には、時間の意味があると見て、「時に」を採用するという違いです。もっとも、「その上」については、語頭ではなく語末に漢字が使われるため、漢字で書くのであれば、その後ろの名詞などとのあいだに読点を使うのが読み手に対する配慮として有効です。
漢語の接続詞
漢語の接続詞は、「いっぽう(一方)」「そく(即)」の二つです。「一方」は、接続詞の用法における表記が上述のどの辞書類にも載っていません。名詞としての用法は、『教科書』『NHK』に「一方」と書くものとして載ります。新聞各社で「一方」を項目として掲げていないのは、「一方」が漢語であり、かつ漢字の意味が生きているため、当然「一方」と書くという暗黙の了解があるからでしょう(ただし、「当用漢字表」の時代であれば、「いっぽう」と書くことも行われました)。ひとまず、現代においては、接続詞のうち、漢字表記が一般的な語の代表例と見なすことができます。
接続詞の「そく」は、前述のいずれの辞書にも載っていません。「個人の幸福即社会の幸福」(『新選国語辞典 第10版』)または「高齢者即弱者とはならない」「生即死」(『明鏡国語辞典 第3版』)のように使います。この使い方は、漢字連続が長くなるため、読みやすさの観点から、類義語の「すなわち」のほうが用いられやすかったり、放送では耳で聞いてわかりやすいことが大切であるため、やはり「そく」ではなく「すなわち」や「つまり」のほうが出やすかったりするということになり、「一方」ほどは、現代語として必要性が高くありません。
まとめ
以上に見てきたように、現代語の表記において、接続詞は、かな書きが原則となりますが、一部、漢字表記が行われるものがあります。漢字表記のない「では」や表外字・表外音訓を用いる「さて(扨)」などが、原則どおりひらがなで書きやすい接続詞であると見るなら、その反対の極が「一方」です。そのあいだに、統一的な標準表記が設けにくい、いくつかのタイプの接続詞が位置しています。
通常、副詞として処理される「他方」に対して、『岩波国語辞典 第8版』のように接続詞用法があると見なせば、漢字表記が選ばれやすい接続詞が一つ増えます。目安としては、「Aだが、他方、B」(読点でつなぐ)というような使い方が主であると見れば副詞、「A。他方、B」(句点でつなぐ)という使い方が「他方」に認められるとすれば接続詞というように辞書などでは処理されるようです。
和語の場合、公用文で漢字表記とする「および」や「もしくは」は、教科書やマスメディアでは、特段、漢字表記が求められないのに対し、漢語の「一方」の場合は、特に分野の区別なく、漢字が選ばれやすいという傾向が見られました。このことを考えると、接続詞の表記は、和語であれば、かな書きが原則、漢語は漢字表記というふうにしたうえで、和語の中にも部分的・例外的に漢字を用いるものがあると考えれば、接続詞の表記の全体像が捉えられます。
参考文献
三省堂編修所編(2022)『新しい国語表記ハンドブック 第9版』三省堂
![]()
中川秀太
文学博士、日本語検定 問題作成委員
専攻は日本語学。文学博士(早稲田大学)。2017年から日本語検定の問題作成委員を務める。
- 最近の研究
- 「現代語における動詞の移り変わりについて」(『青山語文』51、2021年)
- 「国語辞典の語の表記」(『辞書の成り立ち』2021年、朝倉書店)
- 「現代の類義語の中にある歴史」(『早稲田大学日本語学会設立60周年記念論文集 第1冊』2021年、ひつじ書房)
- 「現代日本語のジェネレーションギャップ」(2024年、武蔵野書院)など。
コラム一覧
- 2025.12 (47)「『ドッジボール』か? それとも『ドッチボール』か?」
- 2025.11 (46)「デアル体とダ体の詳細」
- 2025.10 (45)「『孔子』や『孫子』のアクセント」
- 2025.9 (44)「比喩的な『続投』が捨てられない理由」
- 2025.8 (43)「1日のうちに行う動作を表す連用形名詞+晩酌」
- 2025.7 (42)「『かき氷』関連のボキャブラリー」
- 2025.6 (41)「代名詞の表記」
- 2025.5 (40)「連体詞の表記②」
- 2025.4 (39)「連体詞の表記①」
- 2025.3 (38)「語頭のラ行音」
- 2025.2 (37)「接続詞の表記」
- 2025.1 (36)「一語文の用法を持つヒト名詞」
- 2024.12 (35)「朝昼晩のあいさつのことば」
- 2024.11 (34)「接頭辞の『ま』『ど』『せい』」
- 2024.10 (33)「相撲の世界における動詞の特別な使い方」
- 2024.9 (32)「数字の語形と表記」
- 2024.8 (31)「ぼかす副助詞」
- 2024.7 (30)「『甲の乙』という形の単語について」
- 2024.6 (29)「母音が連続するときの発音」
- 2024.5 (28)「『現代仮名遣い』と表音一致」
- 2024.4 (27)「動詞のウ音便について」
- 2024.3 (26)「『かな(仮名)』の語形とアクセントと表記」
- 2024.2 (25)「『わかる』のコミュニケーション文法」
- 2024.1 (24)「『よりか』とは何か」
- 2023.12 (23)「『お』と体の部分」
- 2023.11 (22)「質問という行為について」
- 2023.10 (21)「しこ名の『~川』」
- 2023.9 (20)「『~ていただきたいです』という表現について」
- 2023.8 (19)「今に生きる旧国名の別称」
- 2023.7 (18)「『可決・成立する』は是か非か」
- 2023.6 (17)「語頭に[p]の音を持つ単語のこと」
- 2023.5 (16)「『いる』と『おる』の活用形」
- 2023.4 (15)「『ローマ字のつづり方』は実用的か否か」
- 2023.3 (14)「御しがたいひと言『なるほど』のこと」
- 2023.2 (13)「『~犬』はイヌかケンか」
- 2023.1 (12)「『ありか』『かくれが』『すみか』の表記」
- 2022.12 (11)「みずうみ・ぬま・いけ」
- 2022.11 (10)「『お間違いありませんか(お間違いないですか)』に問題はありませんか」
- 2022.10 (09)「現代の1拍語」
- 2022.9 (08)「動植物名を表す漢字について」
- 2022.8 (07)「現代語における女の人の一人称」
- 2022.7 (06)「『水鳥』の語形とアクセント」
- 2022.6 (05)「動物と敬称②」
- 2022.5 (04)「動物と敬称①」
- 2022.4 (03)「『東方・西方』の語形」
- 2022.3 (02)「『母方・父方』の語形」
- 2022.2 (01)「『失礼します』か『失礼しました』か」