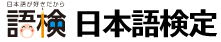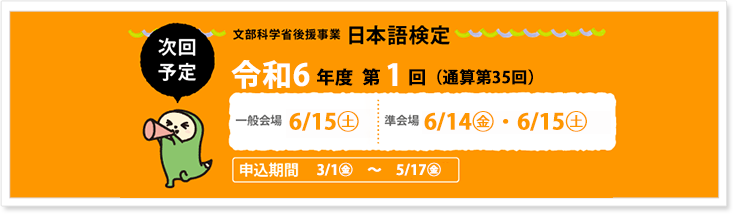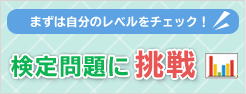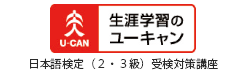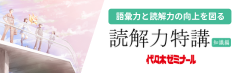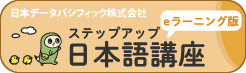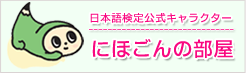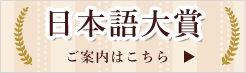以前、中国人留学生から「目上の人に「こんにちは」「こんばんは」を使ってよいかどうか」という質問を受けたことがあります。英語では、good morning、good afternoon、good eveningという、形式的に共通点を持つことばが存在し、相手が目上であっても使えます。中国語も英語と同様だそうです。一方、日本語では、朝の「おはようございます」に対し、「こんにちは」「こんばんは」には「ございます」がつかないため、形式的にアンバランスです。質問を受けたそのときは、その留学生と同じような意識を持つ人が日本語ネイティブの中にもいるものの、大勢としては、ほかに適当な言い方がないため、目上の相手に「こんにちは」「こんばんは」を使うのがやむをえない状況にあると返答した記憶があります。
以下では、朝昼晩のあいさつことばを全体的に見渡します。
朝のあいさつ
朝のあいさつは、友達なら「おはよう」、目上の相手なら「おはようございます」となり、親兄弟や祖父母に「ございます」をつけるかどうかは、微妙なところです。個々の家庭環境によることでしょう。
昼のあいさつ
昼は、ともに住む親兄弟などであれば、あいさつをしません。朝の「おはよう」が済んでいれば、その効果が寝る直前の「おやすみ(なさい)」まで続きます。外出先で子どもが親に偶然に会った場合などは、「お父さん!」などと声をかけ、あいさつことばは使いません。遅く起きてきた相手に対しては、やゆして「おそようございます」が使われることがあります。この「おそようございます」は、まじめな言い方として、晩(夜)のためにとっておいたほうがよかったかもしれないというのが筆者の見方です。その場合、友達などには「おそよう」を使うことになります。もしそれが現実になれば、昼用の丁寧なことばが必要とされます。たとえば「おひるで(ございま)す」(仮の語)のような言い方が候補となりえます。
昼の場合、ウチ(身内)とソト(それ以外、他人)の問題が生じます。家族のほか、友達など親しい相手はウチという扱いになり、「こんにちは」が使えません。「こんにちは」は、目上の相手、初対面の人など、心理的に距離がある相手に使います。それゆえ、友達に何と言えばよいか悩みます。英語ではhello、hi、hiya(Hou are you?の転)などが親しい相手に使えるのと比べて、日本語は不便です。
国語辞典の用例として「やあ、こんにちは」が載ることがありますが、やや古風なことばづかいに見えます。「やあ」でウチに対する呼びかけを行ったうえであれば、友達でも「こんにちは」が使えたということのようですが、現在、このような言い方をする人は減りました。「やあ」や「よう」(「おす」「おっす」「ういっす」「ういーす」とも)という語で呼びかけることも可能ですが、男っぽい、ぞんざい、ぶっきらぼう、といった語感を感じて使わない人と、そのような語感を意識せずに使う人とに分かれます。すなわち、誰もが使えることばではないということです。また、「どうも(どうも)」がいつでもどこでも使われるということが1970年代に盛んに指摘されましたが、現在、人と出会ったときの万能のあいさつことばとはなっていません。
文化庁編(1988)において、野元菊雄氏は、目上の人にあいさつする場合、久しぶりに会った相手なら「ごぶさたいたしてます」でよいが、「昨日今日会ったばかりではね。(笑い)あとはその時々に応じて「お天気つづきで結構でございます」「いいおしめりで……」などなど時候・天候関係のあいさつ言葉を覚えておけばいいでしょう」と述べていました。久しぶりの相手に「ごぶさたしております」「お久しぶりです」などという方法は今でもとれますが、「笑い」以下の内容は、現在は有効ではありません。その日の天候にあいさつことばの選択が左右されるようでは普遍性に欠け、外国人に対する日本語教育にも採用しにくいことでしょう。
晩(夜)のあいさつ
晩(夜)は、ソトの相手には「こんばんは」を使います。丁寧な言い方として、東北などには「おばんです」「おばんでした」(東北では「た」が丁寧さのサインとなる)があります。しかし現在、東北の方言は、重い、かわいくないといった、世間のいわれない批評を受ける傾向にあるため、東北出身の若い世代は、自分たちは「おばんです」とは言わない、それは祖父母世代のことばであると評価します。しかし、あるべき姿は、東北には「おばんです」という、よい言い方があり、これは標準語に不足する部分であるから借用することにして、「おばんです」さらに丁寧な「おばんでございます」(かつては東北以外の東日本で使ったとも)という言い方を使うようにしよう、という発想が現代ないし近未来に生じることです。
「おはよう(ございます)」の拡大使用
上記のように、昼と晩は、あいさつことばに不便なところがあります。そこに生じたのが昼も晩も「おはよう」語彙を使うという現象です。和歌森ほか(1957)で作家の正岡容は、劇界と放送局ではいつでも「おはよう」を使い、その慣用は劇界から出たと推測しています。人々の出勤する時間帯が朝でそろいやすい官庁や一般の企業などと異なるところが両者に共通します。
その後、一般、特に大学生の間に広がり、外山(1990)には、13時過ぎに互いに「おはよう」と言い合う学生の様子が記されます(朝、全員が決まった時間に登校する高校までと異なり、大学では、学生により登校の時間がまちまちであることが放送局などと似る)。「おはよう」であれば、ぶっきらぼうなどの印象は伴いません。午後の授業で生徒・学生が教師に「おはようございます」と言うと、教師から「こんにちは」が返り、それを受けて「こんにちは」に訂正しようとする生徒・学生がいると大学の教員から聞いたことがあります。教師の側としては、自分まで「おはよう」を使うのもためらわれる、または、昼に「おはよう」は不自然だから直させようという意図があって「こんにちは」を使うということでしょうが、ふかん的に見ると、年下の側が「おはようございます」を、年上の側が「こんにちは」を使うというのは、主体の立場による使い分けであると捉えれば、実は合理的なあり方であると見ることも可能です。現実には、「おはよう」と「こんにちは」の語、語形の違いに意識が向いてしまうため、一般化はしないでしょうが。
「おつかれ(さまです)」の拡大使用
仕事などの疲れをねぎらうのが本来の「おつかれ(さまです)」の使い方ですが、現代では、その日に外出先で知り合いと会った際のあいさつことばとして使うことが増えています(目上の相手に使えるか否かは、ここでは扱わない)。
「おつかれ」語彙がその使用範囲を広げた大きな要因は、「こんにちは」「こんばんは」が友達などウチの相手に使えないことにあります。代わりに「おつかれ」を使い、目上の相手には「おつかれさま(です)」を使えば、丁寧さのレベルを調節することができます。別れ際にも使うようにすれば、「さようなら」「じゃあ(ね)」「失礼します」などの使い分けに悩むこともありません。
ただし朝の場合、「おはよう」があるのに「おつかれ」を使う意義が特には感じられず、「おはよう」と「おつかれ」をてんびんにかけてみると、睡眠により疲れがとれたはずの朝という状況と、「おつかれ」本来の「疲労」という意味とがバッティング(衝突)し、「おつかれ」が使いにくいとする人が少なくありません。そのようなことを意識せず、ことばの単純化を志向する人は、朝でも「おつかれ」を使うようです。
「ヤッホー」の拡大使用
大学生(女性)どうしが「ヤッホー」をあいさつに使っているのを初めて筆者が耳にしたのは2019年です。その年に教えていた学生に尋ねたところ、親しい友達と会ったときに(ふざけて)使うとのことでした。最近では、ホンダのVEZELという車のCMの中に、遅い時間に車の中から知人に電話をかけた女性が「ヤッホー」「ひさしぶりー」と話し始める場面があります。その2人がドライブに出かける際の映像から判断すると、相手も同年代の女性のようです。「ヤッホー」を使っているのは、1994年生まれの女優です。昼でも晩(夜)でも「ヤッホー」を使う可能性があることを示す用例であり、ふだん「ヤッホー」を使うという学生に聞いてみると、遅い時間にも使うとの返事が返ってきました。もっとも、夕暮れ時に「ヤッホー」と母親が父親と息子に公園で声をかける場面が漫画『六三四の剣』の第4巻(1982年)にあることなどからすると、かなり以前まであいさつ相当の「ヤッホー」の使用は遡れるようでもあります。用例の推移の調査を要します。
では、どうして「ヤッホー」が広まったのでしょうか。「おつかれ」が、人によっては「疲れていないよ」という反発・反応が生じうる、いわば陰を持った語であるのに対して、山で、知らない人、顔の見えない人に向かっても発しうる「ヤッホー」は、徹底して陽性の語であるという特徴を持ちます。「山じゃないのに?」という反発・反応は、「疲れていないよ」に込められる抵抗感よりも軽い印象です。
筆者が聞いた使用例は、すべて女性による「ヤッホー」でしたが、これが筆者の観察不足によるのか、真に男女差を示すものなのかについては、詳しい調査が必要です。個人的には、本来の「ヤッホー」が男女ともに使える語であることが転義の場合にも当てはまるとよいと考えます。「ヤッホー」に関する課題は、①男性が使うかどうか(「おす」などがあるため、相対的に女性よりも「ヤッホー」の必要性が男性は低い)、②使用者の世代的な範囲、③別れの場でも使われる(兆候がある)かどうか、④現在の20代、30代が50年後に使うかどうか、などです。特に④は、50年後の研究者や学生のための研究課題として最適です。なお、便宜上「50年後」としましたが、もちろんほかの「~年後」でもかまいません注1。
「ごきげんよう」のこと
日本語学者の斎賀秀夫氏は、斎賀ほか(1968)において、学習院のほか聖心女子大学でも「ごきげんよう」を使っていると述べていました(「ミッション系の学校で伸びてきていますね」とも)。東京女子大学の学生から2024年に聞いた話では、跡見学園女子大学の学校説明会に行った際に、学校の人が「ごきげんよう」を使っていたとのことです。また、学習院の女子部出身の筆者の知人によれば、学習院女子大学の守衛さんは、人が門の前を通るときに「ごきげんよう」と声をかけているそうです。学校という場所を離れても、それらの学校の人たちが「ごきげんよう」を使うかどうかは調べを要しますが注2、ひとまず一部の学校では、今でも「ごきげんよう」が使われることがうかがえます。
小説家の藤島泰輔氏(1933~1997)は、学習院中等科に入った際に「朝登校の際、駅で会っても「ごきげんよう」、夕刻別れるときも「ごきげんよう」」であったことに驚いたと藤島(1987)に書き残していました。つまり、「ごきげんよう」は、丁寧なあいさつことばであり、出会いにも別れにも使える便利なことばと言えますが、現代日本語において、「ごきげんよう」は、標準的なあいさつことばの位置を得ていません(別れ専用の丁寧なことばは「さよ(う)なら」、くだけた言い方は、主に戦前は「あばよ」、戦後は「バイバイ」。ほかに「じゃあな」「じゃあね」とも)。
戦後の民主化に伴い、敬語などには簡略化の方向が求められ、「上流社会」から丁寧なことばを一般に取り入れるという方向が試みられることはありませんでした。しかし身分制度のない現代社会においても、丁寧か非丁寧かを区別できることばが必要とされるからこそ、たとえば「おはよう」と「おはようございます」がともに使われることとなります。そう考えるなら、相手や場面によって、「ごきげんよう」と「ヤッホー」を使い分けるという道も理論的にはありうることであり、「ごきげんよう」を古くさい(過去の遺物)と見なすのはもったいないように感じます。
おわりに
あいさつ一つをとっても、いまだ標準語は確立されてはいないと筆者は感じます。標準語は完全なものであり、学校教育を受ければ自然に身につくというようなものではありません。まだまだ整えていかなければならない部分がいくらでも残されています。
注1 心が弾むときに「ヤッホー」と叫ぶ意味・用法がありますが、一過性ないし遊びことば、漫画・アニメなどに使われることば、いわゆるパリピの使うことばとして捉えられているのか、その使い方を載せる辞書は『現代国語例解辞典 第5版』『三省堂現代新国語辞典 第7版』など比較的わずかです。用例として、たとえば1982年から1983年にかけて放送された『超時空要塞マクロス』というアニメ番組の第13話「ブルー・ウインド」には、ローラースケートで遊ぶ若い女性が「ヤッホー」と笑顔で叫ぶ場面があり、第34話「プライベート・タイム」には、主人公とのデートを楽しみにして「ヤッホー」と女性の登場人物が発話する場面があります(アクセントが辞書に載るヤ\ッホーではなく、ヤッホ\ーとなるおまけつき)。また、2024年のAmazon AudibleのCMには、うきうきとした口調で「ヤッホー」と発せられる場面があります。
注2 近衛、林(1997)で、三笠宮崇仁親王の第1女子の近衛甯子氏(1944~)は、「こんにちは」にはなじめず、住んでいるマンションで近所の人たちと会った際には「ごきげんよう」と「言ってしまう」が、近所の人はみな「こんにちは」であると述べています。「ごきげんよう」の置かれた状況が察せられます。
参考文献
近衛甯子、林望(1997)「対談 皇族方はどんな言葉でお話しに?」『東京人』12-3
斎賀秀夫、多田侑史、鶴見良行、中根千枝、編集部(1968)「あいさつと社会生活」『言語生活』196
外山滋比古(1990)『山茶花はなぜサザンカか』朝日新聞社
野元菊雄、秋永一枝、石綿敏雄、佐藤亮一、柳下昭夫(1988)「〈座談会〉言葉の変化をめぐって」『言葉の変化 「ことば」シリーズ28』文化庁
藤島泰輔(1987)『東京山の手の人々』サンケイ出版
和歌森太郎、吉田澄夫、正岡容(1957)「暮らしの変遷とことば」『言語生活』71
![]()
中川秀太
文学博士、日本語検定 問題作成委員
専攻は日本語学。文学博士(早稲田大学)。2017年から日本語検定の問題作成委員を務める。
- 最近の研究
- 「現代語における動詞の移り変わりについて」(『青山語文』51、2021年)
- 「国語辞典の語の表記」(『辞書の成り立ち』2021年、朝倉書店)
- 「現代の類義語の中にある歴史」(『早稲田大学日本語学会設立60周年記念論文集 第1冊』2021年、ひつじ書房)
- 「現代日本語のジェネレーションギャップ」(2024年、武蔵野書院)など。
コラム一覧
- 2025.12 (47)「『ドッジボール』か? それとも『ドッチボール』か?」
- 2025.11 (46)「デアル体とダ体の詳細」
- 2025.10 (45)「『孔子』や『孫子』のアクセント」
- 2025.9 (44)「比喩的な『続投』が捨てられない理由」
- 2025.8 (43)「1日のうちに行う動作を表す連用形名詞+晩酌」
- 2025.7 (42)「『かき氷』関連のボキャブラリー」
- 2025.6 (41)「代名詞の表記」
- 2025.5 (40)「連体詞の表記②」
- 2025.4 (39)「連体詞の表記①」
- 2025.3 (38)「語頭のラ行音」
- 2025.2 (37)「接続詞の表記」
- 2025.1 (36)「一語文の用法を持つヒト名詞」
- 2024.12 (35)「朝昼晩のあいさつのことば」
- 2024.11 (34)「接頭辞の『ま』『ど』『せい』」
- 2024.10 (33)「相撲の世界における動詞の特別な使い方」
- 2024.9 (32)「数字の語形と表記」
- 2024.8 (31)「ぼかす副助詞」
- 2024.7 (30)「『甲の乙』という形の単語について」
- 2024.6 (29)「母音が連続するときの発音」
- 2024.5 (28)「『現代仮名遣い』と表音一致」
- 2024.4 (27)「動詞のウ音便について」
- 2024.3 (26)「『かな(仮名)』の語形とアクセントと表記」
- 2024.2 (25)「『わかる』のコミュニケーション文法」
- 2024.1 (24)「『よりか』とは何か」
- 2023.12 (23)「『お』と体の部分」
- 2023.11 (22)「質問という行為について」
- 2023.10 (21)「しこ名の『~川』」
- 2023.9 (20)「『~ていただきたいです』という表現について」
- 2023.8 (19)「今に生きる旧国名の別称」
- 2023.7 (18)「『可決・成立する』は是か非か」
- 2023.6 (17)「語頭に[p]の音を持つ単語のこと」
- 2023.5 (16)「『いる』と『おる』の活用形」
- 2023.4 (15)「『ローマ字のつづり方』は実用的か否か」
- 2023.3 (14)「御しがたいひと言『なるほど』のこと」
- 2023.2 (13)「『~犬』はイヌかケンか」
- 2023.1 (12)「『ありか』『かくれが』『すみか』の表記」
- 2022.12 (11)「みずうみ・ぬま・いけ」
- 2022.11 (10)「『お間違いありませんか(お間違いないですか)』に問題はありませんか」
- 2022.10 (09)「現代の1拍語」
- 2022.9 (08)「動植物名を表す漢字について」
- 2022.8 (07)「現代語における女の人の一人称」
- 2022.7 (06)「『水鳥』の語形とアクセント」
- 2022.6 (05)「動物と敬称②」
- 2022.5 (04)「動物と敬称①」
- 2022.4 (03)「『東方・西方』の語形」
- 2022.3 (02)「『母方・父方』の語形」
- 2022.2 (01)「『失礼します』か『失礼しました』か」