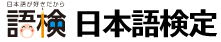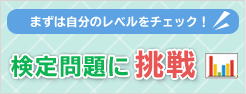東京では「真ん真ん中」を使うところに、関西から「ど真ん中」が入ってきて、現在はそちらが一般化したというふうに語られることがよくあります。東京が関西のことばに弱い(魅力を感じる)という傾向の一例であり、濁音の「ど」に対して、鼻音(マ行やナ行の子音のように、口からだけではなく鼻からも息が抜ける音のことです)の「真ん」よりも強調するための要素としてふさわしいという感覚を持ったのかもしれません。以下では、①「ど」が入り込んだ領域の確認、②「真」が「真ん」あるいは「真っ」になる条件、③「真」が新しく用いられる条件、について検討します。
「ど」の流通
まず「真ん真ん中→ど真ん中」について、古いところでは1949年の記録として、秋山(1953、p.121)に「ドまんなか。などというキタない言葉が東京語でないことを、もう今のアナウンサーは問題としていない」という指摘があります。白黒テレビ時代の大相撲の放送番組を聞くと、アナウンサーが「土俵の真ん真ん中」と言っていることがありました(筆者は栃錦(1925~1990)の取組を伝えるアナウンサーの発話の中で耳にしました)。現在、相撲に限れば、アナウンサーが「ど真ん中」と言うことは目立たず、「一方の白鵬、まだ土俵の真ん中、ゆっくりと腰を上げました」(杉山邦博・小林照幸『土俵の真実』2010、文芸春秋)のように「真ん中」を使うか、「(土俵の)中央」を使うかしているようです。
ほかの「ど~」の言い方についても、日本語学者の見坊豪紀(1914~1992)によって、「どけち」「どすけべ」などは、河内弁として作家の今東光が世に広めたと指摘されています(入江ほか(1968))。「けち」「すけべ」などには、「ま」ないし「まん」がつきません。東京では「けち」「すけべ」を強調する言い方がなかったということであり、そこに「ど」が新たに持ち込まれたという関係になります。また、「ど」は話しことばで使う、くだけた(俗な)言い方という語感があるため、「純粋」「正確」といった意味の「真心」「真水」「真四角」などの代わりに「ど」が使われるということはありません。これらは、科学的な事柄を表すため、俗な性質を持つ「ど」とは相性が悪いということです。
「まん」の使い道
「真ん」は、「真」に「ん」が加わったものです。いつでも「真ん」になるわけではなく、語例は「真ん中」「真ん丸い」「真ん前」などに限られます。これらは、naka、marui、maeというように、「真」の後ろに鼻音の子音がつき、母音が[a]であるという特徴を持ちます。鼻音の条件を満たしていても、「真南」「真向かい」などは、母音が[a]ではないため、「真ん」になりません。また、「真夏」は二つの条件を満たしていても、「まんなつ」とは言いません。「中」「丸い」「前」のように、視覚的に確認できる空間的な事柄について、それを強めて「真ん」と表現するのに対して、「夏」は時間的な概念であり、視覚的に確認できる事柄ではないからでしょう。
「まっ」の使い道
それから「真っ先」のように「真」に促音を加えて強めることもあります。語例には「真っ黒」「真っ白」「真っ最中」「真っただ中」「真っ正直」「真っ裸」「真っ昼間」などがあり、『デジタル大辞泉 アプリ版』によれば「真っ」は「ま(真)が摩擦音([s][f]などの音)、破裂音([p][t][k]などの音)を語頭にもつ語に続くときの形」とのことです。摩擦音と破裂音は、ごく簡単に区別するなら、前者は口を閉じることなく発音する子音であり、後者は口を閉じたのちに出す子音のことです。比較的新しいものとして、「真っピンク」という言い方が行われることがありますが、これは[p]が後ろに来る語の例となります。
「ま」と「正(せい)」
「真」「真ん」「真っ」のうち、「真ん」には新しい語が生まれる可能性はほとんどなさそうですが、「真っ」は「真っ白」「真っ黒」などと同様の言い方が別に必要となった際に用いられる可能性があります。では「真」は、どうでしょうか。このことを考えるには、「ど」ではなく「正」との比較が必要となります。従来、標準的な言い方として「正~」の表現があるところに「真~」が用いられる場合があるからです。たとえば「正反対」のことを「真逆」とする言い方であり、野口(2004、p.69)に「最近は「正反対」のことを「真逆」と言うようになった」との指摘があります。「真反対」という言い方もあります。
組織の個性を考えていくときには、私たちはまず社員がその企業のことをどう思っているかを知るために、社内調査をやります。そのうえで、社会がもっているその企業に対する印象も調査するわけですが、この2つが一致することはまずないといっていいですね。それどころか、真反対の印象になっていることも少なくない。
(東京大学教養学部、博報堂ブランドデザイン(2014)『個性はこの世界に本当に必要なものなのか』KADOKAWA)北の富士は自分と真反対のタイプとして、北勝海となる保志の姿をながめたのではなかろうか。
(村松友視(2019)『北の富士流』文芸春秋) 新しい辞書の中には、「真逆」を俗語としなくなったものもあり、マスメディアにも定着した語であると見る向きもありますが、そう見なすことに問題はないでしょうか。和語と漢語で二字の混種語を構成することに正当の組み合わせではないという感覚が生じることに加え(その点が「真正直」「真一文字」など「真」が接頭辞として機能し、漢語と結合して大きな語を作る場合と異なるところです)、「真」をつけることの意義がはっきりしないこと、単に「逆」(または「反対」)と言ったのでは済まないレベルの事柄を言おうとしているのか、ただことばを「盛る」ために使っているのか、といった使用動機(論理的動機か情緒的動機か)の点で、標準的なことばであるとする根拠が見いだせません。単に人々が使っているからというだけでは理由になりません。どうして俗語としてスタートした語を俗語ではなくなったとしたくなるのでしょう。
「真逆」を使う人の感覚としては、俗語としてスタートしたというつもりはなく、「逆」という語に「真」をつけただけというのが正直なところのように見えます。「逆」自体は、俗語ではありません。しかし、「逆」には、「反対」の意味が感じられない場面で過剰に用いられるようになったという背景があります。そのことを高橋(1984、pp.312-313)を頼りに確認します。
「逆に」という言葉が気になるのである。とりわけ最近耳につくということだけでなく、物事を逆説的に、もしくは、相対的に見ているわけでもないのに使う人が多いからだ。それは新聞や雑誌の活字の中でも使われ出している。あるスポーツ新聞紙を読んでいて苦々しく思ったことがある。「田淵選手は年齢からくる衰えを感じて引退を表明した。逆に、CM界から注目を浴び始めた」(中略)何が、逆に、なのか分らない。文章の中では、野球選手と広告業界の因縁といったものには一切触れておらず、逆に、という言葉を無造作に介在させて、いきなりCM界などといった言葉が出てくるのである。それでなんとなく納得させてしまうような強引さがある。
「反対」の意味がなくとも、「逆に」を使うことにより、何か新しい視点を提示しているかのように受け手に錯覚させようという意図が感じられれば、受け手の側は不快に思います。このような真に「反対」を意味することのない「逆(に)」の使い方が広まれば、本来の逆の意味を保っているということを表すために「真」によるサポートが必要となり、「真逆」がはやることとなります。もし、「正反対」と違う意味・語感を表すために「真逆」を使うという主張をしたければ、「正反対」と「真逆」の両方を使う人たちに対する大規模な意識調査をする必要があります。「真逆」のみを自身の語彙の中に持つ人の感覚のみを追い求めても、わかることは「真逆」を使う理由だけであり、「正反対」を使わない意味・語感の面での理由は明らかにならないからです。「正反対」は堅苦しい感じがするから自分には使いにくい、というのは、意味・語感の話ではなく、その人の理解語彙(意味がわかる語彙)・使用語彙(使いこなせる語彙)の話に属します。
おわりに
「真ん真ん中」は、すでに廃れたと見る人も多いことでしょう。しかしながら完全に消えたわけではありません。「そうだ。京都行こう。」というJR東海のキャンペーンの2016年の広告文には、「世界でもっとも人気の町のその「まん真ん中にある春」なんですから。」という一文が用いられていました。写真には、京都御所と桜が写っています。ここには「ど真ん中」ではなく「真ん真ん中」を用いる価値が「真ん」に感じられないでしょうか。「ど」は1拍、「真ん」は2拍ということから来る語調のよさの違い、さらに、manmannakaという音の連なりが持つ柔らかさ、それが京都御所と桜の写る写真と調和するということです。日常的には、あまり用いられなくなった「真ん真ん中」が、特別な用途のために命脈を保っている、そのようなさまをJR東海の広告が示してくれました。「いま、ふたたびの奈良へ。」をもじり、「いま、ふたたびの真ん真ん中。」と、この文章を結びます。
参考文献
秋山安三郎(1953)『東京えちけっと』創元社
入江徳郎、大石初太郎、見坊豪紀、曽野綾子(1968)「気になることば」『言語生活』204
高橋三千綱(1984)「「逆に」と「ウッソォ」」『群像』39-12
野口恵子(2004)『かなり気がかりな日本語』集英社
![]()
中川秀太
文学博士、日本語検定 問題作成委員
専攻は日本語学。文学博士(早稲田大学)。2017年から日本語検定の問題作成委員を務める。
- 最近の研究
- 「現代語における動詞の移り変わりについて」(『青山語文』51、2021年)
- 「国語辞典の語の表記」(『辞書の成り立ち』2021年、朝倉書店)
- 「現代の類義語の中にある歴史」(『早稲田大学日本語学会設立60周年記念論文集 第1冊』2021年、ひつじ書房)
- 「現代日本語のジェネレーションギャップ」(2024年、武蔵野書院)など。
コラム一覧
- 2025.12 (47)「『ドッジボール』か? それとも『ドッチボール』か?」
- 2025.11 (46)「デアル体とダ体の詳細」
- 2025.10 (45)「『孔子』や『孫子』のアクセント」
- 2025.9 (44)「比喩的な『続投』が捨てられない理由」
- 2025.8 (43)「1日のうちに行う動作を表す連用形名詞+晩酌」
- 2025.7 (42)「『かき氷』関連のボキャブラリー」
- 2025.6 (41)「代名詞の表記」
- 2025.5 (40)「連体詞の表記②」
- 2025.4 (39)「連体詞の表記①」
- 2025.3 (38)「語頭のラ行音」
- 2025.2 (37)「接続詞の表記」
- 2025.1 (36)「一語文の用法を持つヒト名詞」
- 2024.12 (35)「朝昼晩のあいさつのことば」
- 2024.11 (34)「接頭辞の『ま』『ど』『せい』」
- 2024.10 (33)「相撲の世界における動詞の特別な使い方」
- 2024.9 (32)「数字の語形と表記」
- 2024.8 (31)「ぼかす副助詞」
- 2024.7 (30)「『甲の乙』という形の単語について」
- 2024.6 (29)「母音が連続するときの発音」
- 2024.5 (28)「『現代仮名遣い』と表音一致」
- 2024.4 (27)「動詞のウ音便について」
- 2024.3 (26)「『かな(仮名)』の語形とアクセントと表記」
- 2024.2 (25)「『わかる』のコミュニケーション文法」
- 2024.1 (24)「『よりか』とは何か」
- 2023.12 (23)「『お』と体の部分」
- 2023.11 (22)「質問という行為について」
- 2023.10 (21)「しこ名の『~川』」
- 2023.9 (20)「『~ていただきたいです』という表現について」
- 2023.8 (19)「今に生きる旧国名の別称」
- 2023.7 (18)「『可決・成立する』は是か非か」
- 2023.6 (17)「語頭に[p]の音を持つ単語のこと」
- 2023.5 (16)「『いる』と『おる』の活用形」
- 2023.4 (15)「『ローマ字のつづり方』は実用的か否か」
- 2023.3 (14)「御しがたいひと言『なるほど』のこと」
- 2023.2 (13)「『~犬』はイヌかケンか」
- 2023.1 (12)「『ありか』『かくれが』『すみか』の表記」
- 2022.12 (11)「みずうみ・ぬま・いけ」
- 2022.11 (10)「『お間違いありませんか(お間違いないですか)』に問題はありませんか」
- 2022.10 (09)「現代の1拍語」
- 2022.9 (08)「動植物名を表す漢字について」
- 2022.8 (07)「現代語における女の人の一人称」
- 2022.7 (06)「『水鳥』の語形とアクセント」
- 2022.6 (05)「動物と敬称②」
- 2022.5 (04)「動物と敬称①」
- 2022.4 (03)「『東方・西方』の語形」
- 2022.3 (02)「『母方・父方』の語形」
- 2022.2 (01)「『失礼します』か『失礼しました』か」