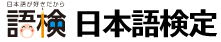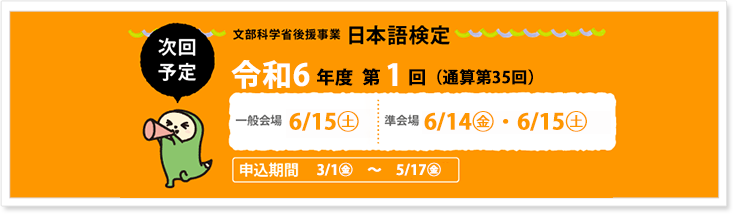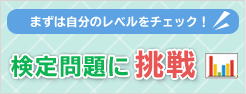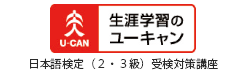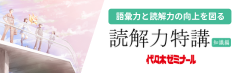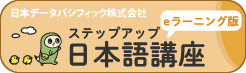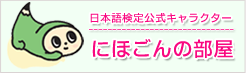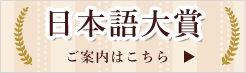固有の日本語つまり和語には、ラ行の音(おと)で始まる単語がほとんどなく、「礼」や「レモン」の「レ」は、漢語(中国語由来のことば)・外来語によるものだとされています。奈良時代などの昔の人が中国語を学んだ結果、「礼」や「路傍」などラ行音で始まる漢語が日本語の中で使われるようになります。「令和」の元号は、日本人にとって、必ずしも発音しやすいものではないのではないかといった心配が生じるのも、本来の日本語にラ行で始まる語が少ないことから来ています。
以上が言語学的な事実です。それに対し、ここでは、なるべく多くのラ行音で始まる語をとりあげて、現代人の感覚としては、和語、漢語、外来語といった語種の区別が難しいものがあること、それはどういう理由によるものか、といったことを検討します。語種という用語は、小学校の国語の教科書に出てきますが、大学受験までの間にテストで問われることがあまりないためか、ふだん、語ごとの語種を意識しているという人は少ないのが実情です。もっとも、外来語については、「ライト」「ロック」など、カタカナで書くことばというふうに、表記を手がかりにして判断できる場合もあります。「レモン」の場合は「檸檬」という漢字表記がある(あった)ために、外来語か漢語か迷うという人がいます。同じ外来語であるにしても、「ライト」と「レモン」のように、語種の判別がしやすいものとしにくいものとの区別を施しておくというのがここでの狙いです。
ラ行音で始まる和語
「男ら」などというときの「ら」は、接尾辞(接尾語)として辞書に載ります。文頭には立たない接尾辞や助詞・助動詞のたぐいは、ここでいう語頭のラ行音からは外します。
NHKの『NHK日本語発音アクセント新辞典』(以下『NHK』)のラ行音の語(約3000語)をチェックした結果をもとにすると、和語は三つあります。「るつぼ」「るまた」「ろは」です。語種情報を載せる『新選国語辞典 第10版』(以下『新選』)、『新潮現代国語辞典 第2版』(以下『新潮』)でこれらは和語として扱われています。『新潮』によれば、「るまた」は「「殺」「段」「殿」などの「殳」が筆写体で「ル」と「又」とを合せたような字形なのでいう」とあり、「ル」は、かな文字の「ル」のことであるとわかります。したがって、文字としての「ル」と「又」に言及しようとして、たまたま語頭にラ行音が来たことばとして解釈できます。「ろは」のほうも、「「只(ただ)の字を「ロ」と「ハ」の二字に分けて読んだ語」(『新潮』)であるため、文字を分解したことにより、意図せず生じたラ行音ということになります。
これらに対し、「るつぼ」は、その語源がはっきりせず、「鋳る壺」または「炉壺」から来たものと推測されています。前者なら活用語尾の「る」が期せずして語頭に来た和語という扱いとなり、後者なら「る」の部分は漢語という扱いとなります。以上の三つを例外とすれば、残りの語は、漢語か外来語です。なお、『NHK』以外からであれば、「るんるん」「れろれろ」といった和語があげられます。これらは俗語またはオノマトペという特徴を持ちます。
外来語の場合
漢語についてふれる前に、判別の簡単なものが多そうな外来語を見ます。『NHK』のラ行で始まる語のうち、約600語が外来語です。たとえば「ラッキー」「リップ」「ルッコラ」「レース」「ロード」などがあります。これらについては、語種についての知識がなくとも、「もともとの日本語ではない、つまり外来語」というような判断が容易に行えます。漢字を使わず、カタカナで表記するということが大きな判断基準です。そうすると、漢字が当て字として使われることのある外来語については、漢字の存在が判断を惑わせる可能性があります。「レモン」が「檸檬」と書かれることにより、漢語ないし非外来語(和語・漢語を合わせたものとして使います)として意識されることがあるのがその例です。地名の「ラオス」から来ている「ラウ・ラオ」(タバコの道具)も「羅宇」の漢字で書かれることにより、非外来語と意識されることがあります。もっとも、現在では、単語そのものが身近な存在ではなくなりました。1998年の『昭和恋々』(山本夏彦、久世光彦)という本には、「《羅宇屋》も《吐月峰》も、今は死語である。死語について喋っていると、横町のご隠居になったみたいで、嫌になる」とのくだりがあります。「吐月峰(とげっぽう)」は、タバコの吸い殻を入れる竹の筒、つまり「灰吹き」のことです。
カタカナが原則の語がひらがなで書かれるようになると、外来語ではなく、和語ではないかというように意識されることがあります。中国語由来の「ラーメン」が「らーめん」「らあめん」などとかな書きされ、日本の独特の食文化ということで和語と見なされるのがその例です。
発音や表記ではなく、外国にはない日本独自の物事という観点から、ある語を非外来語と考える人もいます。たとえば「ランドセル」について、海外では、日本の子どもが使うようなランドセルは見かけないから、「ランドセル」ということばそのものも非外来語であろうというようにです。歴史的には、「ランドセル」は、オランダ語で「背嚢(はいのう)」の意のransel(ランセル・ランゼル)がなまってできた語形であり、軍人が使うカバンを指すことばでした。明治時代になり、学習院の子どもたちに使用されるようになったのが、日本的な「ランドセル」の始まりとされます。
漢語の場合
『NHK』のラ行で始まる語のうち、約2000語が漢語です。「来店」や「乱雑」など、個々の漢字が音読みであると判断できれば、全体としても音+音の漢語であるという答えが容易に出せるはずです。ただし、何が音読みで何が訓読みなのか区別できないという人の場合、語種の区別も困難であり、「漢字があるから外来語ではなく非外来語」というふうに捉えているようです。
ここでは、音読み・訓読みの区別、およびその知識を利用した語種の区別が比較的に容易にできる人であっても、何らかの理由で判別しにくいという事例について考えます。
動植物は、カナカナで書かれることが多いから外来語に見える
たとえば「らくだ」は、「駱駝」の表記を持つ漢語ですが、「駱駝」が「常用漢字表」(2010)にない漢字を使っていること、動植物はカタカナで書く一般的傾向があること、といった理由により、実際に見かける書き方としては「ラクダ」が多いという結果が生じます。それゆえ、これは「ライオン」や「ラマ」と同じく外来語であろうと判断されやすくなります。同じことが「ラバ」「ロバ」にも言えます。「騾馬」「驢馬」と書く漢語であると即座に判断する人は、語種に詳しい人に限られます。「ば(馬)」が音読みであると判断できても、「騾」と「驢」が何を指すのかまではわからない、それゆえ全体の語種は「不明」という答えになる人が多いのが実際のところでしょう。
植物では「りんご(林檎)」「れいし(茘枝)」「れんこん(蓮根)」などがラ行音で始まる漢語です。
漢字単独の場合と異なる発音を持ち、かな書きの多い熟語は、漢語に見えない
「落下」のように、単独の発音「らく」から変化している語であっても、それが漢字で書かれていれば、「落着」「落第」と同じグループの語であろうという類推が働きます。一方、「らっきょう(辣韮)」のように、「辣」の漢字の音が「らつ→らっ」と変化し、かな書きすることの多い語になると、発音と漢字を手がかりとした判断が行いにくく、和語じゃないかという迷いが出てきます。話しことばとして「らっきょ」という短い形が使われるところも、「漢語は、漢字で書く正式・公的なことば」という一般的な印象からずれるため、漢語らしくないことばに見えます。「歴」の「れき」が変化した「れっき(とした)」も、かな書きにより「歴」からは距離ができ、和語・漢語の区別がしにくくなります。
オノマトペ風の語は、和語に見える
「らんらんと輝く目」の「らんらん」や「ろくろく勉強もせずに」の「ろくろく」といった語は、漢字で書けば「爛々」「碌々」ですが、副詞にはひらがなで書かれるものが多いこともあり、これらもかな書きで問題がまったくありません(「常用漢字表」にない漢字を使っているというのも、かな書きが選ばれる理由です)。音の繰り返しがあるところは、「きらきらと輝く」の「きらきら」や「こつこつ勉強する」の「こつこつ」と似ています。これらは和語のオノマトペであり、それと同じであると捉えるならば、「らんらん」や「ろくろく」も、その人の頭の中では和語扱いとなります。
西洋風の物事を表す語は、外来語に見える
楽器の「らっぱ(喇叭)」は、『新選』『新潮』では漢語として扱われています。現実には、「ラッパ」と書かれることも多く、「トランペット」や「チェロ」など西洋音楽の楽器に外来語が多いため、それと同じで外来語と感じる人が少なくありません。ただし、「語源未詳。梵ravaから、オランダroeperから、あるいは、中国語「喇叭」からか、など諸説がある」(『大辞林 第4版』)語であり、明らかに漢語であるにもかかわらず外来語として捉えられやすい語の例としてはふさわしくありません。
よりよい例としては「れんが」があります。漢字で書けば「煉瓦」となる漢語です。この語が「れんが」さらに「レンガはかつて青く彩釉されていた」(山崎秀司『図説 ペルシア』1998年、河出書房新社)のようにカタカナで書かれた場合、外来語という感じが出てきます。明治以降の近代建築において、レンガの果たした役割が大きいことなどから、「れんが」という語そのものが西洋由来であると考えられている場合もあります。2024年6月、7月に東京・山梨の大学生150人から得た回答では、約9割が外来語であると思っていたとしています(すでに語種についての説明をしてある学生が対象です)。
話しことばで使う日常語は、漢語か和語か判断に悩む
「ろうそくの火」の「ろうそく」や「ろれつが回らない」の「ろれつ」は、漢字で書けば「蝋燭」「呂律」となる漢語ですが、文章で使う硬い印象のことばではなく、会話の中で使う、日常的なことばです。それゆえ自信をもって漢語とすることがためらわれ、和語に見えるという人が出てきます。なお、「ローソク」という表記も見られ、外来語として意識する人の存在もうかがえますが、ここでは、その指摘にとどめます。
「りす」は、日本の動物だから和語だと思う
動物の「りす」は、「りっす」または「りっそ」の音が変化して生じたものだとされます。漢字で書けば「栗鼠」となる漢語です(「栗」単独の音読みは「りつ」)。しかし漢語に見えないという人が少なくありません。前述の150人に対する調査では、和語と答える人が75人、漢語が14人、外来語が61人という結果でした。外来語と見る人の場合、カタカナ表記が多いことが主な判断材料となっています。
他方、かな書きされやすいこと、カタカナの「リス」が出やすいこと、「パンダ」や「ぞう(象)」と異なり、外国・外来の動物という話を聞かないこと、などが和語と見なす要因として働きます。加えて、「いぬ」や「ねこ」と同じく、それ以上に分解できない語つまり単純語として「りす」が把握されていることも、この語を和語と感じる人の多い理由です。「りす」は、「り」と「す」からできているとは考えないということです。そして、直感的に「欄外」「流動」など漢語であり、漢字2字で書かれるものには、はつ音(「ん」の音)や長音といった、いわゆる特殊拍が含まれている場合が多いのに対して、「りす」には、「普通の音」しか使われていないから漢語らしくない、それゆえ和語ではないか、「栗鼠」は当て字表記ではないかというところまで考えが進みます。
まとめ
ことばそのものの話としては、「ラーメン」や「りす」を和語とする解釈は誤りに属します。しかしそれとは別に、以上に見てきたように、人々の意識としては、何らかの理由で漢語や外来語を自分に近しい存在の和語として捉えていたり、あるいは漢語を舶来の外来語として捉えていたりするという場合もあります。そのような主観的な捉え方も、ことばにまつわる貴重な情報として記録に値すると筆者は考えます。
参考文献
大野晋(2014)『大野晋の日本語相談』河出書房新社
![]()
中川秀太
文学博士、日本語検定 問題作成委員
専攻は日本語学。文学博士(早稲田大学)。2017年から日本語検定の問題作成委員を務める。
- 最近の研究
- 「現代語における動詞の移り変わりについて」(『青山語文』51、2021年)
- 「国語辞典の語の表記」(『辞書の成り立ち』2021年、朝倉書店)
- 「現代の類義語の中にある歴史」(『早稲田大学日本語学会設立60周年記念論文集 第1冊』2021年、ひつじ書房)
- 「現代日本語のジェネレーションギャップ」(2024年、武蔵野書院)など。
コラム一覧
- 2026.1 (48)「『ほぼほぼ』『やっぱり』『わざわざ』 その副詞は何のために?」
- 2025.12 (47)「『ドッジボール』か? それとも『ドッチボール』か?」
- 2025.11 (46)「デアル体とダ体の詳細」
- 2025.10 (45)「『孔子』や『孫子』のアクセント」
- 2025.9 (44)「比喩的な『続投』が捨てられない理由」
- 2025.8 (43)「1日のうちに行う動作を表す連用形名詞+晩酌」
- 2025.7 (42)「『かき氷』関連のボキャブラリー」
- 2025.6 (41)「代名詞の表記」
- 2025.5 (40)「連体詞の表記②」
- 2025.4 (39)「連体詞の表記①」
- 2025.3 (38)「語頭のラ行音」
- 2025.2 (37)「接続詞の表記」
- 2025.1 (36)「一語文の用法を持つヒト名詞」
- 2024.12 (35)「朝昼晩のあいさつのことば」
- 2024.11 (34)「接頭辞の『ま』『ど』『せい』」
- 2024.10 (33)「相撲の世界における動詞の特別な使い方」
- 2024.9 (32)「数字の語形と表記」
- 2024.8 (31)「ぼかす副助詞」
- 2024.7 (30)「『甲の乙』という形の単語について」
- 2024.6 (29)「母音が連続するときの発音」
- 2024.5 (28)「『現代仮名遣い』と表音一致」
- 2024.4 (27)「動詞のウ音便について」
- 2024.3 (26)「『かな(仮名)』の語形とアクセントと表記」
- 2024.2 (25)「『わかる』のコミュニケーション文法」
- 2024.1 (24)「『よりか』とは何か」
- 2023.12 (23)「『お』と体の部分」
- 2023.11 (22)「質問という行為について」
- 2023.10 (21)「しこ名の『~川』」
- 2023.9 (20)「『~ていただきたいです』という表現について」
- 2023.8 (19)「今に生きる旧国名の別称」
- 2023.7 (18)「『可決・成立する』は是か非か」
- 2023.6 (17)「語頭に[p]の音を持つ単語のこと」
- 2023.5 (16)「『いる』と『おる』の活用形」
- 2023.4 (15)「『ローマ字のつづり方』は実用的か否か」
- 2023.3 (14)「御しがたいひと言『なるほど』のこと」
- 2023.2 (13)「『~犬』はイヌかケンか」
- 2023.1 (12)「『ありか』『かくれが』『すみか』の表記」
- 2022.12 (11)「みずうみ・ぬま・いけ」
- 2022.11 (10)「『お間違いありませんか(お間違いないですか)』に問題はありませんか」
- 2022.10 (09)「現代の1拍語」
- 2022.9 (08)「動植物名を表す漢字について」
- 2022.8 (07)「現代語における女の人の一人称」
- 2022.7 (06)「『水鳥』の語形とアクセント」
- 2022.6 (05)「動物と敬称②」
- 2022.5 (04)「動物と敬称①」
- 2022.4 (03)「『東方・西方』の語形」
- 2022.3 (02)「『母方・父方』の語形」
- 2022.2 (01)「『失礼します』か『失礼しました』か」