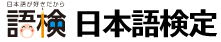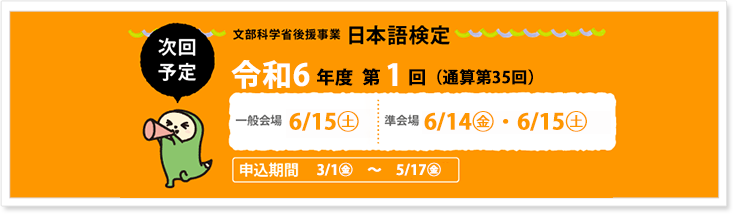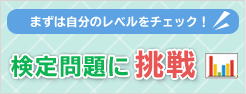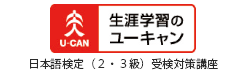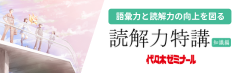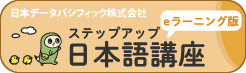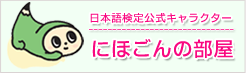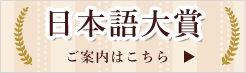表題にある「続投(する)」は、文字どおりの意味では、野球において投手が交代せずに投げ続けることを意味します。さらに二つ目の意味として、政治家などが辞職せずに、その役職を続ける場合などに比喩的に「続投」が使われることがあります。この「続投」については、時々、その適切性が問われることがあります。たとえば、高島(2009、p.252)は、野球以外の使用領域の広がった「続投」について、辞書などで意味を確かめたうえで、結論としては「小生頭がカタイもので、どうもいまだに「社長続投」のたぐいにはなじめない。どうして「留任」ではダメなのですかね」と述べています(初出は2004年12月2日の『週刊文春』)。「頭がカタイ」と謙遜していますが、同じように考える人は少なくありません。それにもかかわらず、どうして「石破首相続投」(2025年)のようにいまだに衰えずに使われるのか、その事情を考えます。
比喩的「続投」の輝き
1986年9月19日の朝日新聞のコラムで、評論家の加藤周一(1919~2008)は、「続投」について次のように指摘しています。引用は、加藤(2016、p.131)からのものです。
近ごろ都にはやるものに、「続投」という言葉がある。中曽根居すわりという代わりに、中曽根続投という。続投はもちろん野球の比喩である。比喩は巧妙で、だれが思いついたのか私は知らないが、その人の文学的才能の豊かさを示すだろう。しかし一度思いついたら、いつまで経っても同じ比喩を繰り返しているのは、そういう人の文学的無能を示す。
Sigit(2016)によれば、政治の分野で「続投」が比喩的に用いられたのは、1970年代のことだということです。上の引用文の時期(1980年代)になると、比喩的な使用がかなり目につくようになり、当初の新鮮な感覚はすでに失われ、単に惰性で用いられていると感じられたということでしょう。
筆者は、野球の世界で使われる「続投」が政治などの分野で使われたことについて、そこには、次のような理由があると考えます。
- ①
- 高度成長の時代、国民的スポーツと言えば野球(ないし相撲)であったこと。
- ②
- 交代の有無という点において、野球と政治の世界に共通点が見いだされたこと。
- ③
- どちらにも交代せずに続けることに対する意外性が伴うこと。
- ④
- 交代しないことに対する批評を述べようという意識が働くこと。
- ⑤
- どちらの世界も新聞・テレビという同じ場所で扱えること。
まず、記者の誰かが政治の記事に野球用語の「続投」の意味をずらして使うことを思いつく。記事または見出しに「続投」を使ったところ、思わぬ反響が得られた。ほかの記者もマネをして使うようになり、世間でもおもしろい表現であると気づく人が出てきた。スポーツ面と政治面のいずれにも「続投」が使われるものの、その意味は少し違う。両方の面に目を通す読者は、その違いを味わうことになります。新聞の作り手としては、してやったりという気持ちをいだいたことでしょう。そこには加藤氏の言う「文学的才能の豊かさ」があります。もし国民的スポーツがその当時からサッカーやバスケットボールであったなら、「続投」の広がりはなかったかもしれません。「交代する」「交代させる」という言い方はあっても、「続投」に相当する語がない分野もあることでしょう。たとえばボクシングでは、選手がほかの選手に交代するということ自体がありません。そのようなことを考えると、野球のことばが政治などの世界で比喩的に使われたこと、使われるに足る条件を満たしていたことは、奇跡的なことであったとも評することができます。
失われる有効性
20世紀後半、21世紀前半になると、スポーツの種類は多様化し、野球についてほとんど知らないという人が増えます。一方、紙の新聞の購読者は減り、総合、政治、経済、国際、そしてスポーツというように、順を追って新聞をめくるという生活を送る人も減ります。これはつまり、野球を意識しながら別の世界に使われる「続投」に対して味わいを覚えるという人も減っていることを意味します。
野球のことばであることを意識しつつ使うという段階からさらに進むと、野球のことばであることを知らないということとなり、「応援続投」「付き合い続投」といった野球とは無関係の使い方が出てきます。インターネット上のこういった使用例がSigit(2016)で報告されています。「応援」や「付き合い」は、動作を表します。動作を表す場合は、「続投」ではなく「続行」を使うことができます。「試合を続行する」や「交渉を続行する」と同じく「応援を続行する」で間に合います。「応援を続投する」としたところで、大きなレトリック効果は得られません。「続行」や「続ける」と比べ、少し変わった表現だという程度でしょうか。
捨てられない理由
以上のように、比喩的な「続投」が現れるようになってから年月がたち、もはやそこに目新しい表現といった価値はありません。それにもかかわらず、この言い方がマスメディアなどで愛用されているのはなぜでしょうか。新聞などでの使用を受けてか、当の国会議員も「首相、続投する気ですか」のように使っています。そこははっきり「やめない」「辞任しない」といった言い方をすればよいように感じます。
言いかえ候補となる「留任」について、国語辞典には「(任期が切れても)転任など無くそのまま、その官職・役目にとどまること」(『岩波国語辞典 第8版』(以下『岩国』))とあります。語釈にある「とどまる」は「時がたっても動こうとしないで前と同じ場所・地位に存在する」(『旺文社国語辞典 第12版』(以下『旺国』))というように、予想された動きが否定される状況で使うことの多い動詞です。それゆえ「留任する」には、「やめない」「辞任しない」と似た表現という趣があります。そして、「首相留任」「首相やめず」「首相辞任せず」といったストレートな表現に飽き足りないと感じた人が「続投」を使い始めたと想像します。比喩的な「続投」は「任期の区切りになっても役職を退かずそのまま続けること」(『岩国』)と記されます。語釈に用いられる「続ける」は「続くようにする」(『岩国』)、「ある事柄・状態を途切れさせずに連ねる。持続させる」(『旺国』)というように記され、「とどまる」とは異なり、それまでの状態に対する否定的な捉え方は表現されていません。「続ける」に対する一般的な語感としても、「続けない」ほうが望ましいという前提はないでしょう。そうすると、「続投」には「(やめるべきであると見なされる状況で)やめずに続けること」という内容のうち、丸カッコ内の内容を皮肉(アイロニー)として表現する価値があります。その価値さえあるなら、たとえ表現形式としての新鮮さは失われていても、「投」の部分の意味が生きていなくても一向にかまわない、そんなふうに解釈することができます。
別の見方をするなら、客観的に表現すべき場面で「続投」を使えば、中立的な報道としてはまずいということでもあります。たとえば、朝日新聞とNHKの世論調査を比べてみると、次のような書き方が見られます。
朝日新聞:朝日新聞社が16、17の両日に実施した全国世論調査(電話)で、参院選の結果を受けて石破茂首相は辞めるべきか尋ねたところ、「辞めるべきだ」は36%(前回7月調査41%)で、「その必要はない」が54%(前回47%)と過半数を占めた。
(2025年8月18日、朝刊)NHK:石破総理大臣が、参議院選挙の敗北後、「政治空白をつくってはならない」として続投の意向を示していることについて、その賛否を尋ねたところ、「賛成」が49%、「反対」が40%、「わからない、無回答」が11%でした。
(2025年8月12日、NHK選挙WEB)どちらも調査対象者に実際に提示された文言であると見なして話を進めます。その場合、朝日新聞のほうは、「辞める」という表現を使っているので特段の問題はありませんが、NHKのほうは「続投」を使っています。これは、比喩的な「続投」になじみのない調査対象者がいる可能性を見落としていることとともに、「続投」の意味をよく理解している調査対象者がマスメディアの批判的な見方を「続投」から読み取り、それが回答に影響してしまう恐れがあることも問題です。特段、皮肉などを意図しているわけではないというなら、それこそ「続ける」「やめる」など、普通の表現を使うべきだということになります(筆者の用字として、「辞める」は「やめる」と表記します)。
「居座る」と「続投する」
やめずにいるということを「居座る」であれば批判的に伝えることができます。ただし、「首相居座り」などとすると、政治家側からひどい言い方だと苦情が来るかもしれません。それに対し、「首相続投」なら表向きは批判的な言い方ではないとかわすことができるとマスメディア側の人は考えるのかもしれません。しかしです。第三者の目で見れば、いずれも「やめるべきタイミングでやめない」ことを意図して使う表現であることに違いはありません。それよりも、「首相やめず(ない)」といった言い方にしておいて、やめるべきだという理由があるなら、それは、記事本文(論説文など)で論じるという形をとったほうが中立報道の文章としてふさわしいと感じます。「続投容認」など名詞的に表現するのに「続ける」「やめる」などの和語動詞では具合が悪いなら、「留任容認」のように「留任」で十分です。
おわりに
長らく筆者は、「続投」という語の比喩的な意味・用法が廃れずにいることに対して、不思議に感じてきました。以上のような理由があると考えることにより、ようやく自分の中で一応の答えが得られた気がしています。今後は、「続ける」や「やめる」など、ひねりのない普通の言い方がもっと使われることを願います。
参考文献
加藤周一(2016)『夕陽妄語1』筑摩書房
高島俊男(2009)『お言葉ですが…⑩ちょっとヘンだぞ四字熟語』文芸春秋
Sigit Sugiarto(2016)「「続投」の意味・用法の一般化」『名古屋言語研究』10
![]()
中川秀太
文学博士、日本ウェルネススポーツ大学スポーツプロモーション学部 准教授、日本語検定 問題作成委員
専攻は日本語学。文学博士(早稲田大学)。2017年から日本語検定の問題作成委員を務める。
- 最近の研究
- 「現代日本語のジェネレーションギャップ」(2024年、武蔵野書院)
- 「日本語検定と校閲との接点を探る」(2024年、日本経済新聞社の勉強会における発表)
- 「同訓異字の「使」と「遣」」(2024年、毎日新聞の「毎日ことばplus」への寄稿)
- 「「わがこと」「じぶんごと」「ひとごと」「よそごと」「たにんごと」」(『東京女子大学日本文学』121、2025年)
- 「肯定・否定を表す対義的な応答詞の使用によって生じる社会的な分断」(『大正大学研究紀要』110、2025年)など。
コラム一覧
- 2026.1 (48)「『ほぼほぼ』『やっぱり』『わざわざ』 その副詞は何のために?」
- 2025.12 (47)「『ドッジボール』か? それとも『ドッチボール』か?」
- 2025.11 (46)「デアル体とダ体の詳細」
- 2025.10 (45)「『孔子』や『孫子』のアクセント」
- 2025.9 (44)「比喩的な『続投』が捨てられない理由」
- 2025.8 (43)「1日のうちに行う動作を表す連用形名詞+晩酌」
- 2025.7 (42)「『かき氷』関連のボキャブラリー」
- 2025.6 (41)「代名詞の表記」
- 2025.5 (40)「連体詞の表記②」
- 2025.4 (39)「連体詞の表記①」
- 2025.3 (38)「語頭のラ行音」
- 2025.2 (37)「接続詞の表記」
- 2025.1 (36)「一語文の用法を持つヒト名詞」
- 2024.12 (35)「朝昼晩のあいさつのことば」
- 2024.11 (34)「接頭辞の『ま』『ど』『せい』」
- 2024.10 (33)「相撲の世界における動詞の特別な使い方」
- 2024.9 (32)「数字の語形と表記」
- 2024.8 (31)「ぼかす副助詞」
- 2024.7 (30)「『甲の乙』という形の単語について」
- 2024.6 (29)「母音が連続するときの発音」
- 2024.5 (28)「『現代仮名遣い』と表音一致」
- 2024.4 (27)「動詞のウ音便について」
- 2024.3 (26)「『かな(仮名)』の語形とアクセントと表記」
- 2024.2 (25)「『わかる』のコミュニケーション文法」
- 2024.1 (24)「『よりか』とは何か」
- 2023.12 (23)「『お』と体の部分」
- 2023.11 (22)「質問という行為について」
- 2023.10 (21)「しこ名の『~川』」
- 2023.9 (20)「『~ていただきたいです』という表現について」
- 2023.8 (19)「今に生きる旧国名の別称」
- 2023.7 (18)「『可決・成立する』は是か非か」
- 2023.6 (17)「語頭に[p]の音を持つ単語のこと」
- 2023.5 (16)「『いる』と『おる』の活用形」
- 2023.4 (15)「『ローマ字のつづり方』は実用的か否か」
- 2023.3 (14)「御しがたいひと言『なるほど』のこと」
- 2023.2 (13)「『~犬』はイヌかケンか」
- 2023.1 (12)「『ありか』『かくれが』『すみか』の表記」
- 2022.12 (11)「みずうみ・ぬま・いけ」
- 2022.11 (10)「『お間違いありませんか(お間違いないですか)』に問題はありませんか」
- 2022.10 (09)「現代の1拍語」
- 2022.9 (08)「動植物名を表す漢字について」
- 2022.8 (07)「現代語における女の人の一人称」
- 2022.7 (06)「『水鳥』の語形とアクセント」
- 2022.6 (05)「動物と敬称②」
- 2022.5 (04)「動物と敬称①」
- 2022.4 (03)「『東方・西方』の語形」
- 2022.3 (02)「『母方・父方』の語形」
- 2022.2 (01)「『失礼します』か『失礼しました』か」