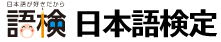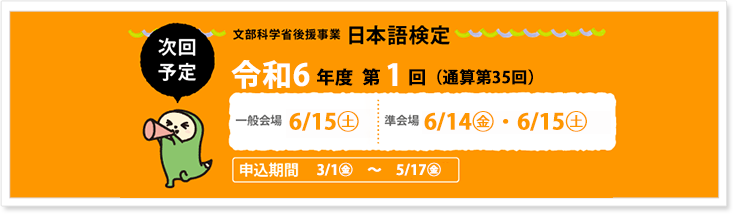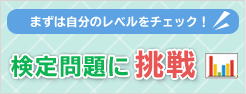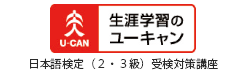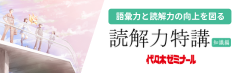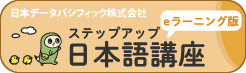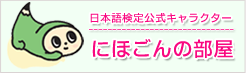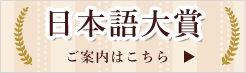夏が近づくと食べたくなる「かき氷」(欠き氷)。最近は、冬の寒い時期にも食べるという人が増えてきました。ことばとしては、昔から「かき氷」であったかと思いきや、実は、そうではないようです。日本語学者の森田良行氏(1930~)は、森田(1989、p.59)で次のように述べています。
筆者の年代の者には「こおりみず」は削った細かい氷にシロップなどを掛けたもので、明らかに「かきごおり」(欠き氷)とは異なる。氷のぶっかき(かちわり)が「かきごおり」なのだが、現代語では、特に若い世代の者は、いわゆる氷水を「かきごおり」と呼び、「こおりみず」は、欠き氷(氷のかけら)を入れて冷やした飲み水を指すらしい。これは、欠き氷にリキュール酒を注いだ「フラッペ」(フランス語のfrappéから)に対応する名称である。同じ「こおりみず」が世代差によって氷水を指したり欠き氷を入れた水を指したりで、意味の上でゆれの現象を呈している。言い換えれば、昭和前半までの日本語と現代語との間に指示する対象にずれが生じた(意味変化)と考えられる。
「意味の上でゆれ」とありますが、森田氏の論考が出たときから30年以上がたった2025年現在では、「こおりみず」で氷にシロップをかけたものを指す人は、さらに数が少なくなっていることでしょう。ゆれは収まり、「こおりみず=氷を入れた水」への変化がほぼ完成したと言ってもよいかもしれません。ここでは、上記の指摘をもとにして、どのような語彙、意味の再編成が生じたのかを整理します。
関連語の一覧
以下には、「かき氷」に関連する語の一覧を示します。丸カッコ内は、『日本国語大辞典 第2版』(以下『日国』)の示す初出例の年であり、用例が『日国』にない場合は「なし」とします。単語を示す箇所は、太字で目立たせます。
- ・
- 氷を砕いたもの:けずりひ(970~999頃) かきごおり(なし) ぶっかき(1909) かちわり(なし、大阪や奈良の方言として記載される) ロックアイス(『日国』に見出しはない、商標名)
- ・
- 氷をみぞれ状に細かくしたもの。蜜やシロップをかける:こおりみず(1877、補注に「石井研堂「明治事物起原―一八」によると、明治四、五年からはやり出した」とある) かきごおり(1951) こおりすい(なし) フラッペ(なし)
- ・
- 氷を細かくしたものに蜜のみをかけたもの:すい(1971、漢字で書くなら「水」) みぞれ(なし)
- ・
- 氷を入れた冷たい水:ひみず(10C終) こおりみず(1563)
「こおりみず」については、夏目漱石の『それから』(『定本 漱石全集6』2017年、岩波書店)に以下の用例がありました。
誠太郎と云ふ子は近頃ベースボールに熱中してゐる。代助が行つて
時々
球
を投げてやる事がある。彼は妙な希望を持つた子供である。
毎年
夏
の初めに、多くの
焼芋
屋が俄然として
氷
水
屋に変化するとき、第一番に馳けつけて、汗も出ないのに、
氷菓
を食ふものは誠太郎である。
氷菓
がないときには、
氷
水
で我慢する。
※原文についているルビの繰り返し符号は、符号を使わず文字に置き換えて表示する。
「アイスクリーム」と「氷水」が比較対象となっています。「氷水」が氷にシロップをかけた食べ物のことを示していて、「氷を入れた水」ではないことがよくわかる用例です。
変遷
「すい」に関し、戸板(1962、p.307)に「五銭の、砂糖水(甘露)だけの氷を「すい」というのは、東京だけのことなのだろうか。最近久保田先生が都内のさるところで、「すい」と注文されたが通用しなかったそうだ」との指摘があります。久保田とあるのは、小説家の久保田万太郎(1889~1963)のことです。高橋(1967、p.159)にも「すい」が「近年次第に姿を見せなくなった」とあります。
「みぞれ」については、『日国』に用例がありません。大阪出身の高橋和巳(1931~1971)の『憂鬱なる党派』に「みぞれを下さい」「ちょっと氷のかち破(わ)りを入れてな」と登場人物が口にする場面(場所は大阪)があるのが地域性についてのヒントになるかもしれませんが、詳しいところは調査を要します。また、久保田、高橋の指摘する状況が①「すい」そのものが(一時的に)廃れた、②「すい」という語が廃れ「みぞれ」が使われだした、という場合のいずれであるかについても知りたいところです。なお、東京・上野の、あるかき氷の店(約80年前の創業)では、一般的には「みぞれ」であるとしつつもあえて「すい」を品名に用いているということを2024年11月に店に行って確認しました。東京都北区十条の店では、筆者が「みぞれはありますか」と聞いたところ、ご主人(70代ぐらい)から「すいのことでしょう、ありますよ」との返答を得た(2024年12月)。ほかの店の状況や「甘露」「せんじ」を用いる地域の調査なども行いたいところです。
『枕草子』や『源氏物語』に用例のある「ひみず」が現代人には使いにくく、「氷を入れた水」という字義どおりの意味で「こおりみず」が好まれるようになり、蜜やシロップをかけた物の意味は、「かきごおり」に委ねられることとなりました。物の状態から言えば「けずりごおり」とでも称する語が生まれてもおかしくはありませんでしたが、そうはならずに「かきごおり」が定着しました。なお「みぞれ」の語釈に「けずり氷」を用いる辞書があります。「氷」の部分の語形は「けずりひ」ではなく「けずりごおり」であると見なしておきます。
「フラッペ」は、果物やアイスを添える場合は、通常の「かきごおり」との大きな違いとなりますが、「かき氷」(『明鏡国語辞典 第3版』)や「(洋風の)かき氷」(『三省堂国語辞典 第8版』)の意味でも使われるところが複雑です。
まとめ
そう遠くない過去において、「かき氷」関連の語彙に変化が生じたことを確認しました。考えてみると、「こおりみず」で細かく削った氷のことを指すというのが特殊なことでもあります。たとえば「どろみず(泥水)」や「なまみず(生水)」のように、名詞二つを並べて複合語にする場合、前の要素「どろ」「なま」が後ろの要素「水」の性質を修飾(限定)しています。複合語の「泥水」「生水」は「水」の一種を表します。それに対し、「こおりみず」で削った氷を意味するという場合は、意味から言えば後ろに来るはずの「こおり」が前に来ています(なぜそういう並びになったのかは不詳)。そのため、「氷なのに(こおり)水と呼ぶこと」には、意味のうえで不自然さがあると言えます。そのようなことが背景となり、「こおりみず」は、文字どおり「水」を指す場合へと意味が変化し、「氷」を指す場合は「かき氷」を使うというように推移してきたのでしょう。
現在、「氷をみぞれ状に細かくしたもの」は「かき氷」、「氷を入れた冷たい水」は「氷水」と呼ぶように統一されてきました。他方、「氷を砕いたもの」は「ぶっかき」「かちわり」「ロックアイス」でゆれが続いています。「氷を細かくしたものに蜜のみをかけたもの」は、「みぞれ」が多いようですが、老舗(しにせ)などでは「すい」を使い続けたり、あるいはあえて「すい」を選んだりしている店もあります。ひとまず、「氷水」の指すところが人によって異なり、会話に食い違いが起こるような事態がなくなったことをよしと見るべきでしょうか。
参考文献
高橋義孝(1967)『穏健なペシミストの観想』新潮社
戸板康二(1962)『ハンカチの鼠』三月書房
森田良行(1989)「語彙と語義の移り行き」『国文学解釈と鑑賞』54-7
![]()
中川秀太
文学博士、日本ウェルネススポーツ大学スポーツプロモーション学部 准教授、日本語検定 問題作成委員
専攻は日本語学。文学博士(早稲田大学)。2017年から日本語検定の問題作成委員を務める。
- 最近の研究
- 「現代日本語のジェネレーションギャップ」(2024年、武蔵野書院)
- 「日本語検定と校閲との接点を探る」(2024年、日本経済新聞社の勉強会における発表)
- 「同訓異字の「使」と「遣」」(2024年、毎日新聞の「毎日ことばplus」への寄稿)
- 「「わがこと」「じぶんごと」「ひとごと」「よそごと」「たにんごと」」(『東京女子大学日本文学』121、2025年)
- 「肯定・否定を表す対義的な応答詞の使用によって生じる社会的な分断」(『大正大学研究紀要』110、2025年)など。
コラム一覧
- 2026.1 (48)「『ほぼほぼ』『やっぱり』『わざわざ』 その副詞は何のために?」
- 2025.12 (47)「『ドッジボール』か? それとも『ドッチボール』か?」
- 2025.11 (46)「デアル体とダ体の詳細」
- 2025.10 (45)「『孔子』や『孫子』のアクセント」
- 2025.9 (44)「比喩的な『続投』が捨てられない理由」
- 2025.8 (43)「1日のうちに行う動作を表す連用形名詞+晩酌」
- 2025.7 (42)「『かき氷』関連のボキャブラリー」
- 2025.6 (41)「代名詞の表記」
- 2025.5 (40)「連体詞の表記②」
- 2025.4 (39)「連体詞の表記①」
- 2025.3 (38)「語頭のラ行音」
- 2025.2 (37)「接続詞の表記」
- 2025.1 (36)「一語文の用法を持つヒト名詞」
- 2024.12 (35)「朝昼晩のあいさつのことば」
- 2024.11 (34)「接頭辞の『ま』『ど』『せい』」
- 2024.10 (33)「相撲の世界における動詞の特別な使い方」
- 2024.9 (32)「数字の語形と表記」
- 2024.8 (31)「ぼかす副助詞」
- 2024.7 (30)「『甲の乙』という形の単語について」
- 2024.6 (29)「母音が連続するときの発音」
- 2024.5 (28)「『現代仮名遣い』と表音一致」
- 2024.4 (27)「動詞のウ音便について」
- 2024.3 (26)「『かな(仮名)』の語形とアクセントと表記」
- 2024.2 (25)「『わかる』のコミュニケーション文法」
- 2024.1 (24)「『よりか』とは何か」
- 2023.12 (23)「『お』と体の部分」
- 2023.11 (22)「質問という行為について」
- 2023.10 (21)「しこ名の『~川』」
- 2023.9 (20)「『~ていただきたいです』という表現について」
- 2023.8 (19)「今に生きる旧国名の別称」
- 2023.7 (18)「『可決・成立する』は是か非か」
- 2023.6 (17)「語頭に[p]の音を持つ単語のこと」
- 2023.5 (16)「『いる』と『おる』の活用形」
- 2023.4 (15)「『ローマ字のつづり方』は実用的か否か」
- 2023.3 (14)「御しがたいひと言『なるほど』のこと」
- 2023.2 (13)「『~犬』はイヌかケンか」
- 2023.1 (12)「『ありか』『かくれが』『すみか』の表記」
- 2022.12 (11)「みずうみ・ぬま・いけ」
- 2022.11 (10)「『お間違いありませんか(お間違いないですか)』に問題はありませんか」
- 2022.10 (09)「現代の1拍語」
- 2022.9 (08)「動植物名を表す漢字について」
- 2022.8 (07)「現代語における女の人の一人称」
- 2022.7 (06)「『水鳥』の語形とアクセント」
- 2022.6 (05)「動物と敬称②」
- 2022.5 (04)「動物と敬称①」
- 2022.4 (03)「『東方・西方』の語形」
- 2022.3 (02)「『母方・父方』の語形」
- 2022.2 (01)「『失礼します』か『失礼しました』か」