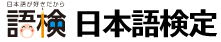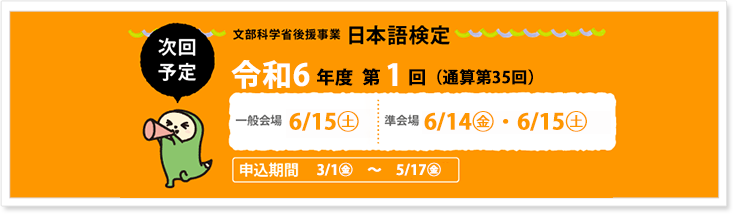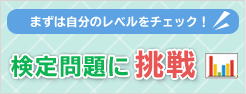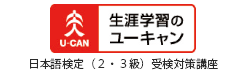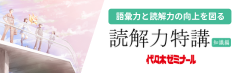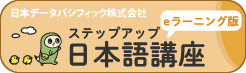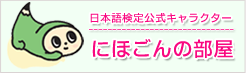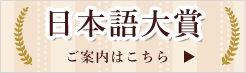たとえば「眠る」と「寝る」は、似た意味の動詞として、その使い分けが問題となります。では、それぞれの連用形が名詞(の一部)として使われる場合はどうでしょうか。「眠り」は「眠りから覚める」「眠りにつく」など、いろいろな動詞との組み合わせで用いられますが、「寝」は「寝が足りない」程度の言い方しかなく、同じことを「眠りが足りない」とも言えます。つまり動詞の場合は、使い分けが複雑であったとしても、名詞としては「眠り」が一般的であり、「寝」のほうは、必要性が低いということです。また、これらの名詞は「睡眠」という漢語名詞とも類義関係にあります。以下では、人が1日のうちに一般的に行う動作について、連用形名詞がどのように用いられるかということを考えます。
起床
まず朝、起きたときは「目覚め」という名詞+動詞連用形の複合名詞はあっても、「覚め」または「起き」という言い方は使いません。「伸び」をするなどしてから布団を畳む。顔や髪を洗ったり歯を磨いたりするとき、「歯磨き」はあっても「顔洗い」はなく「洗顔」(漢語)を使います。一方、「手を洗う」「手洗い」はあっても、「洗手」とは言いません。辞書に「髪洗い」がありますが「洗髪」のほうが優勢でしょうか。体のどこを指すのかわかりにくいため、「磨き」「洗い」単独では使えません。
食事の前後
食事の前に散歩やランニングをするという人もいますが、そのような意味の語として「歩き」「走り」は存在しません。日課としての「散歩」の意味では「そぞろ歩き」は使いにくいでしょう。「体操」「ストレッチ」「筋力トレーニング」に相当する連用形名詞もありません。
場所を問わず要らない物を捨てれば「ゴミ捨て」となるのに対し、「ゴミ出し」は決められた場所にゴミを置くことであるという違いがあります。
食事
食事のとき(朝昼晩)は、料理の段階で「切る」「煮る」「炒める」「沸かす」「ふかす」「漬ける」「炊く」などの動詞を使いますが、「煮が足りない」「ふかしが足りない」など、連用形名詞の数も、その用法も限られます。食事をする段階で「飲み」がありますが、これは酒を飲む意味に限定されています。英語ではdrinkが動詞に加えて飲む物を表す名詞としても使われますが、日本語では、動詞は「飲む」のみが担当し「ドリンクする」は使わず、名詞は「飲み物」「ドリンク」を併用するという状況にあります。食べる場合は、動詞に「食べる」を使い、外来語の「イート」は「イートする」とは言わず、「イートイン」など、今のところは複合語の要素として使う用法に限られます。名詞は、「食べ」がなく「食べ物」と外来語の「フード」とが併用されます。動作を表す名詞としては、和語の「飲み食い」と漢語の「食事」「飲食」が用いられます。外出先で「食事」「飲み食い」「飲食」をすることはあっても、自宅の場合に「飲み食い」「飲食」は使いにくい気がします。もちろん「食事」は使えます。辞書には、「検診の前に飲食しないように」(『デジタル大辞泉 アプリ版』)という、医師などからの指示を示すとおぼしい用例があります。このような医療的な立場においては、家か外かという点は問題にならず、食べ物・飲み物を口にするな、ということが表せれば十分です。その指示を自宅で家族に伝える場合に「あしたは検査があるから飲食は控えるように言われている」と言うこともあるでしょう。したがって、筆者が使いにくいとするのは、日常生活で「食事はまだだ」「食事を済ませる」などと言うことはあっても、自宅での飲食行為について「飲み食いはまだだ」「飲食を済ませる」などと言うことはないということです。字義的な意味から言えば、そのような使い方があってもおかしくなさそうですが、実際には「飲み食い」「飲食」は、外での行いを指すのに適したことばです。
食後
食後の「後片づけ」のあとは、「掃除」「洗濯」と続き連用形名詞の出番がありません。具体的な動作としては「皿洗い」や「はたき(をかける)」があります。庭があれば、「庭いじり」「庭仕事」をすることもあります。類義語に「園芸」や「ガーデニング」があり、「ガーデニングも英語で言い換えると、かっこいいみたいになっている。なんで庭いじりといわないのか、と思いますね」(津島佑子「毎日新聞夕刊」1998年4月23日)と指摘されました。「スマホをいじる」に見られるように、「いじる・いじり」には、ややマイナスの評価が感じられ、「庭いじり」とは言いたくない、それなら「庭仕事」や「園芸」のほうがベターであり、おしゃれに言うなら「ガーデニング」を使うとの判断が行われるようです。
入浴
食後、本を読んだりテレビを見たりして時間を過ごし、その後、風呂に入るとします。「入る」「つかる」のあと、「上がる」「出る」という動作が続きます。このうち、連用形が活用されているのは、「上がる」の「上がり」のみであり、「湯上がり」「風呂上がり」という語があります。「上がり」単独では使いません。作家の山本夏彦(1915~2002)は、作家の向田邦子(1929~1981)の随筆では「湯あがりと言って風呂あがりと言ってない」と述べ、「湯上がり」のほうが標準的ないし伝統的な東京の言い方であることをにおわせています(山本(1980、p.171))。現在は、「湯上がり」は使わない、でも柔らかい言い方がしたいという人は「お風呂上がり」を選びます。
「晩酌」を取り巻く現状
外で酒を飲む場合は「飲みに行こう」などと言うのに対し、自宅で酒を飲むことには「晩酌」が用いられます。「晩酌」も字義的には「晩に酒をつぐ」ことしか表さないので、自宅でも外でもよさそうですが、実際には自宅での行為に使用が偏ります。外で飲む場合に「晩酌」が使えないと言い切れるかどうかについての国語辞典の判断は分かれ、『明鏡国語辞典 第3版』(『明鏡』)は「家庭で、夕食のときに酒を飲むこと」と記しますが、『岩波国語辞典 第8版』(『岩国』)は「(家で)晩飯のときに酒を飲むこと」と、「家」をカッコに入れて記します。『旺文社国語辞典 第12版』『デジタル大辞泉 アプリ版』は『明鏡』と同様であるのに対し、『学研現代新国語辞典 改訂第6版』『三省堂国語辞典 第8版』『新明解国語辞典 第8版』『大辞林 第4版』は『岩国』と同様の扱いをしています。『新選国語辞典 第10版』のように、「家庭」にふれず「夕食のとき酒を飲むこと」とのみ記す辞書もあります。『現代国語例解辞典 第5版』も同様です。旧来の日本社会では、自宅で食事をするのが普通であり、外で食べるのは特別なことであった。そういう特別な場合を指すために「外食」ということばが必要とされたと考えてみます。それに対し、家でする食事を表す「中食(なかしょく・ちゅうしょく)」「内食(うちしょく・ないしょく)」は比較的に新しい語です。一般的である家庭での夕食どきに、食事に加えて酒も飲むことを表現するための語として「晩酌」が求められたと考えられます。外で酒を飲む場合は、最初から「酒を飲みに行く」など、食事よりも酒を優先的に表現します。その場合は「夕食のときに酒が伴う」のではなく「酒を飲むときに夕食が伴う」という感覚であり、「晩酌」の必要性が下がります。「いつも外で夕食をとり、そこに酒を添える」という人がいることは否定しませんが、一般的な「晩酌」の使い方としては、家庭での行為に偏りがちであると見てもよさそうです(外での「晩酌」を完全否定はしません)。あるいは、店側で「晩酌セット」(アルコール1杯とつまみ)という売り出し方をしていることがあり、それをもとにして、外でも「晩酌」が使えると捉えている人もいそうです。
ここまでは、「晩酌」がウチとソトのどちらに偏って使われるかという話でした。ここからは、「晩酌」が使いにくいという人が増えてきている現状について考えます。数百人の大学生の感想などを聞いてみると、現在、「晩酌」を自分で使うという人はごくわずかです(知らないことばという回答も珍しくありません)。祖父や父が使うのを見て自分でも使うようになったという学生も時にはいます。では、「晩酌」が使いにくいという人がどういう印象をこの語にいだいているかというと、「父親の世代が使うことば。サラリーマンのことば」といった意見がよく聞かれます。ポイントは「母親の世代」という意見がないことです。筆者なりに現代語としての「晩酌」につきまとう語感を述べると、次のようになります。
戦後の昭和から平成にかけて、外で忙しく働くのは主に男の役割であると見なされた。夫が自宅に戻ると、妻が風呂か食事かの選択を促す。そして食事にはビールや日本酒といった酒が付随する。息子や娘は、その父親の姿を見て、晩酌という行為とことばを覚える。あるいは、本やテレビで覚えた「晩酌」ということばについての確かな実感を得る。ことばそのものの意味から言えば、大学生ぐらいの年齢の人が自分が飲むことについて、晩酌を使うという道がひらけるものの、典型的なものとしては、仕事でたまった疲れを1杯の酒で癒やすという社会人の行為、子どもにとっては父親の行う行為という印象が「晩酌」には強い。ところが、バブル経済の崩壊した1990年代以降になると、終身雇用制は崩れだし、家族で食卓を囲む家庭は減り、バラバラの時間に食べる、または家族が別々に食べる「個食・孤食」といった現象が増えてくる。そうして、父親が晩に酒を飲む姿を見て晩酌という行為とことばを身につける機会を持たない人が増えた。父親世代というところからさらに発展し、「おじさんくさい」といった語感がつきまとうことにより、死語化する可能性が出てきた。
以上に対し、2020年から数年間、新型コロナウイルスがはやった時期には、外に飲みに行かず自宅で飲むことが目立つようになり、「家飲み」「宅飲み」「自宅飲み」という言い方が盛んに用いられ、外で飲むことは「外飲み」と表現されるようになりました。たとえば「家飲み」は、『大辞林 第4版』では「俗に、自宅で酒を飲むこと。家族で飲む場合や、知人どうしが集まって飲む場合など。宅飲み。自宅飲み」と記されます。1人で飲む場合に「家飲み」が使われる可能性を考慮したためか、『新選国語辞典 第10版』では「〔俗語〕自宅で酒を飲むこと」と、最小限の記述にとどめています。辞書で「俗に」「俗語」という評価がなされていることには、①「家で飲む」だから「家飲み」とする造語のしかたは安直である、②これらの語を使うのが主に若い層に限られると辞書の編者が考えた(分別のあるおとなは安易に造語せず、「家で飲む」「自宅で飲む」と言えば済む、とも)、③「晩酌」ということばを知らないのかと不審に思った、といった要因が働いたように推測しますが、筆者自身は編者ではないため、断定はできません。「家飲み」などを使う人がどの年代になってもそれらを使い続けるのか、それともしかるべき年齢になれば「晩酌」を使うようになるのか、それとも「家飲み」類と「晩酌」を使い分けるようになるのか、今後の行方が楽しみです。
そういえば、日常生活で使う「晩~」のことばには、「晩飯」「晩ごはん」といったものがありますが、これらは、「夜飯」「夜ごはん」に主役の座を奪われるようになってきています。「晩」に対する一般の人の愛着が薄れていると見れば、「晩酌」に同じことが起こっても不思議ではありません。「晩~」の語は、日常語からは消えて、「(最後の)晩さん・晩さん(会)」や「晩婚(化)」のように、改まった言い方ないし文章語として生き延びることになるのかもしれません。
まとめ
1日の行動だけを見ても、いろいろな連用形名詞およびその類義語となる漢語や外来語がひしめき合っている様子がうかがえます。新たに生み出されることばや衰退することばがあることにも気づきました。辞書や本・雑誌から連用形名詞をすべて抜き出して、その特徴を考えるというようなアプローチが一般的ですが、ここでは、人の生活というものを主軸として、そこで行われる基本的な動作が何か、その動作を表すことばは何か、という方向でアプローチしてみました。語彙は、いろいろな側面から眺めることが大切だと感じます。
参考文献
山本夏彦(1980)『つかぬことを言う』平凡社
![]()
中川秀太
文学博士、日本ウェルネススポーツ大学スポーツプロモーション学部 准教授、日本語検定 問題作成委員
専攻は日本語学。文学博士(早稲田大学)。2017年から日本語検定の問題作成委員を務める。
- 最近の研究
- 「現代日本語のジェネレーションギャップ」(2024年、武蔵野書院)
- 「日本語検定と校閲との接点を探る」(2024年、日本経済新聞社の勉強会における発表)
- 「同訓異字の「使」と「遣」」(2024年、毎日新聞の「毎日ことばplus」への寄稿)
- 「「わがこと」「じぶんごと」「ひとごと」「よそごと」「たにんごと」」(『東京女子大学日本文学』121、2025年)
- 「肯定・否定を表す対義的な応答詞の使用によって生じる社会的な分断」(『大正大学研究紀要』110、2025年)など。
コラム一覧
- 2026.1 (48)「『ほぼほぼ』『やっぱり』『わざわざ』 その副詞は何のために?」
- 2025.12 (47)「『ドッジボール』か? それとも『ドッチボール』か?」
- 2025.11 (46)「デアル体とダ体の詳細」
- 2025.10 (45)「『孔子』や『孫子』のアクセント」
- 2025.9 (44)「比喩的な『続投』が捨てられない理由」
- 2025.8 (43)「1日のうちに行う動作を表す連用形名詞+晩酌」
- 2025.7 (42)「『かき氷』関連のボキャブラリー」
- 2025.6 (41)「代名詞の表記」
- 2025.5 (40)「連体詞の表記②」
- 2025.4 (39)「連体詞の表記①」
- 2025.3 (38)「語頭のラ行音」
- 2025.2 (37)「接続詞の表記」
- 2025.1 (36)「一語文の用法を持つヒト名詞」
- 2024.12 (35)「朝昼晩のあいさつのことば」
- 2024.11 (34)「接頭辞の『ま』『ど』『せい』」
- 2024.10 (33)「相撲の世界における動詞の特別な使い方」
- 2024.9 (32)「数字の語形と表記」
- 2024.8 (31)「ぼかす副助詞」
- 2024.7 (30)「『甲の乙』という形の単語について」
- 2024.6 (29)「母音が連続するときの発音」
- 2024.5 (28)「『現代仮名遣い』と表音一致」
- 2024.4 (27)「動詞のウ音便について」
- 2024.3 (26)「『かな(仮名)』の語形とアクセントと表記」
- 2024.2 (25)「『わかる』のコミュニケーション文法」
- 2024.1 (24)「『よりか』とは何か」
- 2023.12 (23)「『お』と体の部分」
- 2023.11 (22)「質問という行為について」
- 2023.10 (21)「しこ名の『~川』」
- 2023.9 (20)「『~ていただきたいです』という表現について」
- 2023.8 (19)「今に生きる旧国名の別称」
- 2023.7 (18)「『可決・成立する』は是か非か」
- 2023.6 (17)「語頭に[p]の音を持つ単語のこと」
- 2023.5 (16)「『いる』と『おる』の活用形」
- 2023.4 (15)「『ローマ字のつづり方』は実用的か否か」
- 2023.3 (14)「御しがたいひと言『なるほど』のこと」
- 2023.2 (13)「『~犬』はイヌかケンか」
- 2023.1 (12)「『ありか』『かくれが』『すみか』の表記」
- 2022.12 (11)「みずうみ・ぬま・いけ」
- 2022.11 (10)「『お間違いありませんか(お間違いないですか)』に問題はありませんか」
- 2022.10 (09)「現代の1拍語」
- 2022.9 (08)「動植物名を表す漢字について」
- 2022.8 (07)「現代語における女の人の一人称」
- 2022.7 (06)「『水鳥』の語形とアクセント」
- 2022.6 (05)「動物と敬称②」
- 2022.5 (04)「動物と敬称①」
- 2022.4 (03)「『東方・西方』の語形」
- 2022.3 (02)「『母方・父方』の語形」
- 2022.2 (01)「『失礼します』か『失礼しました』か」