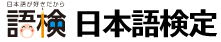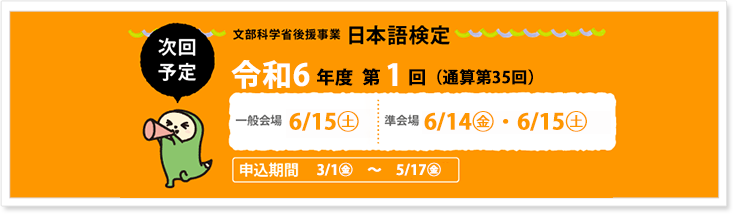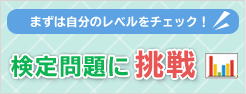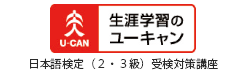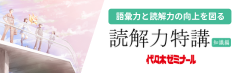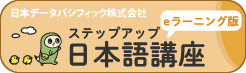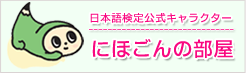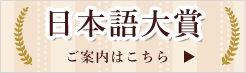古代中国の思想家のうち、「孔子」や「老子」のように、「~子(し)」を後ろに持つ人物のアクセントを考えます。アクセントは、単語ごとに決まっているオトの高い・低いの組み合わせのことです。「孔子」や「老子」の場合、コーシ ̄、ローシ ̄というように、平板型(オトの下がる部分がない)のアクセントで定着しているように感じますが、「孫子」のソ\ンシのように、頭高型(1モーラ目のみが高い)のアクセントを持つ人名もあります(ここでは「~子」までを人名として扱います)。「~子」の人名について、そのアクセントを整理します。
「モーラ」とは「拍(はく)」ともいい、日本語の発音単位のことです。「あいうえお」は、5モーラです。「あ」や「い」それぞれが1モーラです。特殊拍と呼ばれる長音(伸ばすオト、「カード」の「ー」)、促音(小さいツのオト。「カット」の「ッ」)、はつ音(撥音。ンのオト。「ヒント」の「ン」)も、それぞれ1モーラとしてカウントします。
辞書の扱い
アクセントを載せる辞書のうち、一部の辞書には固有名詞のアクセントも載ります。アクセント専門のアクセント辞典の中にも固有名詞のアクセントを載せるものがあります。それらをもとにして、古代中国の思想家についての記載状況を下の表に掲げます。表の中で「日国」とあるのは『日本国語大辞典 第2版』、「NHK」は『NHK日本語発音アクセント新辞典』、「大辞泉」は『デジタル大辞泉 アプリ版』、「新明解」は『新明解国語辞典 第8版』、「新明解アク」は『新明解日本語アクセント辞典 第2版』のことをそれぞれ指します。その右に「柴田」とあるのは、NHKの元アナウンサーであり、NHK放送文化研究所の用語担当部長を務めた経験を持つ柴田実氏のことです。同氏は、『大辞林』のアクセントの記述も担当しています(一部)。「山下」は、NHK放送文化研究所の山下洋子氏のことです。同氏は『NHK日本語発音アクセント新辞典』の編集メンバーのひとりです。「中川」は本稿の筆者のことです。それぞれの人間が選んだアクセントを名前の下に記しています。

「なし」とあるのは、その語が辞書に載っていないこと、「アクなし」とあるのは、見出しはあっても、アクセントが載っていないこと、をそれぞれ意味します。番号は、たとえば「晏子」であれば、1モーラ目にアクセントの中心部、つまりアクセント核があること、「韓非子」は3モーラ目にアクセント核があることを表し、0は、下がる部分がどこにもないことを表します。「荘子」の『新明解アク』のところに「ソージ0」とあるのは、同辞書では「ソーシ」ではなく「ソージ」のみが立項され、アクセントが平板型であることを意味します。
表の内容をもとにして、次のように整理することができます。
- ①
- 3モーラ以外の語の場合、「子」の直前にアクセント核がある。例:ゴ\シ(呉子)、カンピ\シ(韓非子)、キコク\シ(鬼谷子)
- ②
- 3モーラ語は、頭高型(1モーラ目から2モーラ目にかけてオトが下がるタイプ)が一般的である。例:ボ\クシ(墨子)、ア\ンシ(晏子)、レ\ッシ(列子)
- ③
- 2モーラ目が長音の3モーラ語は、平板型が一般的である。
標準語では、ンやッなどの特殊拍にはアクセント核が来ません。アやイなどの母音やカやサのように子音+母音からできているオトと比べて、オトとしての安定性に欠けると捉えられているからです。そこで、アン\シではなくア\ンシ、レッ\シではなくレ\ッシというように、一つ前のモーラにアクセント核が置かれる結果となります。「墨子」「告子」の場合、ボクシ、コクシのクの部分にいわゆる無声化が生じて、特殊拍と同じようにアクセント核を置くには不安定な位置になります。無声化とは、キシ\(岸)やクスリ ̄(薬)、カ\クチ(各地)の○部分にある母音[i][u]がのどの震えを伴わずに発音される現象のことです。通常は、母音は、のどのふるえを伴って発音されます。無声化が起こるのは、[k]や[s]のような、のどのふるえを伴わない子音、いわゆる無声子音に囲まれることによって、[i]や[u]の母音がそれらと同じ性質を帯びることによります。「墨子」「告子」の場合は、[bokusi][kokusi]の[u]の母音が無声化します。それによって、ボク\シ、コク\シというアクセントはさけられ、ボ\クシ、コ\クシという発音が行われます。
「孟子」や「老子」は、2モーラ目に長音という特殊拍を含むため、モー\シ、ロー\シというふうには発音しません。ほかの場合と同じく、1モーラ目にアクセント核が来てモ\ーシ、ロ\ーシとなるなら、3モーラの「~子」の語は、すべて頭高型というようにまとめることが可能でした。しかし実際には、モーシ ̄、ローシ ̄のように、このタイプのみは、オトの下がる部分のない平板型が基本的な発音として選ばれています。
アクセントのゆれ
3モーラの語は、頭高型が基本的であるという条件が前述の③の語にも及ぶと、ソーシ ̄に対するソ\ーシというアクセントが生じるようです。「孔子」に対し、コ\ーシと発音されるのを何度か聞いたことがあります。あるいは柴田氏のように、人名はモーシ ̄、ローシ ̄、書名はモ\ーシ、ロ\ーシというように使い分けるという人もいます。孔子に関連する書物は『論語』であるため、書名としてコ\ーシという判断はありません。
他方、頭高型が基本の語に平板型のアクセントが聞かれる場合もあります。ジュ\ンシに対するジュンシ ̄、または、ソ\ンシに対するソンシ ̄というアクセントのことです。コーシ ̄やローシ ̄における平板型が、同じく歴史上、名高い人物ということで「荀子」「孫子」にも適用されたアクセントである可能性があります。「性善説の孟子と性悪説の荀子」「孫子の兵法」のようなフレーズは、世間によく知られています。そして、よく知られた物事には平板型のアクセントが生じやすいという傾向があるからです。
まとめ
古代中国の思想家のアクセントについて整理してきました。中国の古典に興味がある人や中国の歴史ドラマや映画に興味がある人にとって、著名な思想家のアクセントは、どう発音すればよいか気になることがあるでしょう。ここでは、その仕組みを記しました。
国語辞典では、固有名詞のアクセントを記載しない傾向がありますが、そういうことばのアクセントこそ、人は辞書で標準的なアクセントを確認したいはずです。アクセントをまったく記載していない辞書であればまだしも、アクセントを載せる方針であるにもかかわらず、固有名詞はその対象外とする辞書は、アクセントに対する考え方が甘いと言わざるをえません。語釈や表記は、載せずに済ませることができないのに対し、なぜアクセントは、編集側の都合で載せたり載せなかったりするのか、という疑問を辞書のユーザーなどから突きつけられ、そしてそれに合理的な回答を与えることが難しいからです。求められることは、しかるべき研究者がアクセント研究の成果をもとにして、全国に通じる標準的なアクセントを堂々と辞書に記すという仕事です。
![]()
中川秀太
文学博士、日本ウェルネススポーツ大学スポーツプロモーション学部 准教授、日本語検定 問題作成委員
専攻は日本語学。文学博士(早稲田大学)。2017年から日本語検定の問題作成委員を務める。
- 最近の研究
- 「現代日本語のジェネレーションギャップ」(2024年、武蔵野書院)
- 「日本語検定と校閲との接点を探る」(2024年、日本経済新聞社の勉強会における発表)
- 「同訓異字の「使」と「遣」」(2024年、毎日新聞の「毎日ことばplus」への寄稿)
- 「「わがこと」「じぶんごと」「ひとごと」「よそごと」「たにんごと」」(『東京女子大学日本文学』121、2025年)
- 「肯定・否定を表す対義的な応答詞の使用によって生じる社会的な分断」(『大正大学研究紀要』110、2025年)
- 「きちんとことばを伝えるための10章」(2025年、共著、朝倉書店)など。
コラム一覧
- 2026.1 (48)「『ほぼほぼ』『やっぱり』『わざわざ』 その副詞は何のために?」
- 2025.12 (47)「『ドッジボール』か? それとも『ドッチボール』か?」
- 2025.11 (46)「デアル体とダ体の詳細」
- 2025.10 (45)「『孔子』や『孫子』のアクセント」
- 2025.9 (44)「比喩的な『続投』が捨てられない理由」
- 2025.8 (43)「1日のうちに行う動作を表す連用形名詞+晩酌」
- 2025.7 (42)「『かき氷』関連のボキャブラリー」
- 2025.6 (41)「代名詞の表記」
- 2025.5 (40)「連体詞の表記②」
- 2025.4 (39)「連体詞の表記①」
- 2025.3 (38)「語頭のラ行音」
- 2025.2 (37)「接続詞の表記」
- 2025.1 (36)「一語文の用法を持つヒト名詞」
- 2024.12 (35)「朝昼晩のあいさつのことば」
- 2024.11 (34)「接頭辞の『ま』『ど』『せい』」
- 2024.10 (33)「相撲の世界における動詞の特別な使い方」
- 2024.9 (32)「数字の語形と表記」
- 2024.8 (31)「ぼかす副助詞」
- 2024.7 (30)「『甲の乙』という形の単語について」
- 2024.6 (29)「母音が連続するときの発音」
- 2024.5 (28)「『現代仮名遣い』と表音一致」
- 2024.4 (27)「動詞のウ音便について」
- 2024.3 (26)「『かな(仮名)』の語形とアクセントと表記」
- 2024.2 (25)「『わかる』のコミュニケーション文法」
- 2024.1 (24)「『よりか』とは何か」
- 2023.12 (23)「『お』と体の部分」
- 2023.11 (22)「質問という行為について」
- 2023.10 (21)「しこ名の『~川』」
- 2023.9 (20)「『~ていただきたいです』という表現について」
- 2023.8 (19)「今に生きる旧国名の別称」
- 2023.7 (18)「『可決・成立する』は是か非か」
- 2023.6 (17)「語頭に[p]の音を持つ単語のこと」
- 2023.5 (16)「『いる』と『おる』の活用形」
- 2023.4 (15)「『ローマ字のつづり方』は実用的か否か」
- 2023.3 (14)「御しがたいひと言『なるほど』のこと」
- 2023.2 (13)「『~犬』はイヌかケンか」
- 2023.1 (12)「『ありか』『かくれが』『すみか』の表記」
- 2022.12 (11)「みずうみ・ぬま・いけ」
- 2022.11 (10)「『お間違いありませんか(お間違いないですか)』に問題はありませんか」
- 2022.10 (09)「現代の1拍語」
- 2022.9 (08)「動植物名を表す漢字について」
- 2022.8 (07)「現代語における女の人の一人称」
- 2022.7 (06)「『水鳥』の語形とアクセント」
- 2022.6 (05)「動物と敬称②」
- 2022.5 (04)「動物と敬称①」
- 2022.4 (03)「『東方・西方』の語形」
- 2022.3 (02)「『母方・父方』の語形」
- 2022.2 (01)「『失礼します』か『失礼しました』か」