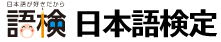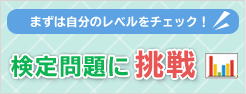副詞は、動詞や形容詞を修飾する語のことであり、その種類には、たとえば「ゆっくり」「堂々と」のような動きのありさまを表す様態副詞(「状態副詞」とも)、「非常に」「とても」のような程度副詞、「あまり(~ない)」「たぶん(~だろう)」のような、述語との呼応(対応)関係を持ち、肯定か否定か、事実か推量かといった送り手(話し手・書き手)の態度を表す陳述副詞などがあります。
以下では、果たして使う必要があるか? という観点から副詞を見渡します。
副詞の使用は控えめに
上記の疑問について、かつて社会学者の清水幾太郎(1907~1988)は、「非常に大きい」と言いたいときにも「大きい」とのみ言うように、控えめにことば選びをすべきであると述べていました。それから、高橋(1955)には「日本人が外国人と話をしているのをよく聞いていると、われわれは実にひんぱんに「非常に」という言葉を使うようだ。ヴェリー・グッド、ヴェリー・ナイス等々。外国人はこの「非常に」という言葉をそうたやすくは使わないのである」との指摘があります。程度副詞の使用は、送り手にとっては気持ちがよくても、受け手(聞き手・読み手)が事実を正確に把握するうえでは、そのノイズ(妨げ)になる恐れがあります。何も、程度副詞を一切使わないように、ということではありません。くだけた会話の中で使うというように、公私のバランスを考えて使えばよいとも言えます。ただし、なるべく控えめにことばを選ぶという清水のことばは、常に意識したいところです。
「ほぼほぼ」の解釈
近年よく使われる「ほぼほぼ」という副詞の問題点は、上記の観点から眺めれば、その本質が捉えられます。若者が使うとか、新語だからとかいったことは問題の枝葉にすぎません。ある人は「ほぼほぼ」を「ほぼ」よりも程度が低い意味で使い(「ほぼほぼできた」は「ほぼできた」より完成度が低い)、ある人は「ほぼ」よりも程度が高い意味で使う(「ほぼほぼできた」のほうが「ほぼできた」より完成度が高い)、それによって受け手が円滑に内容を理解しにくくなっている点が重要です。自信のなさをごまかしたい気持ちが前者の意味を生む一方で、強調したいという気持ちが後者の意味を生み、その二つの意味が「ほぼほぼ」の一語に込められることによって、目の前の相手がどちらの意味で使っているのか、受け手の側で推測しなければならなくなりました。ぼかすことと強調する(盛る)ことは、現代語に見られる大きな特徴です。ただ、「とか」や「一応」はぼかし専用、「まじ」や「めっちゃ」は強調専用であるのに対し、「ほぼほぼ」の場合は、その両方の用途が一語の中に埋め込まれているというのがユニークなところです。
陳述副詞の問題
陳述副詞にも「強調的な意味が出てくるから、ニュースなどの客観的報道には注意を要する」という指摘があります(宮地(1979))。「絶対」「決して」といった副詞は客観性についての強調的な表現となり、不用意に使われると、受け手としては、それは本当かという疑いをいだき、別の意図があるのではないかと勘ぐりたくなります。このことについて、小松(2014)の指摘が有益です。ある学術書の中に、古代の日本語には語頭にラ行音を持つ語が原則として存在しないが、「rという子音は語頭においても決して不安定な子音ではない」から、ほかの言語と比べた場合、語頭のラ行音がないことが日本語の特徴として注目に値する、といった趣旨のことが書かれています。小松はそこに使われた「決して」に着目し、「その可能性が疑われるからこそ加えられた否定の強調である」と述べます。送り手の不安・疑いが「決して」によって図らずも外に現れたと読み取れます。
根拠を問いたくなる副詞
以下では、小松(2014)を手本にして、受け手の印象という観点から2種の副詞を検討します。まず「根拠を問いたくなる副詞」から見ます。たとえば「やっぱり」という副詞は、文の始めにおいて、「(住むのには)やっぱり日本が一番いい」のように使われます。なぜ日本がいいのでしょうか。何らかの方法でほかの国と比べたことがあるのでしょうか。こんなことを言うと「みんながいいと言うから」という反論が返ってきそうですが、「みんな」とは誰のことでしょうか。「日本がいい」の背後に確たる根拠がないとすれば、ほかの国は日本より劣るという判断を、こちらも確たる根拠なく行っていることになりはしないでしょうか。あの国は危ない、貧しい、何もないといった判断を「何となく」行い、いわれのない偏見を持つ結果につながっていないでしょうか。そう考えると「やっぱり」の使用は小さな問題とは言えなくなります。この語が目立つようになった時期を述べたものに山崎(1977)があります。そこには「やっぱり」は1960年代から70年代の初めにかけて「異様に耳につくようになった」とあり、「とりわけ、テレビのインタビューなどで何かを訊ねられると、返答の頭に意味もなく「やっぱり」を加えないと、口をきけない人が目立ったものです」と指摘されています。
同様のことは「意外に(意外と)」にも当てはまります。「意外においしい」「(本や試験の内容が)意外に難しい」などと使いますが、事前にどれだけの予測をしていたことでしょうか。おいしさ、難しさについての予測がまずあり、そこからずれる結果を目の当たりにして「意外に」とするならわかりますが、単に口癖で使っているなら、それはやめて単純に「おいしい」「難しい」と述べるほうがすっきりします。そうでないと「自己紹介などで、「あたしって、意外とシャイなんです」と言う若い人がいた。聞いているほうとしては、「だれも、あなたがシャイでないとは言っていない」と言いたくなる」(佐竹(1997))といった印象につながる恐れもあります。
偉そうに感じる副詞
二つ目に「偉そうに感じる副詞」を検討します。インターネット上の書き込みなどには、飲食店などについてのコメントに「わざわざ○○から来たのに休みだった」などと書いてあることがあります。「遠くから(こんなところまで)来てやったのに」という気持ちがにじみ出ています。店には定休日があり、また、何かの事情で急に休むこともあります。SNSを使って「わざわざ」人に知らせずとも、ただ心の中で残念だなと思えばそれで済むことです。また、ある旅行雑誌に「わざわざ行きたい! 魅惑の空港 大分空港」という広告文がありました。最近こういう「わざわざ」の使い方を目にすることが増えています。「遠く、特に東京からカネと時間をかけてわざわざ行く」という含みが感じられ、現地の人に対して失礼な感があります。「わざわざ」と似た性格を持つ副詞としては「せっかく」が挙げられます。
こうして、受け手の印象という観点から副詞を見直してみると、記述に値する事柄がほかにもたくさんあるような気がしています。ここでは、その一端を記しました。
参考文献
小松英雄(2014)『日本語を動的にとらえる』笠間書院
佐々木絵美(2018)「校閲記者のこの一語⑤「ほぼほぼ」はほぼ、「ほぼ」?」『日本語学』37-11
佐竹秀雄(1997)「若者ことばと文法」『日本語学』16-4
高橋義孝(1955)『落ちていた将棋の駒について』暮しの手帖社
宮地裕(1979)『新版 文論』明治書院
山崎正和(1977)『おんりい・いえすたでい‘60s』文芸春秋
![]()
中川秀太
文学博士、日本ウェルネススポーツ大学スポーツプロモーション学部 准教授、日本語検定 問題作成委員
専攻は日本語学。文学博士(早稲田大学)。2017年から日本語検定の問題作成委員を務める。
- 最近の研究
- 「現代日本語のジェネレーションギャップ」(2024年、武蔵野書院)
- 「日本語検定と校閲との接点を探る」(2024年、日本経済新聞社の勉強会における発表)
- 「同訓異字の「使」と「遣」」(2024年、毎日新聞の「毎日ことばplus」への寄稿)
- 「「わがこと」「じぶんごと」「ひとごと」「よそごと」「たにんごと」」(『東京女子大学日本文学』121、2025年)
- 「肯定・否定を表す対義的な応答詞の使用によって生じる社会的な分断」(『大正大学研究紀要』110、2025年)
- 「きちんとことばを伝えるための10章」(2025年、共著、朝倉書店)など。
コラム一覧
- 2026.2 (49)「『地酒』の語釈」
- 2026.1 (48)「『ほぼほぼ』『やっぱり』『わざわざ』 その副詞は何のために?」
- 2025.12 (47)「『ドッジボール』か? それとも『ドッチボール』か?」
- 2025.11 (46)「デアル体とダ体の詳細」
- 2025.10 (45)「『孔子』や『孫子』のアクセント」
- 2025.9 (44)「比喩的な『続投』が捨てられない理由」
- 2025.8 (43)「1日のうちに行う動作を表す連用形名詞+晩酌」
- 2025.7 (42)「『かき氷』関連のボキャブラリー」
- 2025.6 (41)「代名詞の表記」
- 2025.5 (40)「連体詞の表記②」
- 2025.4 (39)「連体詞の表記①」
- 2025.3 (38)「語頭のラ行音」
- 2025.2 (37)「接続詞の表記」
- 2025.1 (36)「一語文の用法を持つヒト名詞」
- 2024.12 (35)「朝昼晩のあいさつのことば」
- 2024.11 (34)「接頭辞の『ま』『ど』『せい』」
- 2024.10 (33)「相撲の世界における動詞の特別な使い方」
- 2024.9 (32)「数字の語形と表記」
- 2024.8 (31)「ぼかす副助詞」
- 2024.7 (30)「『甲の乙』という形の単語について」
- 2024.6 (29)「母音が連続するときの発音」
- 2024.5 (28)「『現代仮名遣い』と表音一致」
- 2024.4 (27)「動詞のウ音便について」
- 2024.3 (26)「『かな(仮名)』の語形とアクセントと表記」
- 2024.2 (25)「『わかる』のコミュニケーション文法」
- 2024.1 (24)「『よりか』とは何か」
- 2023.12 (23)「『お』と体の部分」
- 2023.11 (22)「質問という行為について」
- 2023.10 (21)「しこ名の『~川』」
- 2023.9 (20)「『~ていただきたいです』という表現について」
- 2023.8 (19)「今に生きる旧国名の別称」
- 2023.7 (18)「『可決・成立する』は是か非か」
- 2023.6 (17)「語頭に[p]の音を持つ単語のこと」
- 2023.5 (16)「『いる』と『おる』の活用形」
- 2023.4 (15)「『ローマ字のつづり方』は実用的か否か」
- 2023.3 (14)「御しがたいひと言『なるほど』のこと」
- 2023.2 (13)「『~犬』はイヌかケンか」
- 2023.1 (12)「『ありか』『かくれが』『すみか』の表記」
- 2022.12 (11)「みずうみ・ぬま・いけ」
- 2022.11 (10)「『お間違いありませんか(お間違いないですか)』に問題はありませんか」
- 2022.10 (09)「現代の1拍語」
- 2022.9 (08)「動植物名を表す漢字について」
- 2022.8 (07)「現代語における女の人の一人称」
- 2022.7 (06)「『水鳥』の語形とアクセント」
- 2022.6 (05)「動物と敬称②」
- 2022.5 (04)「動物と敬称①」
- 2022.4 (03)「『東方・西方』の語形」
- 2022.3 (02)「『母方・父方』の語形」
- 2022.2 (01)「『失礼します』か『失礼しました』か」