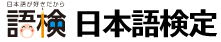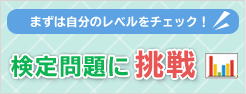荷物を入れる「バッグ」が「バック」と発音されたり、寝台の「ベッド」が「ベット」と発音されたりというように、「濁音+促音+濁音」という構成の語において、後ろの濁音が清音化する現象があります。伝統的な日本語では、「濁音+促音+濁音」の構成の語は一般的ではありません。他方、外来語には少なくない構成です。本来の外国語(bag、bed)としては誤りですが、日本語の一種としての外来語においては、日本語話者にとって扱いやすい、発音しやすい形へと合理的に変化したと見なすこともできます。もっとも、最近は英語教育が進んだことなどもあり、なるべく「バッグ」「ベッド」のように濁音で発音するほうが適切であるという意識を持つ人が増えてきているようです。ここでは、どういう語に濁音→清音の現象が見られるのか、その特徴を整理します。該当する語を集めるにあたっては、『三省堂国語辞典 第8版』を使いました。たとえば「バッグ」の注釈に「なまって、バック」のように記されているのがこの辞書の特徴です。
音声的な条件
「濁音+促音+濁音」において清音化が起こるということは、語頭が「あ」や「い」などの母音には関係のない現象だということでもあります。ナ行、マ行、ヤ行、ラ行、ワ行にも濁点で区別されるオトがないので、対象外となります。
清音化には、後ろの清音が閉鎖音(破裂音)であること、という条件が働きます。閉鎖音は、「か」や「た」のように、発音するには一度、口の中で閉鎖を作る必要があるオトのことです。「ば」のように、両くちびるを閉じるオトがわかりやすい例です。「か」や「た」の場合は、舌(した)と口の中のくちびるよりも後ろにある部分との間で閉鎖が起こっています。閉鎖のあと口をひらく点を捉えて表現したのが破裂音という言い方です。
「ば」や「べ」など、語頭の濁音も閉鎖音です。つまり、清音化する場合、後ろの濁音が清音に変わるという変化が生じていますが、「語頭も語末も閉鎖音である」という特徴は失われずにいる、ということです。その共通点があることによって、オトは少し変化しているが、語としては同一のものという捉え方が可能になるのでしょう。
以上の説明に当てはまるのが「グッド→グット」(good)、「バッグ→バック」(bag)、「ビッグ→ビック」(big)、「ベッド→ベット」(bed)といった例です。「ビック」という同音語が存在しないから「ビッグ」を「ビック」としても問題が生じない、と言いたくなりますが、「バック」には「後ろ」、「ベット」には「賭け事」という意味がありますから、同音語の有無が即座に清音化を妨げる決定要因にはなりえないことがわかります。同音語があってもなくても、清音化は生じうるというふうに言いかえることもできます。
語末がザ行の場合、「グッズ→グッツ」(goods)、「バッジ→バッチ」(badge)のように、サ行ではなく、タ行のオトに変わります。ザ行、サ行、タ行は、発音するのに使う口の場所が(ほぼ)同じです。ザ行は歯ぐきのところで発音する破擦音であり、「閉鎖」という特徴をタ行と共有します(実際には語中のザ行は閉鎖を伴わずに発音されることが多いですが、ここでは規範的には閉鎖があるという立場で書いておきます)。破擦音は、閉鎖音(破裂音)のあとにすぐに摩擦音が続くオトのことを言います。
他方、サ行は同じく歯ぐきのところで発音するオトではありますが、閉鎖のない摩擦音であるところがザ行、タ行と異なります。摩擦音は、発音(調音)器官が接近はするものの、閉じはしない、という特徴を持つオトです。サ行やハ行がこれに当てはまります。閉鎖音および破擦音に対し、摩擦音は、オトの印象がだいぶそれらと異なります。「ズ」「ジ」に関して、清音化が「グッツ」「バッチ」のように「ツ」「チ」のオトで実現され、「グッズ→グッス」「バッジ→バッシ」とならないのは、以上のような事情によります。
語頭の濁音は、半濁音つまりパ行でもかまいません。「パッド」が「パット」となるのが具体例です。ハ行、バ行、パ行は、ハ行が口の奥のほうで発音する摩擦音であり、バ行、パ行がくちびるで発声する閉鎖音です。
長い語における清音化
3モーラの語の場合、清音化すると同音語とバッティングするという問題が生じますが、たとえば「キューピッド」(cupid)のような長い語(ここでは5モーラ以上の語を長い語としておきます)では、「キューピット」にしたところで、ほかの語と紛れる恐れがありません。「ドッグ」(dog)単独では「ドック」にしにくくとも、「ブルドッグ」を「ブルドック」とするのは抵抗がないというのも同様です。工藤(2012、p.89)には「「ブルドック」ソースのラベルにはBULLDOGとあった」という指摘が見られます。
インターネットには、「ゴッドハンド(godhand)→ゴットハンド」「デッドロック(deadlock)→デットロック」「バッドニュース(badnews)→バットニュース」「ポッドキャスト(podcast)→ポットキャスト」といった例も出てきます。
「ドッジボール(dodge ball)→ドッチボール」という例もあります。語末の清音は閉鎖音という条件がありますから、「ドッシ」ではなく「ドッチ」です。英語のdodgeは、「かわす」「よける」という意味です。
時折、「ドッチ」という語があり、それが「ボール」とくっついて「ドッヂボール」という語ができたと誤解している人がいます。先ほど述べたように、英語のdodgeを取り入れたのが外来語の「ドッジ」です。現代語では、外来語に「ヂ」は使わないというルールがあります(料理の「チヂミ」は例外)。したがって、「ドッヂ(ボール)」という書き方はしません。なお、「ダッグアウト」に対する「ダグアウト」のように、促音を削ることによって、発音しやすくしているとおぼしい例もあります。また、毎日新聞社校閲センターの平山泉氏によると、新聞の原稿段階では「ギングリッチ」(アメリカの政治家)が「ギングリッジ」で出てくることがあったそうです。必要のない事例にも「チ→ジ」という意識が働く、過剰修正と呼ばれる現象の一例です。
Zの場合
ここまでの例からわかるように、語末は、濁音であるのが正式な言い方です。すると、アルファベットの最後の文字であるZ・zが「ゼット」と一般的に発音されるのは不思議です。「ゼッド」のほうが正式だという考え方がないからです。固有名詞であえて「ゼッド」を使っている場合は別ですが、普通名詞としては「ゼット」が広く用いられます。山下(2021)によると、江戸時代から昭和にかけて刊行された英語の辞書や教科書に示されるZの「読み方」はジー、ズィー、ズイー、ゼットなどでゆれていたそうです。「ゼット」の古い例としては『異人詞入和洋五体以呂波』(1872)によるものがあがっています。そして、同論文の「アルファベットの読み方の変遷(江戸~昭和)」の表に「ゼッド」がないのが注目されます。早いうちから「ゼッド」ではなく「ゼット」で発音されやすかったということです。山下(2017、p.100)の「イギリス英語では「ゼッド[zed]」、アメリカ英語では「ズィー[ziː]」だが、日本語ではほとんどの場合「ゼット」」という指摘も参考になります。
では、どうしてZのみ、語末が清音で固定し、濁音が出てきにくいのでしょうか。それは、Zが単字(「ただ一つの文字。一字」(『日本国語大辞典 第2版』)であり、複数の文字からなるつづりを意識することがないことが理由でしょう。あまりにも単純な理由であり、もっと複雑な理由を求める人にとってはもの足りないかもしれません。しかし、bedやbagなどが複数の文字からできていて、そこに「ベッド? ベット?→bed→ベッドだ」というような思考過程がありうるのに対し、Zには、そのプロセスが存在しないということは、無視できない大きな差であり、十分おもしろいことだと考えます。
まとめ
「濁音+促音+濁音」の清音化は、外国語から取り入れたことばを日本語らしく取り扱うための工夫の一種であると見ることができます。しかし、外国語、特に英語とのつきあいが深くなってきたこともあり、徐々に上記の構成の語を苦にせず発音することができる層が増えてきました。100年後の日本語話者の発音実態はどうなるでしょうか。
参考文献
石野博史(1983)『現代外来語考』大修館書店
工藤力男(2012)『日本語に関する十二章』和泉書院
山下洋子(2017)「放送用語委員会(東京) 外来語としての「アルファベット」の発音」 『放送研究と調査』67-6
山下洋子(2021)「日本語におけるアルファベットの語形の変遷」『立教大学大学院日本文学論叢』20
![]()
中川秀太
文学博士、日本ウェルネススポーツ大学スポーツプロモーション学部 准教授、日本語検定 問題作成委員
専攻は日本語学。文学博士(早稲田大学)。2017年から日本語検定の問題作成委員を務める。
- 最近の研究
- 「現代日本語のジェネレーションギャップ」(2024年、武蔵野書院)
- 「日本語検定と校閲との接点を探る」(2024年、日本経済新聞社の勉強会における発表)
- 「同訓異字の「使」と「遣」」(2024年、毎日新聞の「毎日ことばplus」への寄稿)
- 「「わがこと」「じぶんごと」「ひとごと」「よそごと」「たにんごと」」(『東京女子大学日本文学』121、2025年)
- 「肯定・否定を表す対義的な応答詞の使用によって生じる社会的な分断」(『大正大学研究紀要』110、2025年)
- 「きちんとことばを伝えるための10章」(2025年、共著、朝倉書店)など。
コラム一覧
- 2026.1 (48)「『ほぼほぼ』『やっぱり』『わざわざ』 その副詞は何のために?」
- 2025.12 (47)「『ドッジボール』か? それとも『ドッチボール』か?」
- 2025.11 (46)「デアル体とダ体の詳細」
- 2025.10 (45)「『孔子』や『孫子』のアクセント」
- 2025.9 (44)「比喩的な『続投』が捨てられない理由」
- 2025.8 (43)「1日のうちに行う動作を表す連用形名詞+晩酌」
- 2025.7 (42)「『かき氷』関連のボキャブラリー」
- 2025.6 (41)「代名詞の表記」
- 2025.5 (40)「連体詞の表記②」
- 2025.4 (39)「連体詞の表記①」
- 2025.3 (38)「語頭のラ行音」
- 2025.2 (37)「接続詞の表記」
- 2025.1 (36)「一語文の用法を持つヒト名詞」
- 2024.12 (35)「朝昼晩のあいさつのことば」
- 2024.11 (34)「接頭辞の『ま』『ど』『せい』」
- 2024.10 (33)「相撲の世界における動詞の特別な使い方」
- 2024.9 (32)「数字の語形と表記」
- 2024.8 (31)「ぼかす副助詞」
- 2024.7 (30)「『甲の乙』という形の単語について」
- 2024.6 (29)「母音が連続するときの発音」
- 2024.5 (28)「『現代仮名遣い』と表音一致」
- 2024.4 (27)「動詞のウ音便について」
- 2024.3 (26)「『かな(仮名)』の語形とアクセントと表記」
- 2024.2 (25)「『わかる』のコミュニケーション文法」
- 2024.1 (24)「『よりか』とは何か」
- 2023.12 (23)「『お』と体の部分」
- 2023.11 (22)「質問という行為について」
- 2023.10 (21)「しこ名の『~川』」
- 2023.9 (20)「『~ていただきたいです』という表現について」
- 2023.8 (19)「今に生きる旧国名の別称」
- 2023.7 (18)「『可決・成立する』は是か非か」
- 2023.6 (17)「語頭に[p]の音を持つ単語のこと」
- 2023.5 (16)「『いる』と『おる』の活用形」
- 2023.4 (15)「『ローマ字のつづり方』は実用的か否か」
- 2023.3 (14)「御しがたいひと言『なるほど』のこと」
- 2023.2 (13)「『~犬』はイヌかケンか」
- 2023.1 (12)「『ありか』『かくれが』『すみか』の表記」
- 2022.12 (11)「みずうみ・ぬま・いけ」
- 2022.11 (10)「『お間違いありませんか(お間違いないですか)』に問題はありませんか」
- 2022.10 (09)「現代の1拍語」
- 2022.9 (08)「動植物名を表す漢字について」
- 2022.8 (07)「現代語における女の人の一人称」
- 2022.7 (06)「『水鳥』の語形とアクセント」
- 2022.6 (05)「動物と敬称②」
- 2022.5 (04)「動物と敬称①」
- 2022.4 (03)「『東方・西方』の語形」
- 2022.3 (02)「『母方・父方』の語形」
- 2022.2 (01)「『失礼します』か『失礼しました』か」